2025年9月1日 午前7時30分
【論説】江戸時代にオランダ語を通じて受容され、独自に発展した蘭学。福井は杉田玄白や笠原良策(白翁)ら蘭学に接し、明治以降の日本近代化の礎となった人材を多数輩出した。近年、こうした先人を顕彰する動きが続いている。この機会に蘭学と福井のつながりへの理解を深め、人材育成や魅力ある地域づくりに生かしたい。
昨年は、小浜藩医・杉田玄白らの「解体新書」出版から250年。これを記念して県と小浜市は、同市で「蘭学サミット」を開催した。日本初の西洋医学の解剖書である解体新書は、観察の重視など科学的思考を根付かせた。
サミットに出席した作家で医師の海堂尊さん(福井県立大客員教授)は昨年、大坂で蘭学塾・適塾を開いた緒方洪庵らを主人公とした歴史小説「蘭医繚乱 洪庵と泰然」を出版。この中で、適塾で蘭学を学んだ福井藩の橋本左内や大野藩で教えた塾頭伊藤慎蔵らの活躍も描いた。
執筆にあたり多くの研究者を取材した海堂さんは、作品で紹介しきれなかった偉人の逸話などを一般の人にも知ってもらおうと「蘭医学サロン」を企画。幕末に天然痘の予防のため種痘を広めた福井の町医者・笠原良策をテーマに、今年8月に福井市で第2回蘭学サミットと合同開催した。
良策を主人公として今年公開された映画「雪の花―ともに在りて―」の上映もあり、県内の研究者らが種痘の意義や良策の人物像について多面的に語り合った。
こうした催しや作品を通じて見えてきたのは、蘭学先進地としての福井。そこで県は「ふくいで花ひらく蘭学」と題したリーフレットを作製した。「杉田玄白の解体新書が種となり、笠原白翁の種痘や福井藩の近代化へとつながった」と解説し、適塾で学んだ、あわら市出身の村医・藤野升八郎や、その息子で中国の文豪魯迅の師・藤野厳九郎らも紹介。厳九郎については、同市日中友好協会が「ゆかりの地MAP」も作製した。映画「雪の花」のロケ地マップもあり、これらを用いて蘭学と福井の関わりを発信し、教育や観光に役立てたい。
一方、鎖国下の江戸時代に蘭学が発展した歴史を振り返ると、8代将軍・徳川吉宗の存在が大きかった。吉宗は洋書の輸入制限を緩和し、積極的に海外の知識を導入した。福井市立郷土歴史博物館で開催中の特別展「松平春嶽と勝海舟」(7日まで)では、海舟が吉宗を高く評価していたことを示す春嶽宛ての手紙も出品されている。海舟が出世した原点にも蘭学の猛勉強があった。こうした先人たちに共通する異国文化への好奇心と学問への情熱、それを社会に役立てようという高い志を受け継ぎたい。

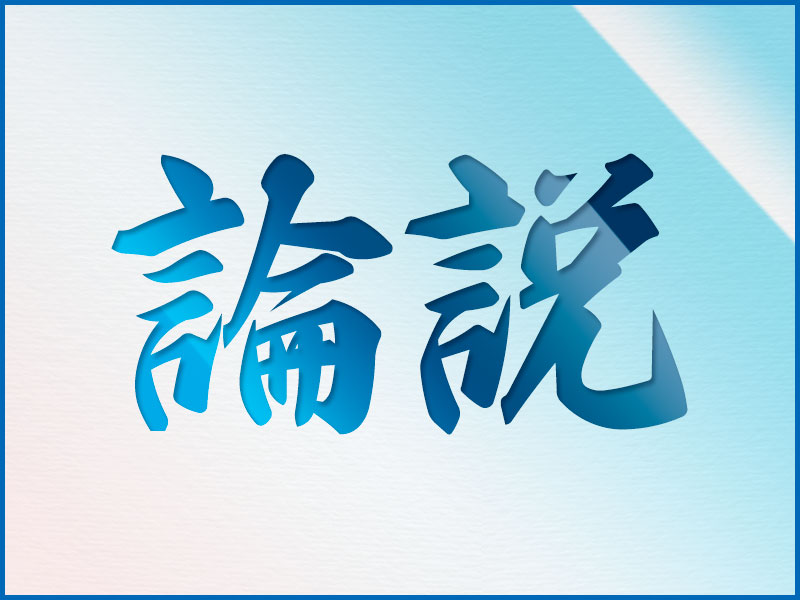
WACOCA: People, Life, Style.