.jpg)
※雑誌『WIRED』日本版 VOL.55 特集「THE WORLD IN 2025」の詳細はこちら。
世界中のビジョナリーや起業家、ビッグシンカーがキーワードを掲げ、2025年の最重要パラダイムを読み解く恒例の総力特集「THE WORLD IN 2025」。天文学者のリサ・カルテネッガーは、太陽系外惑星の大気の中についに分子を検知する可能性に期待を寄せる。
2025年、わたしたちはこの銀河系の外に生命が存在する兆候を、初めて発見するかもしれない。
この大発見を成し遂げるために欠かせないのが、口径6.5mのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)だ。21年、フランス領ギアナの海辺の町クールーからロケット「アリアン5」に載せて打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、宇宙望遠鏡としてこれまでのところ世界最大のサイズを誇っている。このジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によるデータの収集が始まって以降、天文学者たちは、比較的古い銀河やブラックホールといった、宇宙の最も薄暗い天体を観測することができるようになったのだ。
関連記事:天の川銀河の新たな観測結果は、その特殊な成り立ちの再定義を迫る
関連記事:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が初期の宇宙のあちこちに巨大ブラックホールを発見
だがおそらくそれよりもっと重要なのは、22年、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測により、天文学者たちがハビタブルゾーン(生命居住可能領域)と呼ぶ場所の中に、岩だらけの太陽系外惑星を初めて確認したことだろう。ハビタブルゾーンとは、ある恒星の周囲にある、液体の水分が存在するのにふさわしい温度をもった領域のことで、その領域を回る惑星の岩だらけの表面の下には、わたしたちが知っている生命が存在するための重要な要素のひとつである液体の水が存在している可能性があるのだ。
この地球サイズの惑星たちは、「トラピスト1」と呼ばれる赤色矮星の周りを周回している。トラピスト1は地球から40光年の距離にあり、質量は太陽の10分の1ほどしかない。赤色矮星は太陽に比べて低温でかなり小さいため、その周囲を周回している地球サイズの惑星を検知することは比較的容易にできる。
とはいえ、そういった太陽系外惑星の発する信号はたいていの場合、それらよりずっと明るい主星の発する信号に比べてかなり弱い。こうした惑星たちを発見できたのは、技術的に極めて難易度の高い偉業だったといえる。
大気の中の分子を検知する
次なる課題は、そういった惑星の大気の中に分子を検知することだが、これには天文学的にさらに高度な技術が必要となる。
惑星がその主星である恒星とわたしたちとの間を通り過ぎるたびに、恒星の光は惑星の大気を通過する。その際に恒星の光は通り道にある分子に衝突し、スペクトル吸収が起こる。この現象を探し、確認するのは非常に難しい。
それを実現するには、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って数回分の惑星通過のもたらすデータを集めることにより、主星からの信号を抑えつつ、岩だらけの惑星の途方もなく薄い大気層中に存在する分子の特徴を増幅しなければならないのだ(この惑星の大気の層がどれくらい薄いかというと、例えば惑星がリンゴぐらいのサイズだとすると、その大気はリンゴの皮よりもさらに薄いことになる)。

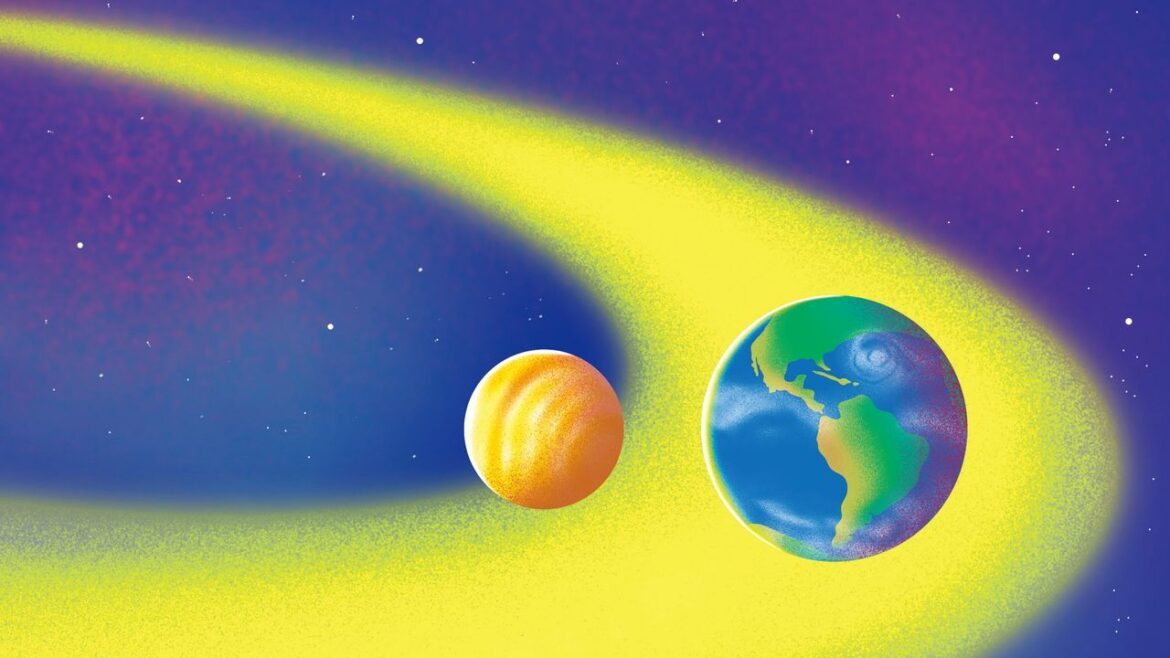
WACOCA: People, Life, Style.