
────────────────────────────
─<<<「どうする家康」 関連動画>>>─
「どうする家康」予習解説

──────────────────────────────
※画像使用について
動画内で使用している画像はNHKが公式に発信している画像のみを引用の上で使用しております。
スクリーンショット等の画像は使用しておらず、著作権者は(C)NHKとなります。
──────────────────────────────
#どうする家康 #徳川家康 #松本潤
#有村架純 #松重豊 #岡部大 #大森南朋
#杉野遥 #山田裕貴 #岡田准一
#酒向良 #ムロツヨシ
#久保史緒里 #板垣李光人
#日本史 #歴史 #古沢良太

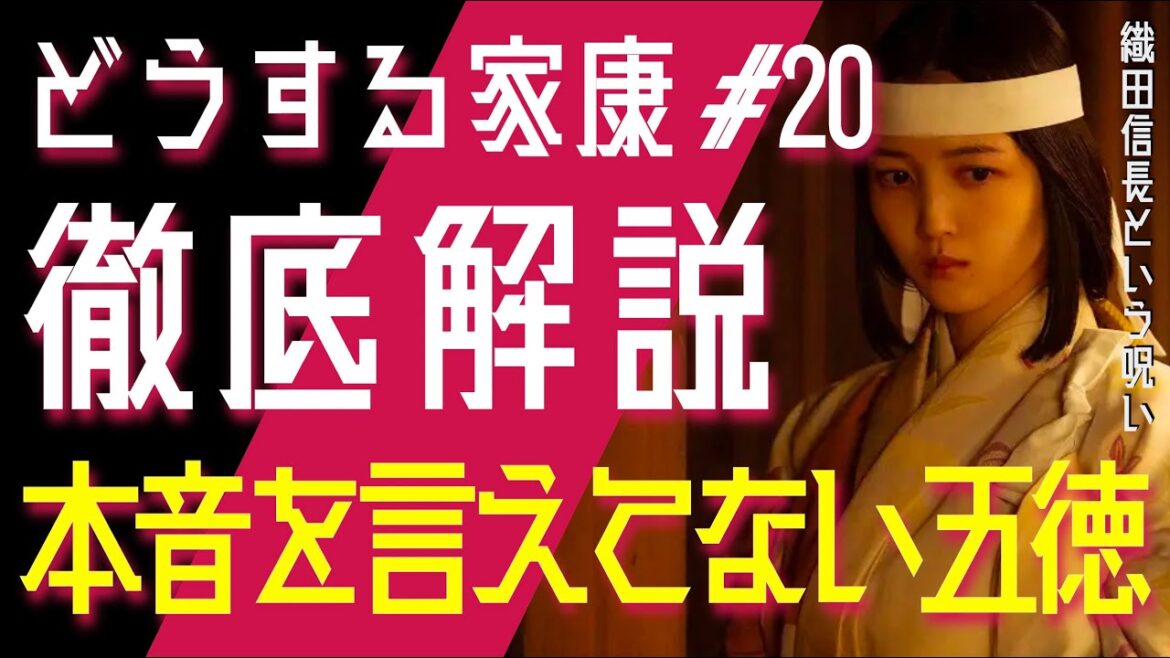





28 Comments
おっしゃっる通り、松平家は20近くあり、伊井家はガチ名家で、交渉にはガチ名家が優位だったので、交渉でストレスいっぱいだったそうですね。
五徳が二言目には「織田信長の娘」と言いますが、プライドと同時に私も、五徳は「自分にはそれしかない」と思っていると感じました。嫡男を産めず、何かの才があるわけでもなく、役に立てていないと認識しているからこそ、自分を保つために父親の権力に頼らざるを得ない点で、偉大な父親を持つ息子だけでなく娘もたいへんなのだと描かれているのだと思いました。
細かいことかもしれませんが、吉田城は愛知県豊橋市(東三河)で、浜松は静岡県浜松市(遠江)なので「浜松の吉田城」は違和感があります。
ヤギシタさん動画アップありがとうございます。
どんどん面白くなってるドラマですね
孤独感漂う五徳のシーンが引きたって見えました。
八蔵から聞き出すなんて さすがいい演出で どうやって助かるんだろうって夢中で観ていたので
45分があっという間で しかも次回へ続く千代〜
来週が今から楽しみ過ぎてどうしよう
五徳、こわい((((;゚;Д;゚;))))カタカタカタカ
今回の大河こわい人の描き方、上手い!
悪い人の描き方ではないです(ᵔᴥᵔ)
山田八蔵が言った「すまぬ」も、真実を知る前と知った後とで意味が全く違うものとなり、まさに「コンフィデンスマンJP」の手法だと思いました。
瀬名が積極的に千代をおびき寄せるといった場面を見て思うのですが、今回の古沢脚本では、史実をうまく使って従来とは全く違った瀬名像(瀬名の再評価となるドラマ)にするんじゃないかなと今からワクワクしております。
五徳と瀬名=嫁と姑
嫁だけが血の繋がりがないんですよね
瀬名に、自ら動くように言われても、ヤギシタさんが言われるように、どうしたら良いか分からなかったと思います
嫁姑の確執が、残酷な結末の一面となる伏線ですね
五徳、孤立していますが、これから起きる事を考えると怖いです
ヤギシタさん、理路整然とされている解説、素晴らしいです
予習解説で気付きましたが髪を短くされ爽やかです
人の本音と建前、そしてうかつさをまざまざと見せつけられた気がします。
五徳はこのような汚い者たちをなんて言ってても本当は恐くて何にも出来ないことを隠してるし、大岡弥四郎は戦に駆り出されるのがうんざりだとまくし立てるけど武田についたところで変わらないというやけくそになってるだけだし、瀬名は千代を呼び出して籠絡しようとするが実際は・・・と( ̄▽ ̄;)
そしてこの方々はみんな一様に諸々迂闊さが目立ちますね。
何でもかんでもお父上に報告するとか、とうの昔にばれてるのに傘型の連判状を書くとか、既に勝頼に読まれてるのに千代を絡め取ろうとするとかほんとに迂闊です(笑)
来週以降も見なければ分かりませんが、行先を分かってるので(ノ∀`)アチャーという感じです。
勝頼をここまで高く評価してるのは過去のドラマや映画でもなかなかないと思います。
信長を持ってして「信玄に勝るとも劣らない逸材」と言わしめるΣ(゚ω゚ノ)ノ
事実勝頼の時代に信玄の時代より領土拡大してますからね( ̄▽ ̄)
今回はいつも以上に鼻をいじくるのが目立っていたが、何でそんなにいじくるのかな⁇
五徳も、折れる事が出来ればあれほど孤立することはないのでしょうけど、まぁ、難しいのでしょうかね。
後、今回のタイトル「岡崎クーデター」、大岡達の反乱はもちろんですが、瀬名の個人的な判断で千代を自宅に呼び寄せて会ったと言う事もクーデターだと言えるのではないでしょうか。
私が今回「あ!」と思った箇所は、石川数正が「今は誰が寝返っても不思議はござらぬ」と言った所です!
今回は瀬名と五徳のお嬢様対決が見物でしたね。
徳川家のために自ら率先して動く瀬名vs信長の娘というプライドに縛られて、動けない五徳。
いよいよ瀬名のラストに向けて動き始めたなという感じですね。
武田勝頼は信玄でも落とせなかった高天神城を落としたり、一時期は武田家史上最大領地を支配した実績があるので、そんな勝頼の能力を見抜く信長はさすが先見の明がありますね。
ラストシーンの瀬名と千代の対面は震えました!!
シャーンという音を一回聞けば「千代だ!」と身構える体にさせられてしまったようです笑
毎回、素晴らしい考察動画をありがとうございます。
第20話では「岡崎クーデター」のタイトル通り大岡弥四郎による謀反が主題でしたが、なぜ大岡がクーデターに走ってしまったのかを考えた時、その大きな理由(背景)の一つは、主君である家康との「距離感」だったのではないかと私は思いました。
ここからは私の勝手な想像(妄想)ですが、家康が岡崎にいた頃そばで仕えていた大岡にとって、頼りなさげでありながらも懸命に頑張る家康を間近に見ることで、徳川家を盛り立てていこうという気概をその当時は強く持っていたと思います。
しかし家康が浜松に移ってしまった時から、大岡にとっては家康との距離、物理的なだけでない心の面も含めた距離感(被害者意識のようなもの)が知らず知らずのうちに積み重なり、次第に家康の真の姿が見えづらくなってしまったのではないでしょうか。
この点で対比されるのが、物語の後半で家康の正式な家臣となる井伊虎松です。
井伊も大岡と同様に、武田家と徳川家とを比べた場合、強大で力強い武田家に自身の故郷を治めてもらうほうが良いと当初は考えていました。
ですが結果的には大岡が家康を裏切る一方で、逆に井伊は家康の家臣になった。
この違いは、心の距離感が出来てしまった大岡に比べ、井伊は家康のいる浜松にいて家康を身近に感じ、かつ領民の様子を通じて家康がどのような主君であるかを自分の肌で感じ取ったからだと思います。
同じく家康を裏切った本多正信は、一向一揆の鎮圧後に家康と直に対面しその時に改めて家康の人間性に触れ、最後去る前に家康に貴重な助言をしていました。
大岡も、捕まった直後(あるいはクーデターを起こす前)に家康と直に話し合い、自分の思いを家康に直接ぶつける機会があったらよかったのにと勝手に想像してしまいました。この点で私は、大岡を「不幸な人物だった」と感じた次第です。
以上です。今回も、長文ご容赦ください。
所領の団子屋の柴田理恵さんがライバル枠なの面白いですね😂
今回で徳川四天王が揃い踏みしましたね( ´ ▽ ` )ノ
これまでいくつも家康が出て来る大河ドラマとか時代劇あったけど、四天王が全員出るのあんまりないんですよね。
直近だと直虎だったかな。
お万からの
男には戦のない世は作れない。お方様のような方であれば…
という祈りのようなことばは、
瀬名に、今こそ勝負どころ、と高揚させ、
あのような行動に導かれたのかもしれませんね。
仏教用語としての「無間地獄(サンスクリット語ではAvici)」の読み方は「むけんじごく」です…。
このドラマの中で
“あほたわけ”という言葉がよく出てきますが、これは何か深い意味があるのでしょうか?
五徳姫に関しては
流石、久保ちゃん
といったところでしょう。
怖くて鳥肌が立ちました。
普段の久保ちゃんを知っている
ということもあり
ギャップがすごかったです。
瀬名がクーデターの陰に千代の暗躍があったことに気付いたのは,戦が続いて疲弊している民衆(今回は岡崎の武士)に,食料や色欲といった俗物的な欲求を与えることで相手を洗脳(コントロール)して体制に反旗を翻させるという手法が三河一向一揆の時の民衆が重なったからのようですね。
一向一揆の時には,本證寺が不入の権と本願寺ネットワークの交易を背景に,今川の戦にかり出される三河の民に,食料を与え,歩き巫女の妖しい踊りと自由な男女交際,現世の罪は現世限りで救われるという宗教の力を背景に民衆を洗脳・扇動して,一揆(反乱)を誘発し,近しい家臣までもそれに巻き込まれました。
今回は,武田という強大な軍事力と金山による経済力を背景に,織田家の戦にかり出される岡崎の家臣団に,織田勢力からの脱却と大岡弥四郎が語ったような「いいものを食っていい女を抱く」という俗物的な欲求をちらつかせて家臣団を洗脳・扇動して,クーデター(反乱)を誘発しました。その手口が全く同じであることを,瀬名が混乱の渦中で見抜いたというシナリオでした。
その手法は千代のこれまでの人生が反映されており,戦乱に疲弊した民にどのように向かい合うべきかを瀬名が示すことで対決しようと考えたのではないでしょうか。(予告編からの予想です。)
その政治的センスは,お万が前話で指摘したとおりで,女性である瀬名が政治を行えばという伏線を回収するとともに,家康を飛び越えた行動が家康をはじめとする男どもにどのように映るかが今後の悲劇への序章となるのでしょうか。
また,五徳との嫁姑の関係が問題をややこしくしそうですね。五徳もあまりにも家風の違う家に嫁ぎ,自分のアイデンティティである幼少期からの価値観(弱肉強食の織田家)と嫁ぎ先の価値観(和気藹々の徳川家)のギャップに苦しんでいるようですね。昔から面々と続く嫁姑問題の本質を見事に言い当てていると思います。(別に鬼嫁や鬼姑がいるのではなく,価値観を共有できない二人があまりに近い距離にいて,互いにうまく譲り合えないだけなのでしょうが…)
五徳と瀬名の会話…
先週の回で五徳の説得にうなずいて浜松で瀬名と家康が一緒に住む事になってたら信康と瀬名は後のあんな事にはなってなかったのかも…と思います。
前回から瀬名(有村架純)さんの退場のカウントダウンは始まって今回の五徳の「織田の娘」の言葉で導火線に着火された音が私には聞こえました…
同郷の久保ちゃんの活躍は嬉しい事ですがドラマとはいえ有村架純さんとバチバチになるシーンは複雑な気持ちです。
五徳がことさらに「信長の娘」を強調するのは、その事実がこころの拠り所であると同時に、父親への美化された憧れでもあったのだと思います。
現代のように18歳以上になってから結婚するのではなく、ほんの子どもの頃に輿入れ。
そして信長は戦で留守にすることも多いうえに、何人も側室がいる。
そんな状態で五徳が信長と接することができたのはとても少なかったと思います。
父親の記憶が少ないからこそ、将軍に「父」と呼ばれたり、“天下布武”を掲げたりしている話を聞くにつれ、どんどん父親像が美化されていったのではないでしょうか。
そして、女性が輿入れするイコール人質の意味合いもあった当時。
建前としては織田と徳川は同格の同盟だけど、実質は織田のほうが格上。
亀姫が織田の男子に嫁ぐならともかく、なぜ自分が?という思いもあったと思います。
もしかしたら織田を出る時に信長から「お前は人質ではない。信長の名代のようなつもりで、信長の娘であることを誇りと思え」とか言われていたのかもしれません。
滅多に会えない、会えたとしても母親や侍女たちと一緒だったり、ほかの兄弟と一緒に会い、そんなに言葉をかけてもらえることはできなかった、遠い存在の父親。
その父親が嫁ぐ前夜、二人だけで自分だけに言葉をかけてくれた、その記憶が五徳のプライドの基となり、支えとなった。
そんな風に想像してしまいました。
世間一般のとらえ方として「桶狭間で(油断して)信長の奇襲を受けて死んだ今川義元」「長篠で(無謀な戦をして)大敗し、武田滅亡を招いた武田勝頼」であるのに対し、義元は当代きっての名将であった、勝頼は信玄時代よりも領土を拡大した名将であったという再評価がされているのが印象深いです。どちらも「家康目線」ならばドラマで描いたような人物像だったと思います。
今回から虎松が本格的に参戦していましたね。小柄な身体をいかして忍者のようにすばしっこい戦い方が良かったです。
榊原小平太に生意気な口をきいて「誰に口をきいている」と叱られていたけれど小平太も最初の頃平八郎たちに生意気なことを言っていたよなと思いました。小平太も成長したんですね〜。
殿に「あの小僧は使えそうか?」と聞かれた平八郎と小平太が顔を見合わせてしぶしぶ「ああ、まあ…」と答えているところが笑えました。
井伊家の出身でプライドの高い虎松はこの先もたぶん色々生意気なことを言うんだろうなと思います。平八郎たちとのやりとりが楽しみです。
井伊直政がなぜ家康につくようになったか?てっきり家康の勇ましい姿を見て心変りしたのかと思ったが、民が笑える主君のほうがいいとは、意外だったけど、説得力ある理由でした。益々これからの展開が楽しみです。何回私達を驚かせてくれるか😄
どうする家康で繰り返し観られるのが「対比構図」であり、それこそ古沢さんらしい描き方だと思います。今回で言えば大岡弥四郎と虎松、そして瀬名と五徳。
目の前の戦いを終わらせるために武田へつくのも、民の幸せと国の平和のために徳川を選ぶというのもどちらも一理ある。
また、帰る場所を無くし三河のおなごとして生きていかなければならなかった瀬名が、偉大なる父・信長の娘として生きていかなければならない五徳に自分と同じ生き方を求めるのは難しかったのではないでしょうか。
ただ、対比させてもどちらか一方を正義として描く事はしていません。
どちらにもそれぞれの正義があるし、だからこそすれ違う悲劇や物語の深みというものが増すのだと感じます。
藤吉郎に桶狭間の裏側を語らせた時の「ものの見方という話でごぜぇます」というセリフにも通じるような気がします。