
政所の別当として幕府政治を取り仕切った大江広元。
実質的に幕府のトップであった広元は、将軍第一の姿勢を崩さなかった一方、幕府政治の安定を第一に北条氏を支援し、後の北条執権政治の基礎も作り上げました。
本来ならば息子の大江親広が、北条氏とともに政権を担い、北条独裁体制とはならなかったはずが、承久の乱で計算が狂い、広元死後、大江氏は再び権力のトップに返り咲くことはありませんでした。
ですが、広元の残した政治遺産は、北条泰時に引き継がれ、御成敗式目、吾妻鏡へとつながり、鎌倉幕府そのものを形作っていくこととなります。
今回は、北条氏と手を結び、新たな幕府の形を作り上げた大江広元の後半生を、息子の大江親広の動きと合わせて紹介します!
———————————–
参考文献
上杉和彦『大江広元』(人物叢書)
https://amzn.to/3GLEnzJ
———————————–
レキショック Twitter
今日はなんの日? その日にまつわる歴史のできごとを毎日発信しています!
レキショック WEBサイト
https://rekishock.com/
【画像引用】
大河ドラマ鎌倉殿の13人公式サイト
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/
大河ドラマ鎌倉殿の13人公式Twitter
#鎌倉殿の13人 #大河ドラマ #歴史

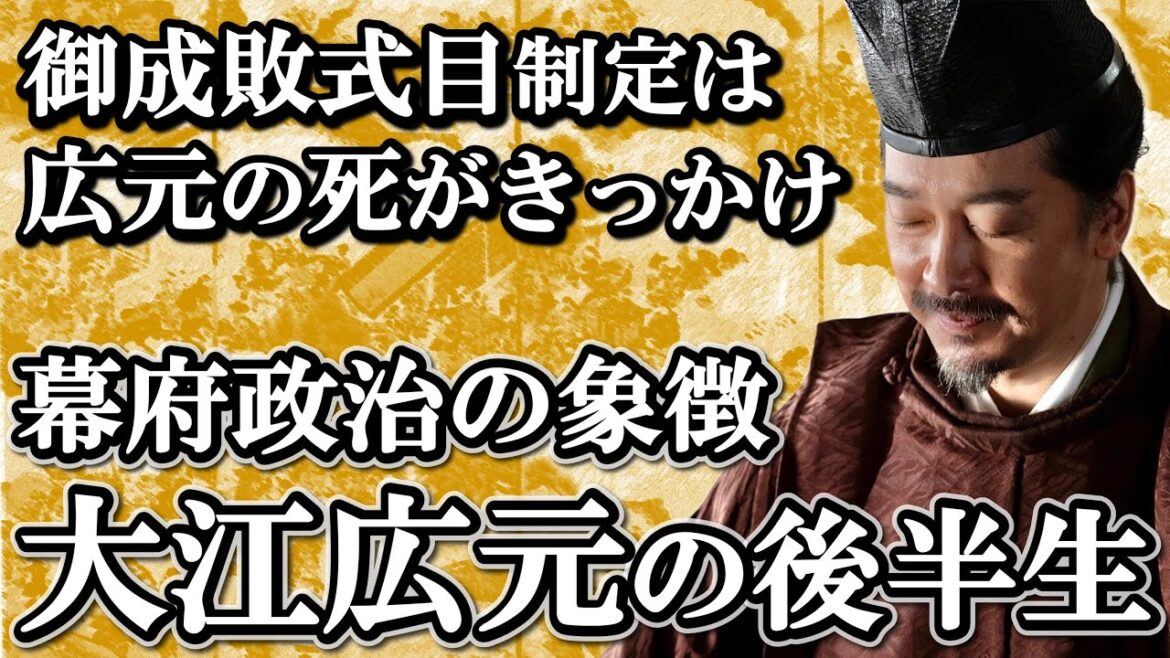
5 Comments
広元の後胤の元就や隆景の登場を
待ってやっと天下の事業に、
携われる様になるまで
長かったですね。
大江ひろもとが大政治家であったことが明確に伝わる動画でとても面白かったです
大江広元は承久の乱では、心穏やかではなかったでしょうね。実子親広が土御門通親の猶子であったため、朝廷側につかざるを得なかったのは、父親として辛かったはずです。しかし、立場上それを表明することも許されず、幕府側トップとして戦うという苦渋の決断をしたのでしょう。戦国時代に限らず、この頃から親子間での戦は行われていたのですね。親子が安穏と暮らしていける現代の幸せを実感します。
大江親広失脚後は、弟の長井時広が活躍する。
承久の乱後には、京都で北条泰時や時房を補佐し、六波羅探題設立に活躍した。
その後時広の長男は鎌倉に戻り、その子孫は鎌倉幕府評定衆家として続く。
そして次男とその子孫は、六波羅評定衆筆頭として、六波羅探題を支え続けた。
重大事が起きたときなどには、長井氏が鎌倉から京都に使者として派遣されることも多かった。
毛利家 大江広元