ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。
今回は、故・松岡正剛氏が所長を務めていた編集工学研究所の社長、安藤昭子氏の『問いの編集力』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を紹介する。AIに答えを求める前に大切にすべき「問い」をどのように生み、育てるか。その具体的なヒントを紹介する。
本稿は「Japan Innovation Review」が過去に掲載した人気記事の再配信です。(初出:2025年3月12日)※内容は掲載当時のもの
現場で広がる「問い」に対する思考停止
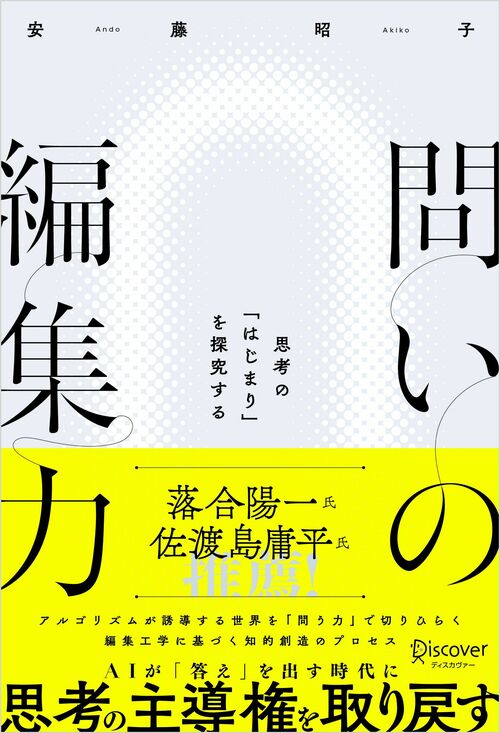 『問いの編集力』(安藤昭子著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『問いの編集力』(安藤昭子著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
「社員に問いを立てるためのスキルをインストールしてほしい」というオファーをいただく機会が増えてきた。
そのきっかけはさまざまだ。社長との対話会でほとんど質問が出なかったことに会社が焦ったということもあったし、新規事業のアイデアを募集してもほとんど提案が集まらなかったということもあった。
あるいは、事業での大きな失敗が直接のきっかけだったこともあった。上司から受けた指示をそのまま実行し、問い直すことをしなかった結果、失敗につながったことに会社が危機意識を高めたのだ。
いずれのきっかけにせよ、トップダウンで与えられた問いを粛々とこなすだけでなく、ボトムアップ的に自ら問いを立てる力を持ってほしいというのは、マネジメントとしては自然な欲求なのだと思う。
しかし、その期待とは裏腹に、現場では問いに対する思考停止状態が広がっている。平たく言えば、「問いを立てるのは無理だ」という思いから抜け切れないのだ。
現場がこう考えてしまう背景にはいくつか理由があるが、代表的なものを2つ挙げよう。

