<「べらぼう」第16話 徹底解説>なぜ平賀源内は、阿片を盛られ、冤罪に遭い、殺されなければならなかったのか<さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)>
──────────────────────────────
Today’s INDEX
0:00〜 0:来週休みです!
1:23〜 1:このためのキャスティング×5
7:49〜 2:障害物を意図的に置くカメラワーク
14:01〜 3:平賀源内は確実に死にました
16:35〜 4:安田顕の源内アプローチ
22:23〜 5:<主題>平賀源内はなぜ殺されたのか
30:00〜 6:史実の平賀源内と本作とのリンク
33:13〜 7:クレジット解説
35:03〜 8:エピローグ
──────────────────────────────
※画像使用について
動画内で使用している画像は基本的にNHKが公式に発信している画像を引用の上で使用しております。著作権者は(C)NHKとなります。
──────────────────────────────
#べらぼう #蔦重栄華乃夢噺 #大河ドラマ
#蔦屋重三郎
#横浜流星 #安田顕 #小芝風花 #宮沢氷魚 #中村隼人 #高梨臨 #井之脇海 #小野花梨 #寺田心 #中村蒼 #正名僕蔵 #伊藤淳史 #山路和弘 #六平直政 #安達祐実 #水野美紀 #飯島直子 #かたせ梨乃 #市原隼人 #橋本淳 #徳井優 #尾美としのり #寛一郎 #西村まさ彦 #風間俊介 #冨永愛 #相島一之 #眞島秀和 #映美くらら #花總まり #生田斗真 #片岡愛之助 #高橋克実 #里見浩太朗 #石坂浩二 #渡辺謙
#平賀源内 #花の井 #田沼意知 #長谷川平蔵宣以 #知保の方 #小田新之助 #うつせみ #田安賢丸 #次郎兵衛 #松葉屋半左衛門 #大文字屋市兵衛 #扇屋宇右衛門 #半次郎 #りつ #いね #ふじ #きく #鳥山検校 #藤八 #北尾重政 #平沢常富 #富本午之助 #西村屋与八 #鶴屋喜右衛門 #高岳 #松平康福 #徳川家治 #大崎 #宝蓮院 #一橋治済 #鱗形屋孫兵衛#駿河屋市右衛門 #須原屋市兵衛 #松平武元 #田沼意次
#綾瀬はるか
#べらぼう解説
#べらぼう第16話解説
#吉原 #浅草 #正法寺 #遊郭

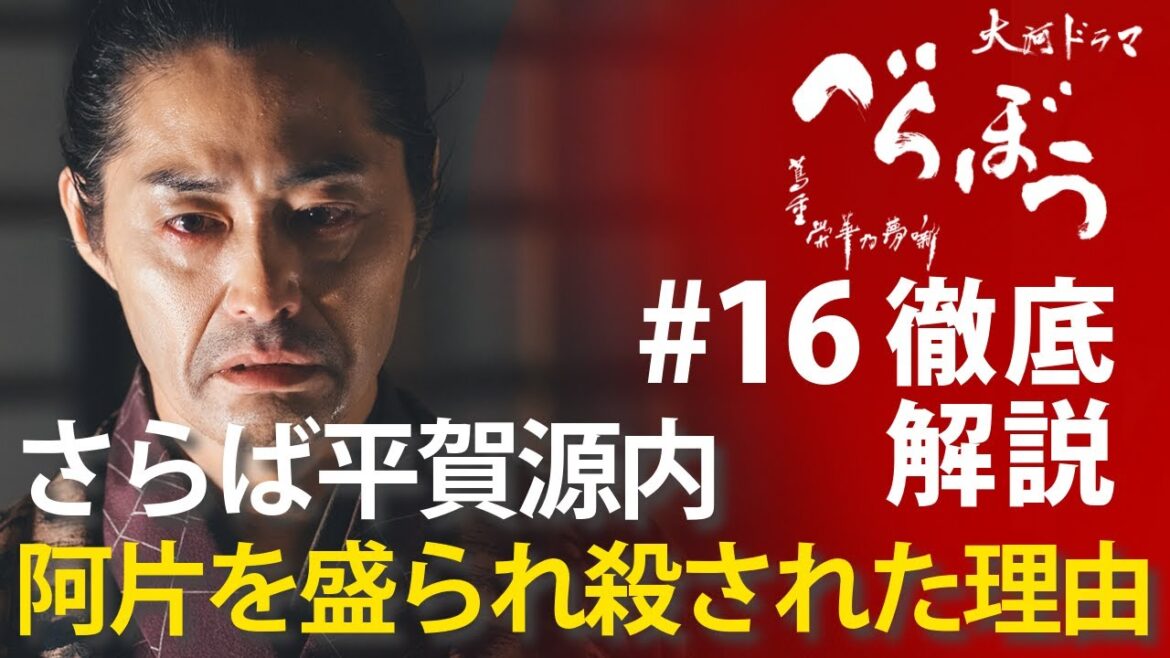
39 Comments
NACSの中でも一番の演技派だと思うのですよ。歳を重ねる度に、ドラマに出る度に、深みを増す俳優だなぁと。
そんなヤスケンさんとの間接的な思い出がありまして、まだ東京進出する前の頃。
アルバイトしていたコンビニにヤスケンさんが来店。後輩が気付き『安田顕さんですよねっ!?』
と、訊ねたらとても恥ずかしそうに支払いを済まし店を後にしました。
ミミガーだけを買ってったようです。
もーこのあたりから好きになりましたよw
突然の獄中死。普通はあの白湯に毒が、と思うはずだが、源内はある程度覚悟してあれを飲んだような気がする
源内さんは死んでしまったんですね💧
それならそれで諦めなければならないのでしょうが、このまま治済が長生きして終るのだとしたならどうにもやりきれません…
治済の悪事を誰が成敗(?)するのか。
本来なら心中で終わるようなオリキャラ新之助(源内が捕まる前に何かを贈っていたなどで)が治済の悪事の証拠でも出し、どうにかなるのか、ならないのか…
しかし、森下さんなら必ず視聴者にカタルシスを味合わせてくれると信じたいです。
治済は焼芋(薩摩芋)を食べていました。
これは治済の協力者に薩摩(島津重豪)がいるのだという明確な暗示であり、私はこの薩摩芋に鳥肌が立ちました…
あれ?録画してたの見直そうかな。調査依頼される前から、誰かに煙管渡されて受取る描写あったような…それがアヘンかどうかは分からないけど、奇行が見られるようになったあたりから何らかの麻薬やってたんじゃないかな?
とりあえず、見直して見よう。
まさに神回でした 凍てつく牢に駆けつけた意次 そして和解 そっと置かれた湯気の立つ白湯であろう茶器に毒など入っていなかったと信じたい
人生上手くいかない事も多かった源内さん 最後に温かい白湯で心解して旅立っていったと思いたい
だったら…生煮えのエビチリにあたった方がまだ良かった…🍤😭💦
ヤギシタさん、もしよろしければ「大人の科学 エレキテル」で検索してみてください。学研「大人の科学vol.22 平賀源内のエレキテル」の案内があるでしょうか。2008年発売のこの商品の購入以来、源内先生をずっと尊敬しています(ホントはもっと前からですが)。そして現在は、精神疾患による障害年金を受給して生活しています。
この度、源内先生の壮絶な明と暗を視聴して、おこがましくも源内先生と私の人生を重ね合わせて見ることができ、幸せを感じています(実際に比べるには雲泥の差がありますけど)。そして、私は源内先生のような天才でもなければ非凡さもないので、一市民として慎ましく生き延びようと思います。でも、自分の半生を肯定してくれるようなドラマと出会え感謝いたします。
第16話の前に、ヤスケンさんが香川県を訪れる平賀源内紀行をみてました。だから余計に切なかったです。
気になるのは、本草学者である源内は煙草のアヘンに気づかないはずはないだろうと思うのです。わかっていて、これぐらいなら大丈夫。自分でコントロールできると考えたか?
心が病んでいたからアヘン?にすがったのか?
ヤギシタ様の素晴らしい解説、考察に感動しました。
この解説、カメラワークとか、影などをもう一度
再放送で見ます^_^。
全て解説通り素晴らしい回でした。一点、本草学者の源内が煙草の煙の匂いに違和感感じなかったのか?という点だけ気になりました。
今回は、スタート以来一番胸が熱くなりました、
意次の立場上泣くに泣けない表情と無念さが絶品でした‼️
なんとか最後に一橋を落としてくれる話を期待しています⁉️
安田さん始め前回のように俳優陣の演技が光る、目が離せない回でした。
源内が退場する回なのに「見立は蓬莱」と不老不死の薬である蓬莱がタイトルに入っているのに違和感を感じていましたが、
源内の本を売り続けることで源内を永遠に生かす、という須原屋の旦那のセリフで本こそが源内を永遠に生かす蓬莱の薬なんだ、と気づき今回のタイトルが腑に落ちました。
「手袋」を使って、家基、武元、源内の死を一人の真犯人の陰謀によるものとしたこと、しかも、それをすべて「意次のせい」だと世間に思わせるように仕向けたこと、これはまさに手練れのプロによる驚愕のテクニックだ。ポイントの第一は、手袋をすぐに始末せず放置し、武元と意次に調べさせたこと。この段階で武元を亡き者にし、手袋を回収してしまえば、武元の死は必ず意次のせいにできる。第二は、偶然ではあるが、源内が手袋捜査に関与したこと。これによって、源内も武元と同様、真実を知ることとなり、最後には命を失うこととなる。直前に意次と口論しているので、世間は源内の死も意次のせいだと思うことになる。意次が作らせた手袋を小道具として、すべてを意次のせいにする、という高度な手法。真犯人にとって邪魔な者はすべて片付け、その一切を最も邪魔な者のせいにするという、非常にわかりやすい展開となっているのには舌を巻く。
なお、最後に治済がサツマイモを食べていた。これは、島津重豪が密貿易の利権を失いたくないため開国派の意次・源内を陥れようとしており源内の死にも関与していたとする説を踏まえて、治済と島津の「連携」をにおわすもの。サツマイモといえば青木昆陽が江戸に広めたものであることを思い起こさせつつ、これまた巧みな演出だった。
月曜日の朝に、昨夜の大河の復習できるの、ほんとうにありがたいです🌸ひとつひとつの場面解説やカメラワークの説明もしていただいて、もう一度見たい気持ちになります🥰
ここまでの源内のイメージから、人を殺して獄中死までどうやってつなげるのかと思っていました。
心神喪失の上に薬と陰謀に巻き込まれて、濡れ衣を着せられて、と持っていくとは!
これまでの源内のイメージを崩さず、史実も曲げず、今回も脚本に唸りました。
ヤギシタさんの服…気持ち喪服ですかね!?
見立ては蓬莱
浦島太郎の物語
繋がる物語
須原屋さんも蔦重も言っていた繋げていく物語
蓬莱でいきつづけるとおもいます
貸家の壁が蓬莱っぽかったですね
田沼のもとに蔦重達が来た時
鷹の声してましたね
(一橋鷹狩を表現!?)
一橋のさつまいも食べてる意味合い
深い
北斗七星のことかな!?
7つのなんとか
………………………………
方八から
八犬伝思いついたのかな!?
ボクは勉強苦手で史実なんてわかりません
中にいたわけでもなく敵でもないので
今回は源内さん!
安田顕さん圧巻の演技でした😭😭
だんだん狂ってしまうところは切なかったです。
蔦重が仮のお墓の前で嗚咽を漏らしながら泣くところがめちゃめちゃ泣けました。思い直して耕書堂を盛り上げていく事が源内に対しての
何よりの供養だと思います。すわらやさん達周りに支えられて
ひと回りもふたまわりも成長していって
欲しいです。
源内と田沼の葛藤が、前回の武元と田沼同様に凄まじく胸に迫った。今までの自分の無念や不運を込めて田沼に食い下がる源内は、あなたはご老中、俺は山師どころかいかさま師と自虐的に語り、与えられた金貨をぶちまけ怨念を込めるように自分の口封じはできないと述べ立ち去った。エレキテル批判に激しく反駁する源内は、強気の言動とは裏腹に、内心では自覚している。だからこそ、エレキテルはいかさまだ、源内は何も成し遂げてはいないという自己否定の声が聞こえてしまう。それらは彼の心が言わせている声であり、明らかに精神的に追い詰められている。精魂傾けてきたものが尽く失敗し、本職の本草学で大成できず落ちぶれてしまった自分への悲壮感に満ちていた。そんな彼にも牢中での田沼の訪問が一抹の慰めとなり、男泣きに泣いた。悲哀続きの彼の最期であったが、心の平安だけは取り戻せたと信じたい。ヤスケンさんの鬼気迫る熱演が、久々に見る役に憑依したかのような迫力で圧巻だった。
そんな源内にあれほど真摯に対した田沼だったが、彼の死後自身の立場や幕府内での今後を見据え豹変し、源内を対外的に見捨てた。忘八と蔦重に毒づかれた後に、源内の遺作の一部を読み涙する。自分(田沼家の家紋は七曜の星紋、幼名は龍助=七ツ星龍)と源内をモデルにした主人公が悪を倒すというストーリーに、さすがの田沼も深く心をかき乱されたのだろう。政治を司る者の建前と本音が描かれ、見ている者にも強くアピールする場面だった。
このためのキャスティング×5という解説には「なるほど」と思いました。里見浩太朗さんが須原屋というポジションでいた意味がこの回のためにあった、と言いたいくらいでした。生田斗真さんは若い頃を見ているので時代劇の悪役をしっかり出来るようになったのが感慨深いですw。安田顕さんの源内は素晴らしかったですね。彼の代表作になるかも。それから解説で「大事なシーンは引きで撮る」と言う言葉を引用されていましたが、ふと山田洋次監督の「幸福の黄色いハンカチ」を思い出しました。主人公(高倉健)が妻と再会するクライマックスシーンも当時「すごい引きだなあ」と思いましたから。
昨日は鬱展開で見終わってから気分がブルーになりました。平賀源内の最後の後味の悪さ、一橋斉済のヤバさ男女逆転大奥を思い出しました
とても良い解説ですね
私の思いを表現してくれました。
今回は 泣かされました
ヤギシタさん 最高です
大好きです❤️😍
今日のヤギシタさんの解説も、神回だと感じました。私なんかは、昨日のような強い回だと、脳幹直撃で思考ストップしてました。
カメラワークなどの工夫や史実とのからみ、筋道整理をしていただいて、ようやくフルコース堪能できたというか。
なんだかすごいものをみた気はしてたのですが、ヤギシタさんのおかげで、やはりそうだったかぁ!と納得です。
ありがとうございました。
今回の話は本当に悲しくて、無念な気持ちになりました…蔦重や須原屋のような人々が源内先生のことを後世まで語り継いで下さったことに感謝です😣
ヤギシタさんが仰る通り、「亡八が!」のカメラワークはすごーくかっこよかったです!私は田沼意次の目線なのかなと思いながら見ていました😮これ以上自分やまわりの人間に危害が及ばぬよう、泣く泣く冷たい態度を取らなければいけない。ゆえに、怒りをぶつけてきたありがた山を直視しきれていない的な…
ヤギシタさんの解説素晴らしいですありがとうございます❤
安田顕さん本当に名演技でした👏解説ふまえて土曜日再放送じっくり観ます😊
大河ドラマはドラマとうたってる以上はドラマであり史実の検証番組ではないですからね。
司馬遼太郎の小説に文句を言うのと同じです。
安田源内主役の独壇場の回でしたね。 演技が凄まじかった。
渡辺意次はどんな演技を残して去って行くのかと思うと、、寂しさと期待で心がワサワサします。
本当に凄まじい回だった😊
蔦重にわざわざあそこで「忘八が」を言わせたのか気になってて。今後行政の失敗や飢饉で民衆から叩かれる(田沼のせいというわけではなく、運が悪かったのもある)ようになってしまう布石かと思いました。今回のことも蔦重には裏事情はわかっていません。だから単に酷いと思ってしまった。裏事情のわからない民衆は都合が悪くなると政治家を叩きますもんね。蔦重にとっても本当は田沼時代の方が良かったのにと後世を知ってる我々は思うけど、当時の民衆はまだ気が付かないですもんね。
田沼「源内は狐憑きで何を言うか分からんというのが俺の見立て 」
須原「俺は源内の書いたものをずっと出し続けるよ。それこそ俺が死んでも、だよ。それこそがあいつを永遠に生かし続ける事になるんだよ」
蔦重「源内さんに頂いた耕書堂という名に恥じぬ様本を出し続けまさぁ」
三者の見立てに考えさせられたし、人の思い考えを伝え続けるものが紙でできた本である事に感動。
前作「光る君へ」での源氏物語や枕草子などにも見られる、千年続く「紙に文字を綴る」文化の尊さを感じました。
安田 顕は何を演じても「庵野秀明」に見えてしまう。
田沼意次と平賀源内の牢屋でのシーンは、現実にはありえないと思いながらも、二人の名優の魂の演技に圧倒されました😢
今回は鎌倉殿の「足固めの儀式」のような納得いかない回でした。理不尽に処刑された上総介殿と源内が重なりました。
ただ救いがあったのは田沼意次の源内への気持ち。頭が良くて他の者が思いつかないようなアイデアで自分の役に立ってくれる便利な奴、ではなくてなんか友情のようなものを持っていた気がします。だからわざわざ牢屋まで会いに行ったんだなと。
蔦重から「死んで欲しかったのか?」と聞かれて「察しがいいな」と答えたのは自分が黒幕だと思わせてこれ以上蔦重が詮索するのをやめさせるつもりだったと思います。蔦重や須原屋、杉田玄白らを巻き込まないために。彼らが立ち去ったあとに涙ぐんで「だから忘れろと言ったのに」と源内の死を悲しんでいましたね。渡辺謙さん、さすがの名演技でした。
一年を通してドラマを観るのが長丁場だなぁ、と大河を観なくて何十年ぶりに観たのが、べらぼう。第一回冒頭の大火のシーンをたまたま観たことでグングンのめり込んでしまいました。
で、今回…今まで瀬川ロス、でも蔦重頑張って🥲って思えて観ていましたが、いやぁ今回は心をエグられました。
もう釘付けで涙を流すことすら忘れて食い入るようにドラマを観るのは何年ぶりかしら、てくらいです。
解説を拝見した上で再度観たら、より感情移入して、今度は泣いてしまうかもしれません。
ひとつ、疑問なのですが…
源内先生は、あの幻覚の時に侍に斬られてはいないのですか?
私は斬られたか、何かで突かれたように倒れ込んだので、そこで命を落としたっばかり思っていました。
そしたら、起き上がって来られたので、そこで「⁇」となり、ちょっとついていけなかったりもしました💦
久五郎とあの侍(名前忘れました💦)がいきなり登場したのも、誰?てなったり😖
そこのところを教えていただけるとありがた山の寒がらすです🙏
いつも動画を欠かさず拝聴しておりますが、久しぶりにコメントします。
安田顕さんの平賀源内、誰の目にも奇妙奇天烈な最期に見えたことでしょう。おかしくなっていく様が滑稽で絶妙でそこがなんとなく気持ち悪い感じを出していて、最高でした。
さすが実力派俳優安田さん、素晴らしい演技でした。そして平賀源内と獄中で手を握っていた田沼意次。主従の関係だとしても、一緒に日の本の未来を語った友のような存在だったのではと思います。
これから本当に1人になってしまった田沼意次の未来を知っているからこそ胸が痛い回でした。
源内の狂った演技、安田顕という役者の底力を目の当たりにしました。意次との友情の場面にも引き込まれました。源内の訃報を聞き俯く意次が決意を固めて表情を作る場面も、切なかったです。。。蔦重に「忘八」と突きつけられたとき、犠牲を広げないためとはいえ友を救わない決断をした自意次自身が一番そう感じたのかもしれません。
一橋治済が芋をおいしそうに食べるだけなのに恐ろしいと感じてしまう生田さんの演技、今回も流石でした。黒幕確定でしたね。
ここでまた蔦重の心を支える朝顔姐さんの教えに私も救われました。。(宝塚時代から愛希さんファンなので、主人公の想像だけでも登場すると嬉しくなります)
今回も解説ありがとうございます^_^
自分も源内ロスの一人です。最後の牢で出されたのは熱燗ではないでしょうか?その前にじょうのすけが源内に酒は飲めるのかと聞いていた場面があり、可能性があるかなと思いました。牢ではとても寒そうにしていたので一気に飲んでしまったのかも。亡くなった瞬間を描かず、視聴者の想像力を掻き立てる演出でしたね。
神回でしたね。安田顕さん、素晴らしかった。
そして史実の部分は曲げずにドラマを創り込む森本脚本お見事です👏👏👏。
生田斗真君の治済、仲間由紀恵治済とはまた違った意味で怖いですね😰
今回、「W“けん”さん」の熱演が凄かったですね。
ベテランの役者さんたちの凄みを感じました。
今回、陰と陽の“一石二鳥”が描かれていたと感じました。
陽の一石二鳥は蔦重。
一時流行した「続きはwebで」というCMや、『STAR WARS』などの単発だけど連作の映画のように、「この本だけ、あるいは浄瑠璃の舞台だけでも面白いけど、本を読み、舞台を見たらより楽しいよ」と持ちかけたコラボは、蔦重も馬面太夫も利が得られる一石二鳥。
昭和の頃の角川映画の「観てから読むか、読んでから観るか」を連想しました。
一方、陰の一石二鳥は治済。
自身の陰謀を暴きかねない武元や源内を消すことは、己の身の危険を潰すと同時に、ひとびとの田沼への疑惑を高め、知恵袋(源内)ももぎ取る、一石二鳥だったと思います。
その治済は、ご三卿。
御三家と違い、領地も信頼おける譜代の家臣も持っていない。
そこで、大名と結んだのでしょうね。
将軍家の正室・御台所は、宮家や五摂家から迎えることが三代家光からの伝統。
だけど治済の息子家斉は、将軍候補になる前に縁談がまとまっていたことで、例外的に外様大名の娘と婚姻後がまとまった。
家斉を将軍に就けたい田沼、力をつけたい薩摩。
利害が一致したことで、協力体制も強固なものになった。
そういうことのように思います。
ところで源内が吸っていたのはアヘンか、大麻など他の薬物か。
イギリスの東インド会社がアヘンの専売権を得たのが1773年、製造権を得たのは1797年。
平賀源内の没年は1780年。
オランダや朝鮮としか交易のない日本で入手できたかどうか、微妙なところなので、そこは視聴者におまかせなのでしょうね。
その源内は…残念だけど、獄○したと思います。
抜け出して生存しているとしたら、あの才気煥発な源内のこと、密かに静かに暮らすことはできなくて、あの鬼才ぶりを表に出してしまったはず、そう思います。
もしかしたら、謎の絵師、写楽になっていたという設定ならあり得るかも。
1年経たずに消えたことは目立ってしまったから姿を隠したとも取れますから。
今回は安田顕さんの鬼気迫る熱演で平賀源内の退場を印象づける正しく神回だったと思います。私個人としては新撰組!!の山南敬助(演:堺雅人)の自害の回をも超える秀逸な回だったと思います。皆さんとそれぞれのシーンについて語りたいことが満載です。その中からいくつか。
現愛を死に追いやったもの
人は余裕があれば相手を思いやったり,意見の相違があってもそのフォローのために直接会ったり言葉を交わすなど手間をかけることができます。しかし,余裕がなくなると,思いもよらないキツい言葉が口から飛び出したり,相手を思いやる一言が出なかったりするものです。意次は家基の死の真相に近づくすべを失い,自分の身も危ぶまれる危機に陥り,源内はエレキテルの件で世間からの猛バッシングを受け,焦燥の中にいました。両者がともに余裕のない最悪のタイミングがすれ違いを生み,互いを思いながらも大切なことを伝えられませんでした。意次は家基暗殺の件から手を引くことをもっと丁寧に伝えることできたはずだし,源内の異常な感情の起伏(アヘン中毒の初期症状)にも気づけたかもしれません。また,源内も普請の件のお礼を直接意次に言上に行っていれば罠に気づけたかもしれません。(しかしこちらはアヘンの影響で難しかったかもしれません)
そう考えると唯一のチャンスは源内邸の異臭に気付き,源内の行動のおかしさに違和感を感じていた蔦重だけだったかもしれません。
松平武元の遺言とも言える金言の伏線回収
前回,武元は意次に「いざという時に米のように食えもせねば、刀のように身を守ってもくれぬ。人のように手を差し伸べてもくれぬ。左様に頼りなき物であるにもかかわらず、そなたも世の者も、金の力を信じすぎておるようにわしには思える」と忠告していました。源内との決別のシーンで金を渡したことが二人の袂を分かったことからも見事な伏線回収であったと思いました。
獄中の源内に差し出されて白湯
源内に差し出された白湯について,私は意次が与えた毒だったのではと考えました。牢獄での面会から,源内がアヘンに犯され,重篤な状況であることを察したのではないかと思います。また,アヘンは古来より自白剤としても使用されており江戸時代にも使用されていたとされています。窮地に追い込まれている意次は意知からの助言で源内の救援を諦めただけでなく,これ以上源内の名誉を傷つけず,自分へ害が及ぶことを避けるために毒を与えたのではないかと想像しました。蔦重たちの訴えで自分の行動の過ちに気付いたからこその意次の罪悪感を背負った演技脱兎のではないかと思いました。本編では描かれていませんが,白湯をあおる源内の姿はソクラテスが獄中で毒酒をあおって自害した姿と私の中では重なりました。
蔦重が受け継いだもの
ラストのシーンで,源内の死を受け入れられなかった蔦重は源内が逃げたことにする。と話していました。これは源内の死を拒むために,「自分の中」で源内を生き延びさせようと考えたものでした。
一方,人の死は二度訪れるといいます。一度目は肉体が滅びること,もう一度はその人の存在を覚えている人が誰もいなくなることです。須原屋はこの二度目の死を絶対に迎えさせないためにも本を出し続ける決意を語りました。
その言葉で蔦重は,源内の精神,志を受け継いで,本を通して民衆の心を耕す耕書堂の精神を世に広めることこそが源内の二度目の死を永遠に遠ざける方法であると悟ったのだと思いました。この決意がべらぼう第2幕の幕開けになると高らかに宣言して,源内の死に大きな意味を持たせたのだと思いました。
長々と書き綴り大変失礼しました。読んでいただいた方,誠にありがとうございました。