▶︎完全版は「ゆにわ塾」から!→https://online.uniwa-juku.com/content/128000
「むすび大学」は日本人が今こそ学ぶべき
真の教養を身につけるための教育系チャンネルです。
歴史、哲学、宗教、文学、政治、ビジネスからテクノロジーまで
ジャンルは問わず、日本が誇る“結び”の精神によって
古今東西の学問を和合させて、新しい文化の創造を目指します。
超一流の教養人から、あらゆる学問のつながりを学ぶ
知的ハイ!な体験を、あなたに。
興味のあるテーマから、ぜひご視聴してください!
【公式HP】http://musubi-ac.com/blog/
【問い合わせ】こちらまでお願いします info@musubi-ac.com ※@を半角に
【講義リクエスト】は任意の動画のコメント欄にて!
オンライン教材「ゆにわのいろは」 開運するためのグランドセオリーを、ぎゅっと凝縮したオンライン教材です。要点がしっかりまとまっていて、体系化されているので、羽賀ヒカルが伝えている開運の秘訣の基礎を一気に学びたい方にオススメです。 https://zinja-omairi.com/g/iroha

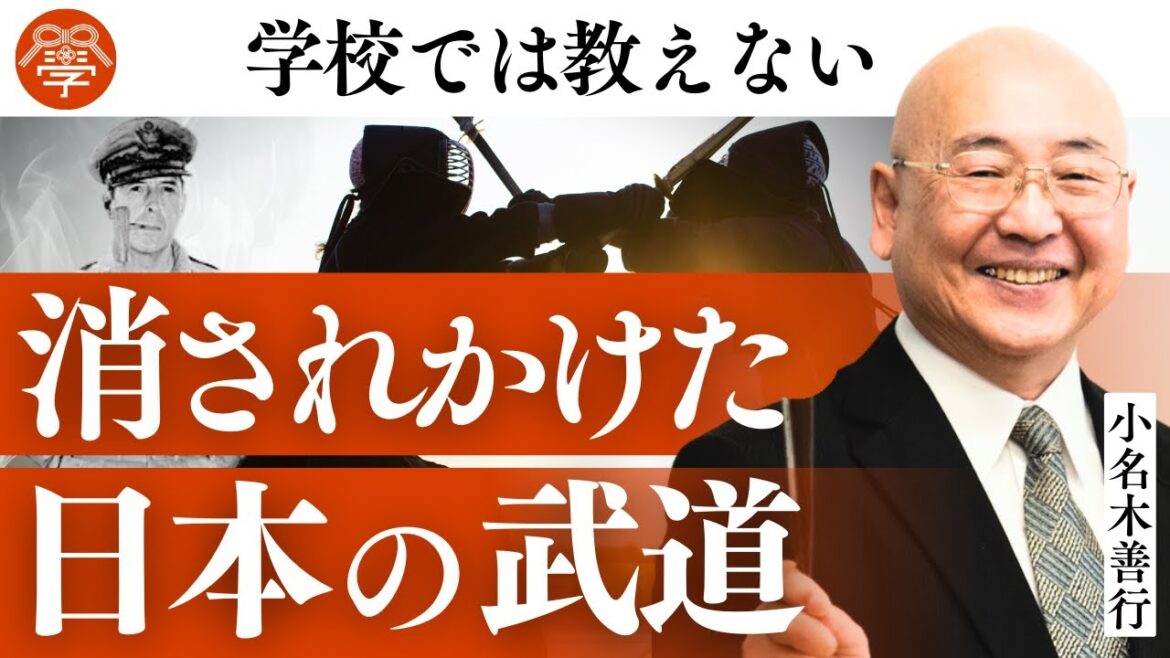
8 Comments
香取神道流は500年ぐらい 流祖は飯篠長威斎家直
結美大学でSMに言及されるとは思いませんでした👍
鹿島神流
(かしましんりゅう)とは、日本の古流武術の流派。鹿島古流、鹿島中古流とも、剣術と柔術を中心に、抜刀術、薙刀術、懐剣術、杖術、槍術、棒術なども行う総合武術である[1]。鹿島神流(鹿島古流、鹿島中古流)の遣い手には、塚原卜伝の父祖伝来をはじめ、昭和時代に「今武蔵」(昭和の宮本武蔵という意味)という異名で称された國井善弥[2]や、筑波大学名誉教授の關文威[3]などがいる。
概要
鹿島神宮に古くから伝わったとされる「鹿島の太刀」を元としている[4]。これは鹿島神宮祭神の武甕槌大神が悪神を鎮める際に使用した技がその始まりであるとして、抜刀術の「祓太刀」がその名残だという[4]。また、建御名方神との力くらべの際に武甕槌大神が使った技が柔術の「霊気之法」の始まりとしている[1]。流祖は松本備前守紀政元[4]。戦国時代、松本備前守紀政元は鹿島大神に祈願すると剣術の極意を記した「天狗書」を賜った[4]。鹿島神流師範家に代々伝わる「天狗書」は松本備前守紀政元の直筆であるとし、師範家の証と位置づけている[4]。松本備前守紀政元はまた、「一ノ太刀(いちのたち)」の発案者であるとされている[3]。上記の祈願の際には國井源八郎と交流の結果國井を後見人として流派を開き、以降國井家が宗家を、上泉伊勢守を始めとする松本備前守の弟子たちが代々師範家を受け継いだ[4]。師範家は幕府からの弾圧を避けるため流派名を変え神影流などと名乗ったという[2]。第十二代宗家國井大善が直心影流の小野清右衛門より免状をもらった時点で宗家と師範家とが統合しこれは第十八代國井善弥まで続いた[4]。2018年3月9日現在、宗家は第十九代國井正勝、師範家は第十九代關文威となっている[1]。
鹿島神流の武術は、哲学的基本原理「五ヶ之法定」と物理的基本原理「方円曲直鋭」とからすべてが構成されている[4]。さらに「表裏一体」の観点から、柔術を始め他のあらゆる武具を用いた術も剣術とほぼ同じように行うことが出来るとされている[4]。
第十九代師範家關文威によって「鹿島神流」流派名は、商標として登録されている[1]。
鹿島神流の武術
鹿島神流の武術は次のようなものとなっている[1][4]。
剣術
基本太刀
裏太刀
相心組太刀
実戦太刀組
合戦太刀
鍔競・倒打
抜刀術
薙刀太刀合
槍術立合
鎖鎌立合
杖術
杖立合
懐剣術
薙刀術
槍術
柔術
霊気投
居捕
立業
投業
組業具足捕
捕手返
後業
国井 善弥
(國井 善彌、くにい ぜんや、1894年1月20日 – 1966年8月17日)は、昭和の日本の武術家。鹿島神流第十八代宗家。福島県いわき市常磐関船町宿内出身。本名は道之。昭和の今武蔵と呼ばれた。
人物
祖父の16代国井新作、父の17代国井英三により、幼少期から家伝の鹿島神流(鹿島神伝直心影流)を教わる。父の命で19歳で外に出て佐々木正之進から新陰流剣術、栖原邦泰から馬庭念流剣術、妙道流柔術を師事。鹿島神流を大成させる。
その後、第1次世界大戦に徴兵され、卓越した武術が軍内で評判となり、陸軍戸山学校の教官に任じられる。中山博道らと共に古流武術を組み直し、戸山流片手軍刀術を開発。成果を上げたことにより校庭に本人の銅像が建立された[1]。
退役後、東京都北区滝野川に道場を開き、「道場破り歓迎」の看板を掲げ「他流試合勝手たるべきこと」とし、幾多の他流試合を相手の望む通りの条件で受けながらも勝ち続け、生涯不敗であったという[2]。剣や棒など武器を取らせても、武器を持たない柔道家や空手家から挑戦を受けても、國井は戦う前から勝負が決しているかのごとく一本を取るのが常であった。武道界からは異端視されたが、日本古武道の強さを体現した武人だった。
墓所はいわき市常磐関船町にある勝蔵院。葬儀は神葬祭で行われた。
弟子
関文威(鹿島神流第十九代師範家、筑波大学名誉教授)、田中茂穂 (武道家)、稲葉稔 (武道家)、野口弘行、平澤誠太郎ほか。
エピソード
『大菩薩峠』机竜之助のモデル
中里介山は、「音無しの構え」を得意とする、国井に出会ったことで『大菩薩峠』の主人公、机竜之助を書いたという説がある[3]。
GHQ教官との試合
太平洋戦争(大東亜戦争)終戦後、GHQから米海兵隊の銃剣術の教官と日本の武道家との試合の申し出があった。日本武道の誇りと名誉がかかった一戦であり、おいそれと負けるわけにはいかない。このため対戦する武道家は実戦名人であることが求められた。また、米海兵隊の銃剣術教官は徒手での格闘術も訓練されているため、剣術のみではなく武器を持たない場合でも強いことが求められた。この条件に、政治家(国務大臣)であり武道家(弘前藩伝の小野派一刀流剣術・神夢想林崎流居合・直元流大長刀術の宗家)でもあった笹森順造は、武道家の間では異端とされていた國井善弥に白羽の矢を立てた。國井は木刀を持って銃剣を持った米海兵隊教官との立会いに臨む。試合が開始されるやいなや國井は相手の攻撃を見切って木刀で制し身動きの取れない状態へと持ち込む。これは圧倒的な実力差であり、米海兵隊教官に負けを認めさせるに十分であった。この試合が実施された当時、GHQは武道が軍国主義の発達に関連したと考え、武道教育禁止の措置を取っていたため、後年、この試合が武道教育禁止の措置の解除のきっかけとなったという話が広まったが、この試合の結果と武道教育禁止の措置の解除に関係があるかどうかは定かでない。ただし、日本武道の名誉をかけた一戦に実戦名人として國井善弥が選ばれたことは特筆すべき点である[4]。
佐々木正之進の内弟子として
修行時代、新陰流免許皆伝の佐々木正之進という武術家の内弟子になった。内弟子になった次の日から、佐々木は國井に「何を持って来い、何もついでに」という指示を出す。「何」と言われてもまったく見当が付かないが、これは相手の思っているところを察知する心眼獲得のための修行だったのだという。師の命令は次第に「何を何して、何は何々」と曖昧さを増すようになったが、國井はかなりの確率で師の意思を掴むことができるようになった。この修行が立会いにおいて、相手の動きを事前に読みきる能力に活かされたという。
奉納演武出入り禁止
明治神宮での奉納演武の際、他流派に立会いを求めたため、その後数年奉納演武に出入り禁止になった。
その他
鹿島神流十八代宗家を名乗るも、過去の古文書がすべて失伝しており、国井が学んだ新陰流などを元に新しく作られた流派ではないかとする説もある(詳細は鹿島神流を参照)。
建御雷神
(たけみかづち、タケミカヅチノオ)は、日本神話に登場する神。
概要
「地震のおかげで普請が増え、大工が儲けて大喜びしている」という、地震よけの歌にかこつけた風刺画(安政2年10月の瓦版)。ナマズを抑えるのは鹿島神ことタケミカヅチ[1]
『古事記』では建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)、建御雷神(たけみかづちのかみ)、別名に建布都神(たけふつのかみ)、豊布都神(とよふつのかみ)と記され、『日本書紀』では武甕槌神、武甕雷神と表記される。『先代旧事本紀』では建甕槌之男神、武甕雷男神、建雷命などとも表記される。
また、鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)の主神として祀られていることから鹿島神(かしまのかみ)とも呼ばれる[2]。
雷神、かつ剣の神とされる[3]。後述するように建御名方神と並んで相撲の元祖ともされる神である。また鯰絵では、要石に住まう日本に地震を引き起こす大鯰を御するはずの存在として多くの例で描かれている。
古事記・日本書紀における記述
神産み
神産みにおいて伊邪那岐命(伊弉諾尊・いざなぎ)が火神火之夜芸速男神(カグツチ)の首を切り落とした際、十束剣「天之尾羽張」(アメノオハバリ)の根元についた血が岩に飛び散って生まれた三神の一柱である[4]。剣のまたの名は伊都尾羽張(イツノオハバリ)という[5]。『日本書紀』では、このとき甕速日神(ミカハヤヒノカミ)という建御雷の租が生まれたという伝承と、建御雷も生まれたという伝承を併記している[6]。
・経津主神
(ふつぬしのかみ、旧字体:經津主󠄁神󠄀)は日本神話に登場する神である。『日本書紀』のみに登場し、『古事記』には登場しない。別名はイワイヌシ(イハヒヌシ)で、斎主神または伊波比主神と表記される。『出雲国風土記』や『出雲国造神賀詞』では布都怒志命(ふつぬしのみこと、布都努志命とも)、『肥前国風土記』では物部経津主之神(もののべのふつぬしのかみ)として登場する。『常陸国風土記』に出てくる普都大神(ふつのおおかみ)とも同視される。
香取神宮(千葉県香取市)の祭神であることから、香取神、香取大明神、香取さま等とも呼ばれる。経津主神は、香取神宮を総本社とする日本各地の香取神社で祀られている。
『釈日本紀』などに引用されている『天書』逸文では、経津主神は鎮星(土星)の精とされる[1]。経津主神は平柳星宮神社など、栃木県に160社以上ある星宮神社の一部で祀られている。
・鹿島神宮
(かしまじんぐう、鹿嶋神宮)は、茨城県鹿嶋市宮中にある神社。式内社(名神大社)、常陸国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。
全国にある鹿島神社の総本社。千葉県香取市の香取神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社[1]。また、宮中の四方拝で遥拝される一社である。
概要
茨城県南東部、北浦と鹿島灘に挟まれた鹿島台地上に鎮座する。古くは『常陸国風土記』に鎮座が確認される東国随一の古社であり、日本神話で大国主の国譲りの際に活躍する武甕槌神(建御雷神、タケミカヅチ)を祭神とすることで知られる。古代には朝廷から蝦夷の平定神として、また藤原氏から氏神として崇敬された。その神威は中世に武家の世に移って以後も続き、歴代の武家政権からは武神として崇敬された。現在も武道では篤く信仰される神社である。
・香取神宮
(かとりじんぐう)は、千葉県香取市香取にある神社。式内社(名神大社)、下総国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。
関東地方を中心として全国にある香取神社の総本社。茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社[1]。また、宮中の四方拝で遥拝される一社である。
弓前文書 神文(現代語訳)
2023-07-13 14:05:27 | 弓前文書(神文)
弓前文書(ゆまもんじょ)とは、「神文」と「委細心得」という二つの文書をさす。
「神文(かみふみ)」とは、文字の無い倭人が弥生時代から口伝で伝えてきたものを、七世紀初頭に香取神宮の神官であった弓前値成(ゆまあてな)が、万葉仮名を参考に漢字を利用し文字化した。その特徴は、倭人語の一音の意味に近い文字を選びだし、その発音は倭人の発音とした。発音を借りた万葉仮名とは大きく異なる。万葉仮名は音読み、に対して、いわゆる、訓読みと考えれば良いだろう。また、漢字に無い特殊文字も創作して使用している。
「委細心得(いさいこころえ)」は、「神文」の取り扱いや、経緯が漢文で書枯れている。
弓前文書原文の神文は、縦四十五センチ×横十八センチ×厚さ三ミリ~五ミリの木板七枚に、それぞれ一行十字、上下二段十四行にわたって、隙間なく書き込まれた漢字(変体形を含む)九八〇字である。
代々の神官が受け継ぐ秘文とされ、第67代弓前和(ゆまに)の池田秀穂により、解読、公開された。
池田秀穂は次のように述べている。
私はいま、まず神文を公開し、さらに「ユマニは他言すべからず」の秘聞まで公開してしまった。ユマニの守るべき掟はすべて破ってしまった。当然神罰あるだろう。わが家滅ぶべし。(中略)すべて覚悟の上。「弥生の言葉と思想が伝承された家」(朝日カルチャーセンター)
それから(作り始めてから)丸五年、平成五年末、上下二巻五百頁の大冊、『弥生の言葉と思想が伝承された家』五百部が完成した。有名神社、大学、親戚、友人、縁故は勿論のこと、朝日カルチャーセンターに五十部委託し、出入りの学者に頒布していただくようお願いする等、様々に伝手を求めて頒布していただいたのであった。こうして置けば何れの日か、種から芽が出ることだろう。「日本曙史話」(沖積舎)
池田秀穂は、覚悟をもって弓前文書を世に出し、そして研究されることを望んでいる。
神文(現代語訳文)
(第1章)
大宇は意図す、大自然変化の流れ。行く道筋、始まりの秩序立て。
大宇は意図す、原点の真相は、事態の自在無限なる疎密運動にある。
大宇の秩序立ては、事態が驚きの無限力塊の姿となったことである。
(第1節)
大自然、始まりの芽生え。
物質を造るという驚きの意志が生まれた。
力は発動した。物質を造るという驚きの意志のそれだ。
出現莫大なる増殖、爆発的に数多火の玉の素粒となった。
宇宙の心、溢れ出た力は奇しき大本となって、大震動を起こし、秩序立てられて行く。
宇宙の秩序立ては、纏まろうとする力が働いて行く。
宇宙の秩序立ては、数多流れ出す自由力の永久不変の形成にあった。
宇宙の姿は、不思議な数多纏まりの力が働き合っている。
宇宙の姿は、さまざまな星で満たされている。
(第2節)
恵みの太陽が、輝き出した。
宇宙形成のなか、ガスが纏まり行く。
宇宙における、形造られ行く力体となった。
宇宙の流れ、秩序立ての大きな垣根が造られる。
宇宙における、核を取り巻く数多の力が覆う集積体となった。
宇宙の流れ、圧縮され混沌状態になる。
宇宙における、灼熱の基が造られた。
宇宙の流れ、灼熱は輝きの放射となった。
宇宙における、輝く存在となった。
(第3節)
大いなる秩序の集積が形成され出した。
大いなる垣根が保たれた。
燃える灼熱体で満たされてゆく。
吸いこまれる数多灼熱の塊。
浮きあがる様々な灼熱の塊。
どんどん変化して行く岩盤。
乱雑に重なり合う岩盤。
入や(いや)盛り上がり寄せ集まつた所。
浮き上がったものですっかり満たした所。
(第4節)
いわゆる生命現象を持ったものが出現、蔓延しだした。
自然力結実の世代。
自然カの結実は小さな現象として芽生えた。
自然意志増殖の生態。
自然意志によって動く単体が出現した。
遺伝、種子増殖の世代。
自己意志による統一活動体が出現した。
親接(雌雄)増殖の生態。
生命有限の個別現象が出現した。
「弓前文書(ゆまもんじょ)」
弓前文書(ゆまもんじょ)とは、七世紀の初め香取神宮の神主であった弓前値名(ゆまあてな)が先祖が受けた天児屋根(あめのこやね)からの神文(かみふみ)という驚くべき天からの口伝えを漢字にして文字化したしたものです。
古事記の主な神々を始め、祓い言葉、日本数詞一二三、十種祓詞の、なんと原語がおさめられております。
まさに国宝とでも言うべき神社神道と主要日本語の起源がズラズラと出てきます。
このホームページは、神文とこれを後世に伝承した弓前一族の手になる日本の古代史、「委細心得」を公開するものです。
併せて、同じ天児屋根からの深遠な成功哲学であるもう一つの伝言を考えます。
今申し上げたことを解明した「古事記と祓い言葉の謎を解くー伊勢・鹿島・香取・春日の起源――」(萩原継男著)というタイトルの私の本が叢文社(そうぶんしゃ)という出版社から2016年3月8日出版とようやく決まりました。
・古事記の元本ー弓前文書(ゆまもんじょ)と神文(かみふみ)ってどんな古文書?
2019/3/30 2019/5/31 未分類
目次
神文は紀元前300年頃の天児屋根からの驚きの伝言
稗田阿礼(ひえだのあれ)の正体
弓前値名(ゆまあてな)によって弓前文書は口伝えから文字化された
神文は紀元前300年頃の天児屋根からの驚きの伝言
「神文(かみふみ)」は、大体七世紀の初めの頃、弓前値名(ゆまあてな)という香取神宮の神職によって文字化された古文書です。
当時は、鹿島神宮には中津(なかつ)という神職が、香取には弓前(ゆま)という神職がいたのですが、彼らの共通の先祖アメノコヤネという神から託宣された神文という神言葉で書かれた文書を大切に守り伝えていました。
中津や弓前という姓は彼らが中臣の姓を与えられる以前の姓です。
以上のことは、神文の解説文とでも言うべき主に弓前値名が書いた「委細心得(いさいこころえ)」に記されています。
約二千三百年前頃に、アメノコヤネから受けた神言葉を口伝えの口承で弓前値名(ゆまあてな)の時代の七世紀の初頭まで受け継いできたのですが、当時の日本語の文字化の成立という時を得てその値名が文字化したのです。
この神文の大きな価値は、八世紀に成立する古事記や日本書紀という古典の原書だというところにあります。
ことに古事記の冒頭に出てくる天之御中主神からイザナキ・イザナミの神までの十七柱の神々や、天照大御神や大国主神の元の名であるオオヒルメムチやオオナムチという言葉は、実はこの神文の中にあります。
だからこそ、神社神道は、基本的には「中臣神道」だと言われるのです。
つまり、現在の神社神道の、少なくともその核となる部分は、中臣氏の祖、中津、弓前という後に鹿島香取の神職になる一族が伝えた口伝に基づいているからです。
「大祓(おおはらえことば)詞」を別名「中臣(なかとみ)の祓(はらえ)」などというのもそういう経緯から来ているのです。
しかしそういう事情を知らないので、中臣氏の専横によってそんな名前が付けられていると思われているようです。
稗田阿礼(ひえだのあれ)の正体
私は、古事記の語り部といわれる稗田阿礼(ひえだのあれ)といわれる正体は、実際には、この弓前値名と記紀編纂の当時、これらに大きく関わったといわれる藤原不比等であったと思っています。
このことについてここで詳しく論ずることは差し控えますが、不比等も値名も、いずれも鹿島・香取の中津・弓前の出身の後裔です。
言伝えによりますっと、「神文」は、約七世紀の初頭の頃、弓前値名(ゆまあてな)という香取神宮の神職によって文字化された古文書です。
その時文字化されたということは、それまでは口伝えで伝わっていたということになります。
これを口承(こうしょう)といいます。
約二千三百年前ごろにアメノコヤネから受けた神言葉を、口伝えで弓前値名の時代の七世紀の初頭まで受け継いできたわけです。
ちょうどそのころの渡来人による日本語の文字化の成立という好機を得て、香取の値名(あてな)という人物が文字化したわけです。
確かマッカーサーに陳情しに行ったのは尾形郷一と言う人物だったと思います。