
東京都議会議員選挙の投開票が6月22日に、参議院議員選挙が7月におこなわれます。
多数の候補者の中から、投票する人をどのように選べばいいのか。候補者の情報がインターネット、SNSで得やすくなった一方、真偽不明の情報にさらされるリスクも高まっています。
候補者の情報を探す際の注意点やポイントを、首都圏ネットワークのリポーター犬、しゅと犬くんと探りました。
「首都圏情報ネタドリ!」配信は6/20午後7:57まで↓

都議選の候補者一覧や各党の公約など最新情報はこちら↓↓

SNS選挙の裏側
2024年11月に行われた兵庫県知事選挙の出口調査で、投票で最も参考にしたものを聞いたところ、テレビや新聞は24パーセント。それに対し、SNSや動画サイトは30パーセントと最も多くなっていました。
SNSで選挙活動は大きく変化しています。

都内で開かれた、選挙候補者向けのSNS対策セミナーでは、都議選の候補者に加え、現職の市議会議員など30人が参加していました。

SNSセミナーを主催した イチニ 高畑卓社長

高畑卓社長
昨年(2024年)は選挙と政治が特にSNSにおいて盛り上がったのがひとつ特徴。多くの方がネットで情報を得て投票先を決めています。

しゅと犬くん
選挙でSNSは、そんなに大事なの?

SNSで何も発信しない人は、存在しないに等しくなってしまいます。例えば10人が立候補し、5人はSNSをやっています。残りの5人に触れる機会をどうやって作るんですか、という話だと思うんですよ。

有権者にメリットはあるの?

SNSや動画のコンテンツが広がったことによって、入口が増えたと思います。街頭演説を聞きに行く、選挙事務所に行くというのはなかなか難しいですよね。それがもうちょっとライトに楽しめる形で入ってくるというのは、すごくメリットがあります。
SNS時代になり、選挙の戦略も大きく変わってきています。

選挙プランナー 松田馨さん
選挙ではこれまで、地元の支援組織の広がりを示す「地盤」、知名度を表す「看板」、資金力である「鞄」の3つのバンが重要とされてきました。
これに加え、ネット地盤が注目を集めていると、選挙プランナーの松田馨さんは語ります。

選挙プランナー 松田馨さん
「何度も何度も駅に立ち続けていくことで、少しずつ知名度を上げていくことは、候補者の皆さんはやっていますよね。SNSの発信も実はそれと非常に近いところがあります。
もし、しゅと犬くんが立候補するなら、SNSというすごく利用者の多い駅があってそこにしゅと犬くんがちゃんと立つようにする。毎日毎日、発信していく。自分のファンにしていく。そういうネット地盤のつくり方というのが、今、非常に有効だと言われています」
これまでのチラシやポスターよりも、SNSでの情報発信を重視する候補者も少なくないといいます。

松田さん
「ビラやポスターは、公職選挙法の厳しい規定があって、量やサイズの制限が細かく決まっています。でも、ネットは自由に発信ができます。そのため、ネットで動画をしっかり発信をする、SNSでテキスト・写真の発信をするというところに力を入れる候補者が多くなっています。それを見て、最終的に有権者も投票先を決めていく、という形に大きく変化してきたんだと思います」
さらに、選挙の資金集めにもSNSの影響が。ネット献金の利用も、非常に広がっているということです。
政治家個人への寄付は選挙運動に関するものに限って、有権者一人につき、年間150万円まで行うことができます。
SNSで知名度を高めることで、全国から資金を集めようという動きもあるといいます。

松田さん
「ある知事選挙ですと、1億円以上をネット献金で集めて、それをまた数千万円ネット広告に使う候補者もいらっしゃいましたし、集めたお金をネットの広告に使ったり、SNSの発信に使ったりということで、これまでの地上戦、空中戦ではない、ネット戦でお金も集めて更に広告も使うというような、ネット上で完結する流れに大きく変わってきていると思います」
収益目当てで動画を配信する人も…
SNSには気をつけたいポイントもあります。それが「知らない間に、偏った情報に囲まれるリスク」です。
都内で暮らす大学生は、最近、スマホによく流れてくる、選挙関連の動画があるといいます。
大学生
「切り抜きで短い動画がパンパン出てくるのがすごく多いです。減税したらこうなる、それで日本がよりよくなっていくという、短くまとめてある動画を見てしまいがちです」
街頭演説や国会の一部を切り取って編集した切り抜き動画。無許可の場合は著作権法違反ですが、規制は追いついていません。

どのような目的で投稿されているのでしょうか。
2024年秋から、政治系の切り抜き動画の投稿を始めたという男性は、政治や国会について視聴者のニーズに合わせた投稿を目指しているといいます。

切り抜き動画 投稿者
「政治家の方が単体で発信していても、そんなに広まらないと思うんですよね。切り抜き動画が配信されることによって、これまで見ていない人も、見るようになってくる。選挙行動にも反映されると思うので」
中には、切り抜き動画の投稿で多いときで月に90万円ほど稼いだという人もいました(詳しくはこちら↓)。

切り抜き動画が注目されたのが、2024年11月に行われた兵庫県知事選挙。

斎藤元彦氏
SNSや動画サイトで斎藤元彦氏を支持する切り抜き動画が大量に拡散され、当選の大きな要因になったとされています。

SNS分析が専門の鳥海不二夫さんは、兵庫県知事選挙の際の投稿の変化を調べました。
オレンジは斎藤氏を支持しない人の動画、青が支持する動画の投稿数です。

選挙前、支持しない動画のほうが比較的多く投稿されていましたが、告示日直前、斎藤氏を支持する動画の中に、急激に再生数を伸ばす、いわばバズッた動画が複数出現します。
すると告示以降、後を追うように、斎藤氏を支持する動画が急増していきました。
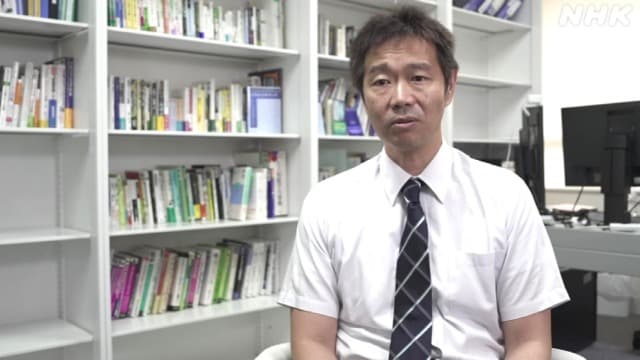
東京大学 鳥海不二夫教授
「人気がある候補者の情報というのは、投稿すればそれだけ再生数が稼げる、それだけ収入が増えると考えられますので、自分自身の立ち位置とは関係なく、人気のある人たちの動画をどんどん投稿していく、切り抜き動画をどんどん投稿していくということを行いがちであるかなと思います」
さらに鳥海さんは、有権者に知っておいてほしいことばがあるといいます。
それが「フィルターバブル」です。

まるで泡の中にいるように、同じような情報ばかりに囲まれることで、SNSや動画サイトの仕組みによって引き起こされます。
実際、選挙情報を動画サイトやSNSで集めていた人に話を聞くと。
YouTubeで選挙情報を集めた大学生
「1回最後まで見た候補者の動画の、関連した動画がYouTubeで流れてくる気がします」
Xで選挙情報を集めた大学生
「一方の政治家の方の悪い点しか見えないような投稿ばかりが表示されていました。その政治家の方が正しくて、もう一方が間違っているというふうに見えてしまいました」

ある候補者の情報を見始めると、その候補者に関する情報が自動的に表示され、それ以外の情報が目に入りづらくなってしまうのです。
東京大学 鳥海不二夫教授
「他の候補者について知るチャンスがなくなりますので。もしかすると本当は自分にとってもっといい候補者がいるかもしれないにも関わらず、それに行き着くことがそもそも難しくなってしまいます」
真偽不明の情報を信じ後悔している女性も
また、SNSで感情的なことばを見ると、人は冷静な判断が難しくなってしまうので、注意が必要です。

例えば、しゅと犬くんがおなかをすかせているとき…スマホで目に入ったのは、ある候補に投票すると「一生ごはんがタダになる」という情報。
思わず飛びついたその情報が、もし間違っていたとしたら?

ゆいさん(仮名)
選挙中に目にした真偽不明の情報を信じてしまい、後悔している女性がいます。20代の会社員・ゆいさん(仮名)です。
地元の知事選挙がふたりの候補の一騎打ちとなり、友人の間でも話題に。SNSでは、候補者に関するさまざまな情報が広がっていました。
会社員 ゆいさん(仮名)
「特に友人がリツイートした情報は、あたかも真実かのように見えてきました」
中でもゆいさんの目を引いたのは、片方の候補は、政策の「文字数が少ない」という批判的な投稿でした。
内容に説得力があると感じ、すぐに友人たちに伝えたといいます。

ゆいさん(仮名)
「悪気も無く、むしろ正義感的な感じで、『伝えなきゃいけない』みたいな使命感がわいてきました」
ところが、投票の直前。ゆいさんが信じた情報は誤りだと指摘した記事が、新聞に掲載されたのです。
ゆいさん(仮名)
「気付いた瞬間は衝撃というか。後悔の方が大きいというか、『自分、何していたんだろう』『なんでこんな情報にのまれたんだろう』という気持ちになりました」
ゆいさんのようなケースは誰に起きてもおかしくない。そう話すのが、社会心理学が専門の安野智子さんです。

中央大学 安野智子教授
「私たちは見たいものを見る傾向があります。これを確証バイアスといいます」
確証バイアスとは、自分の好みやほしい情報に近いものばかりに目がいき、それ以外の情報は無視してしまうという、いわば心のクセです。
たとえば、自分が「いいな」と思う候補者がいた場合、その人に有利な情報はすぐに信じてしまう一方、不利な情報が流れてきても目に止まりづらいのです。
中央大学 安野智子教授
「ある候補にシンパシーを感じたら、その候補のいいところが目につきやすくなるでしょうし、怒りを感じたら、その候補の問題点に目がいきやすくなる。私たちはみんなだまされやすい存在で、バイアスからは逃れられないと考えたほうがいいかと思います」
候補者の情報を探す際の5つのポイント
私たちは、どのように情報を見極めればよいのでしょうか。SNSに流れる情報に詳しい、桜美林大学の平和博教授に聞きました。

選挙情報をインターネット上で探すときに覚えておいてほしい5つのポイントは、「た・し・か・め・て」。
「た」 たどってみよう、発信元は
情報の発信元はどんなアカウントか、確かめてみてください。実名なのか、匿名なのか、どんなプロフィールなのか、これまでにどんな情報を発信してきたのか、発信元を確認することで、情報の信頼度の目安になります。
「し」 しらべて、くらべて、ほかのニュースと
その情報が重要だと思ったら、他のニュースはどう伝えているのかも確かめてみてください。複数の情報源が同じことをいっているかどうか。もし大事な中身が違っていたら、すぐに拡散せず、じっくり確認するようにしましょう。
「か」 感情的な言葉をみたら深呼吸
たとえば「ひどい」「許せない」という怒りのスイッチが入ると、人は冷静な判断が難しくなります。感情が動いたときは拡散をしないということも、とても大切です。感情の高ぶりを感じたときは、一旦スマートフォンやパソコンを閉じて深呼吸をしてみてください。ほんの数秒、気持ちを落ち着けるだけで、冷静な判断力が戻ってきます。
「め」 目立つ動画の即決に注意
いいね!数などの反応が多い投稿は、間違った情報でも、信じやすくなるという研究結果もあります。再生数やリアクション数を狙ったものは画像や見出しにもあります。気持ちが動いても、即決しないようにしてください。
「て」 てがかりとなる根拠や出典は
その情報の根拠になっているもの、根拠自体を確かめてみる習慣をつけると、ネット情報の信頼度を確認することができるようになります。その情報が事実に基づくものなのかという 目で見ることが選挙情報とつきあう上で重要です。
インターネットの情報は膨大で、投票日までに全部を見比べる時間も足りないため、注意をしないと有権者がインターネット特有の現象に知らぬ間に巻き込まれる恐れがあると平さんは指摘します。
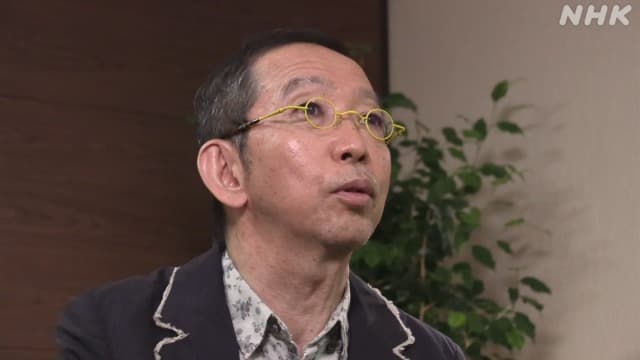
桜美林大学 平和博教授
「選挙の際、世界中で問題視されているのが、ネット上の収益をあげる仕組みです。
アテンションエコノミーという言い方もされますが、これはSNSや動画サイトでアテンション、つまり再生数やいいねの数と言った人々の関心を集めるほど、広告費として収益があげられるというもの。
この仕組みに便乗して収益を上げるために、過激な言葉を使う誹謗中傷やフェイク情報などを選挙期間に発信する投稿者もいるため注意が必要です。
最近は生成AIの登場で誰もが簡単にフェイク画像やフェイク動画などをすぐに作れるようになってきています。
海外ではグローバルな犯罪集団が、社会の関心が集まる選挙の際に投資詐欺などを目的とした選挙関連の広告を発信しており、日本も例外とは言えません。
選挙の期間中は特に、人々の感情を動かすさまざまな意図の刺激的な投稿が増える傾向にあります。情報を信じたり拡散したりする前に“た・し・か・め・て”を確認してほしいと思います」
選挙の情報をどう見極めればいいのか、しゅと犬くんと探る「首都圏情報ネタドリ!」配信は6/20午後7:57まで↓


