
日産自動車のイヴァン・エスピノーザCEOは13日、大規模な再建計画「Re:Nissan」を発表した
EPA/FRANCK ROBICHON
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/19 13:18
ムートゥ朋子

翻訳・編集、週刊「日本のニュースinスイス」担当。得意分野は政治・経済金融。
東京出身。日本経済新聞政治部・経済部で官庁取材や日銀・金融市場を担当。2017年スイスインフォ入社。
筆者の記事について
日本語編集部
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録はこちら
日産・エスピノーサ氏の再建計画
日産自動車は13日、経営の立て直しに向けた大規模なリストラ計画を発表しました。2027年度までにグループ全体で2万人を削減し、車両の生産工場も17カ所から10カ所に減らします。スイスではドイツ語圏大手紙NZZが詳しく報じています。
記事は、4月に就任したイヴァン・エスピノーサ最高経営責任者(CEO)が決めた再建策「Re:Nissan」を「日本では例を見ない抜本的な縮小計画」と評します。工場の閉鎖で生産能力を400万台から250万台に減らすのは「長年の危機を乗り越えて長期的な収益性を回復する」狙いがあると説明しました。
同日発表した2025年3月期の決算は6708億円の最終赤字と、仏ルノーに救済買収される直前の1999年度(6843億円)に並ぶ大損失を記録しました。記事は、「今回は1999年当時よりも大きな挑戦」だとして、ドナルド・トランプ政権の課す25%の自動車関税が、メキシコでの生産台数が多い日産に大きな追加コストをもたらすと解説しています。
「さらに、日産は今回、支払能力を持つ救世主を欠いている」。ルノーとの提携関係は縮小し、ホンダとの合併交渉は破談。エスピノーサ氏は自力で会社を再編成する必要があり、購買や開発の合理化にも着手する方針だと伝えました。(出典:NZZ外部リンク/ドイツ語)
「スイス軍は日本を模範にできる」

日本は北朝鮮などの脅威を理由に長距離ミサイルの配備を進めてきた
AP Photo/Eugene Hoshiko
スイスの複合メディアCH-Media系の複数の地方紙が12日、スイス軍が長距離巡航ミサイルの購入を検討していると報じ、大きな話題を呼びました。系列のオンラインメディアwatson.chフランス語版がその続報としてインタビューした軍事専門家のアレクサンドル・ヴォートラヴェール氏は、中立国スイスが長射程軍備を進める根拠として、日本が手本になるとの見解を示しました。
CH-Media外部リンクの12日の報道によると、スイス軍が購入を検討しているのは米ロッキード・マーティン社製巡航ミサイル「JASSM-ER(AGM-158B-2)」。米国製戦闘機F-35から発射し、飛距離は900㎞以上。米国、イスラエル、オーストラリアが保有し、日本やポーランド、オランダが購入を決めています。スイスはこれまで国境内の防衛に徹してきましたが、JASSM-ERを配備すればロンドンやハンブルク、バルセロナ、プラハ、ブダペスト、ベオグラードが射程に入るといいます。
ヴォートラヴェール氏はJASSM-ER配備の根拠を説明するため、第1に今月7~10日に生じたインド・パキスタンの軍事衝突を挙げました。空中戦で投入された計70~120機の戦闘機は、互いに国境の手前数十㎞から相手国の領空にある敵機を攻撃していたことから、「スイス国境を越えたときにのみ自衛すべきだと考えるのはもはや現実的ではなく、ましてや不合理」だと指摘しました。
第2の根拠としてヴォートラヴェール氏が挙げたのが日本です。第二次世界大戦後に軍隊を放棄した日本は安全保障政策を変更し、射程1500㎞以上の巡航ミサイルを1000発以上取得する計画だと説明したうえで、「日本が提示する(長距離ミサイル保有の)正当性は、スイスにとって興味深い」とみています。
ヴォートラヴェール氏は、「日本は北朝鮮や中国本土から飛んでくる長距離兵器が脅威であると主張している。先制攻撃があった場合に報復する能力を示すことで抑止する必要がある」と説明したうえで、「この議論は、1815年の『武装中立』という(スイスの)当初の原則を思い出させるものでもある」と語りました。
ヴォートラヴェール氏の理論には読者から反論コメント外部リンクが寄せられています。「憲法第9条で軍隊を放棄したはずの日本のように、スイスも偽善者になるべきなのだろうか?」。そうだとすれば、スイス領土外での「予防的」軍事作戦は中立に違反しないのか?いずれにしろ、「日本でもスイスでも法律や国民は軍事同盟への統合は望んでいない」、と主張しました。(出典:watson.ch外部リンク/フランス語)
【スイスで報道されたその他のトピック】
盗まれた仏像が対馬・観音寺に13年ぶり帰還外部リンク(5/12)
日本料理に挑戦外部リンク(5/12~16)
ホンダ、純利益7割減予想 2026年3月期(5/13)
仏語圏グランソンで開催中の「八咫烏展」外部リンク(5/13)
航空自衛隊機が墜落、2人行方不明 愛知・犬山外部リンク(5/14)
収容所経験綴ったダーチャ・マライーニさんインタビュー外部リンク(5/15)
Netflix「新幹線大爆破」に鉄道ファンが熱狂(外部リンク5/17)
早川千絵監督「ルノワール」カンヌ映画祭出品外部リンク(5/17)
スイス人観光客、広島で路面電車にひかれ重傷外部リンク(5/17)
男子テニス錦織選手がジュネーブ・オープン参戦外部リンク(5/18)
話題になったスイスのニュース
先週、最も注目されたスイスのニュースは「CO₂ 回収・除去のスイス新興企業クライムワークスが人員削減へ」(記事/日本語)でした。他に「ルツェルンのラフマニノフ別邸の庭園が一般公開に」(記事/日本語)、「14 歳女子が少年を殺害」(記事/英語)も良く読まれました。
週刊「スイスで報じられた日本のニュース」に関する簡単なアンケートにご協力をお願いします。
いただいたご意見はコンテンツの改善に活用します。所要時間は5分未満です。すべて匿名で回答いただけます。
≫アンケートに回答する外部リンク
次回の「スイスで報じられた日本のニュース」は5月26日(月)に掲載予定です。
ニュースレターの登録はこちらから(無料)
外部リンクへ移動
サブスクリプションを登録できませんでした。 再試行する。
仮登録をしました。 次に、メールアドレスの認証手続きを行ってください。 ご入力いただいたメールアドレスに自動配信メールを送信しました。自動配信メールに記載されているリンクをクリックして、ニュースレター配信手続きを完了させてください。
校閲:大野瑠衣子
続きを読む
次
前

おすすめの記事
トヨタ、沖縄の墓…スイスのメディアが報じた日本のニュース
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/12
スイスの主要報道機関が先週(5月5~11日)伝えた日本関連のニュースから、①試練に直面するトヨタ②トヨタが導く未来のクルマ③沖縄に登場した「ロボット墓所」、の3件を要約して紹介します。
もっと読む トヨタ、沖縄の墓…スイスのメディアが報じた日本のニュース

おすすめの記事
個人的信条より総意を優先 スイス連邦内閣の合議制とは
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/13
スイスの連邦閣僚(政府)は7人の閣僚から成り、合議制で政府方針を決定する。閣僚の個人的信条を押し隠して政府の「総意」を推進するこの仕組みは、スイスの政治的安定を醸成する一方で、責任の所在をあいまいにする危険をはらむ。
もっと読む 個人的信条より総意を優先 スイス連邦内閣の合議制とは

おすすめの記事
関税協議「スイス最前列に」、米財務長官
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/13
ジュネーブで行われた貿易問題を巡る米中閣僚級協議の成功を受け、ベセント米財務長官は12日、「スイスは貿易協定締結の最前列に躍り出た」と語った。
もっと読む 関税協議「スイス最前列に」、米財務長官

おすすめの記事
西側が撤退する人道支援システム どこにもいない救世主
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/14
これまで人道支援を担ってきた西側の主要ドナー国が後退し、世界の人道支援システムは大きな圧力にさらされている。中国や湾岸諸国などの新興ドナー国が台頭する可能性はあるが、旧来のような国連を介した形ではなくなるかもしれない。
もっと読む 西側が撤退する人道支援システム どこにもいない救世主
オピニオン

おすすめの記事
持続可能な農業 AIより「常識」が重要
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/17
農業・食料生産システムにおける重要課題は、人工知能(AI)やデジタル技術では解決できない。
もっと読む 持続可能な農業 AIより「常識」が重要

おすすめの記事
民主主義国家の国際放送が存続の危機に
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/18
世界の国際放送事業で民主主義が劣勢に追い込まれている。米国・西欧の多くが国際放送予算を削る一方、中国やロシアなどは多額の資金を投じて海外プロパガンダを強化する。各国の「情報戦」において、国際放送が果たす役割はどのように変化するのか?
もっと読む 民主主義国家の国際放送が存続の危機に

おすすめの記事
パンデミック条約は多国間主義を照らす鏡に
このコンテンツが公開されたのは、
2025/05/19
スイス・ジュネーブで19日始まった世界保健機関(WHO)の年次総会で、新たなパンデミック条約が採択される。米国がWHOから脱退する情勢下で、「歴史的」な成果として歓迎される。
もっと読む パンデミック条約は多国間主義を照らす鏡に

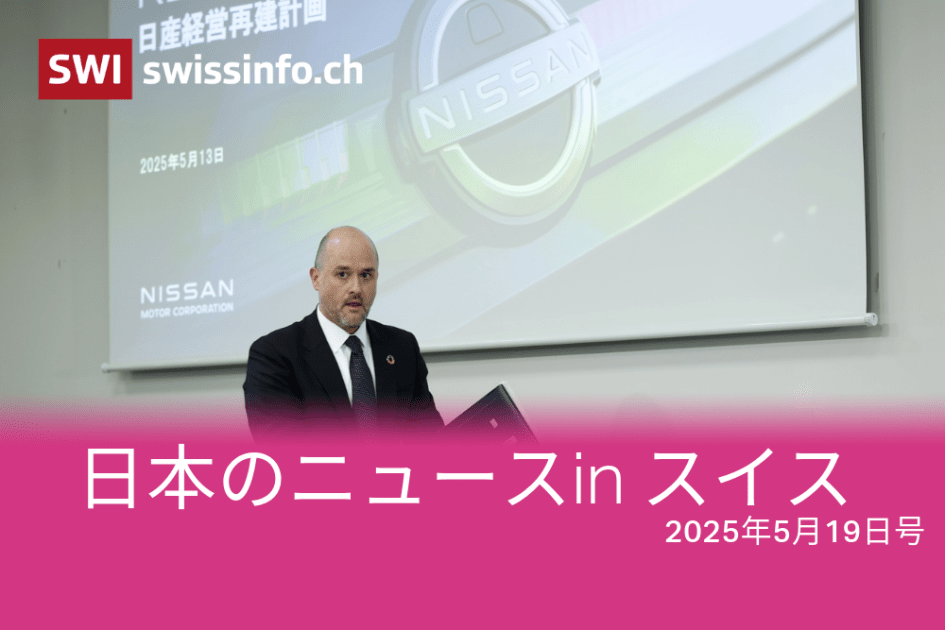
WACOCA: People, Life, Style.