
新潟県中越沖地震, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=1082867 / CC BY SA 3.0
#平成時代の地震
#2007年の日本における災害
#2007年の地震
#中越地方
#新潟県の歴史
#柏崎市の歴史
#2007年7月
新潟県中越沖地震(にいがたけんちゅうえつおきじしん)は、2007年(平成19年)7月16日10時13分23秒 (JST) に発生した、新潟県中越地方沖を震源とする地震である。
地震の規模を示すマグニチュード (M) は6.8、最大震度は6強。
中越地方では2004年(平成16年)の新潟県中越地震以来のマグニチュード6以上および震度5弱以上を観測した地震となった。
気象庁はこの地震を平成19年(2007年)新潟県中越沖地震(英: The Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007)と命名した。
以下、時刻は全て日本標準時 (JST)、自治体の名称は発生当時のものである。
震度5弱以上を観測した地点 震度5弱以上を観測した地点 本震の発生直後、10時14分に佐渡島を含む新潟県全域の沿岸に津波注意報が出され、柏崎(新潟県管轄)では約1m、佐渡市小木(国土地理院管轄)で27cmの津波が観測された。
なお、本震の1時間後の11時20分に津波注意報は解除された。
北西-南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型の地震で、京都大学の研究グループの解析では3つのアスペリティの破壊によるものと推定されている。
この地震の震源域では、200年以上地震が発生していない空白域であった。
震源が海底下にあるためこの地震による断層のような明瞭な変位は地表に現れていない、しかし陸域観測衛星「だいち」に搭載されている合成開口レーダー (PALSAR) による干渉SAR解析を行った結果、震源から15 km東に離れた西山丘陵の活褶曲の向斜軸に沿って幅 1.5km 長さ 15km の帯状隆起域が検出された。
この隆起は、活褶曲が成長した証拠と考える研究者がいる。
活動した断層の位置 この地震については、発生当初から、新潟県中越地震や能登半島地震との関連性がマスメディアを通じて広く報じられた。
これら3つの地震は、断層のずれ方のタイプ(横ずれを伴う逆断層)、断層にかかっている圧力の方向(西北西-東南東方向の圧縮)、規模 (M6.8 – 6.9)、震源の深さ (11 – 17km)、地質学的な地震の分類(直下型地震)などがほぼ同じで、震源の距離も近い。
しかし、圧力の方向や深さは断層型の地震であればよくあるものであり、3つの地震は同じ断層で起きたものではないため、「独立した地震」として扱われている。
これと似たように、距離的に近い地域で短い期間に大地震が発生した例に、1920年代の北但馬地震と北丹後地震や、2016年の熊本地震がある。
だが、新潟県中越地震や能登半島地震が今回の地震の引き金となった可能性もあると考えられている。
この2つの地震が起きた事によって、新潟県中越沖地震を引き起こした断層にかかる圧力(応力)に変化が起き(圧力が増すことも減ることもある)、今回のタイミングで地震が発生したのではないかとの見方もある。
ただ、新潟県中越地震の後の周囲の地殻への応力変化 (ΔCFF) の推定に関しては、気象庁では圧力が減った、産業技術総合研究所活断層研究センターでは圧力が増したなどとなっており、意見は分かれている。
また、断層は北東-南西に延びる逆断層であることはすぐに判明したが、断層の傾く向きは北西側に沈むのか、南東側に沈むのかで意見が分かれた。
北西側に沈む場合、柏崎刈羽原子力発電所のある断層南東側は、断層が地表から浅い所にあることになり、原発の安全対策の欠陥がさらに大きくなることから注目された。
2008年になり、南東側に沈むものであるとする結論が東京大学地震研究所、産業技術総合研究所などから出され、見解は統一されつつある。
これと関連して、過去100年余りの一連の地震活動の傾向や近年のGPSによる観測をもとにした研究により提唱されている日本海東縁から近畿地方北部にかけての新潟-神戸歪集中帯に沿った地域で発生した地震で、かつ1828年三条地震と1964年新潟地震の間にあった空白域を埋めた地震でもある。
高度利用者向けの速報は、出雲崎町の観測点での地震波の検知後、3.7 秒で第1報 M 6.2 を発表し、検知 51.2 秒後の最終報まで、合計11報が発表された。
第1報は、震度6強を観測した長岡市では地震波の到達約3秒前、飯綱町では到達約20秒前である。
7.1 秒後に出された第3報では、2点以上の観測点のデータが利用され、…

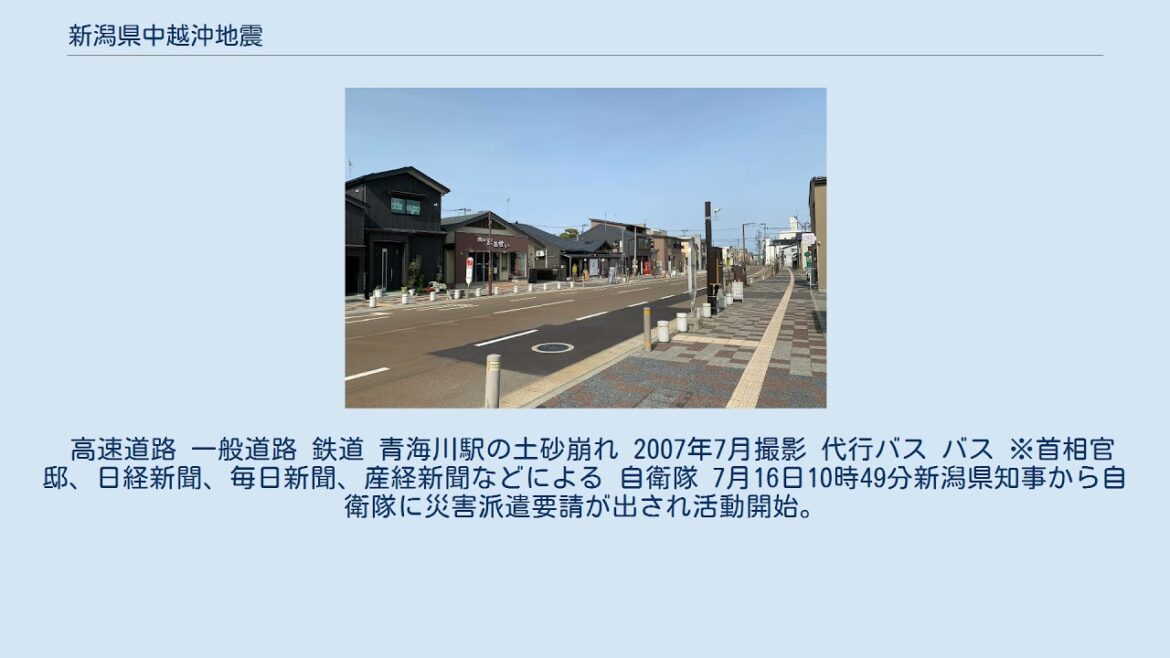
WACOCA: People, Life, Style.