開始から間もなく10年を迎える徳島県のデュアルスクール制度。これは県外に暮らす小中学生の子どもが住民票を移すことなく、一定期間、徳島県内の学校に通えるというものです。地方での暮らしや、地域の子どもとの交流を通して、自然やその土地の文化に触れることができるため、学びの幅も広がると都会暮らしの家族から好評です。単なる短期滞在にとどまらず、「もう一つの学校」として子どもの成長を後押しする点が特徴で、デュアルスクールで訪れたことをきっかけに移住を決断する家族もいます。体験談を紹介します。<前編「地方と都市の学校を“行き来”、徳島発の「デュアルスクール制度」とは? 子連れの里帰り出産や親の介護目的での利用も」から続く>
【マンガ】夫が漁師に、古民家をフルリノベ…移住ライフを描いたマンガを試し読み(全37枚)
MENU
お試し移住で子どもの学校生活への不安を解消
ワーケーションの受け入れ体制も
お試し移住で子どもの学校生活への不安を解消
小学3年生と4年生の男の子2人を育てる阪本さん一家は、徳島県南部にある人口約7000人の那賀町でのデュアルスクールをきっかけに、この春、移住に踏み切りました。もともとは兵庫県宝塚市に暮らしていた阪本さん一家。母親が若い頃に旅行で訪れた徳島県の景色に魅了され、結婚後も家族で度々訪れていました。これだけ頻繁に来るのなら、いっそ移住しては、と考えた阪本さん夫婦。しかし、ネックとなるのは息子たちの学校生活のことでした。
「夫は建築関係の仕事をしていて、私は看護師をしています。移住してもお互いに仕事は見つかりそうでした。ただ、息子たちのことは気になりました」(母親)
移住と聞くと、都会から田舎への移住をイメージしがちですが、阪本さん一家の場合は少し違います。
宝塚で暮らしていた地域にも緑はそれなりにありました。「田舎でもなく、都会でもないという場所で、やっぱりここ(那賀町)とは自然の質が違います」(母親)。 阪本さん一家の子どもたちが通っていた学校は児童数も少なく、上の子の学年には5人、下の子の学年には8人という状況でした。保育園からみんなとずっと一緒に育ってきたため、子どもたちは当初、友達と離れることに抵抗がありました。そんな時に見つけたのがデュアルスクール制度でした。
次のページへお試し移住で子どもの視野も広がる
著者 開く閉じる
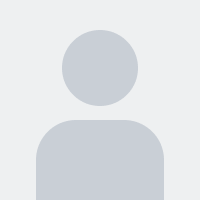
地方紙記者として勤務後、5年間、シカゴにて育児と家事に専念。帰国後フリーランスの記者に。子育て、教育分野を多く取材。『AERA』や東洋経済オンラインの連載『大学受験のリアル』を執筆中。2019年、親子のための中等教育研究所を設立。「東洋経済オンラインアワード2020」ソーシャルインパクト賞受賞。著書に『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)、共著に『知っておきたい超スマート社会を生き抜くための教育トレンド 親と子のギャップをうめる』(笠間書院、大楽眞衣子編著)などがある。


WACOCA: People, Life, Style.