2025年8月26日 午前7時30分
【論説】本年度改定の福井県の最低賃金が千円の大台を超えた。引き上げ額は過去最大の69円で、中央審議会が示した目安の63円を6円上回った。長引く物価高の中で賃金上昇が追い付いていないという労働者側の要求に応えた一方、使用者側からは経営への圧迫を懸念する声が上がる。政府は最低賃金の全国平均を「2020年代に1500円」とする目標を掲げるが、今後の賃上げの持続性には不安が残る。
賃金と物価の好循環の実現は、日本経済の大きな課題の一つだ。春闘を含めて改善の兆しが見えてきたのは、物価高と人手不足が、企業の賃上げを強く後押ししたことが大きい。しかし本年度の中央審議会は、大幅な人件費増にさらされる経営者側の反発で上げ幅を巡る調整が難航。目安額を審議する小委員会の議論は44年ぶりに7回目までもつれて、8月4日にようやく決着した。
これを受けて議論を続けてきた福井地方審議会は、12日に1053円で決着。同審議会の答申では、物価高における労働者の生活安定を図ることに加え、賃上げの流れを非正規労働者や中小企業、小規模事業者に波及させることが適当などとしている。
賃上げは労使交渉の結果であり、政府は直接介入を避けるのが一般的だ。しかし近年、政府は春闘も含めて、経済界に賃上げを強く要請するなど関与が目立つ。石破首相は中央が示した目安よりも最低賃金を引き上げた都道府県を対象に、補助金や交付金で財政支援すると宣言。中央審議会では、赤沢亮正賃金向上担当相が水面下で大幅な引き上げを繰り返し求めたとされ、政府内からも「前代未聞の政治介入」と批判の声が上がった。
県内でも杉本達治知事が経済界に対して積極的な賃上げを要請した。政府が旗振り役を務める賃上げは、短期的には停滞した経済を動かす起爆剤としての役割を果たすかもしれない。しかし、持続性では大きな課題がある。増加した人件費は適切に価格転嫁されることが必要だが、中小や零細では十分転嫁できているとはいえず、こうした企業が取り残されれば、雇用の減少や倒産の増加といった影響を地域経済に及ぼす可能性がある。
福井地方審議会の答申でも、継続的な賃上げのためには価格転嫁に苦しむ中小企業や小規模事業者が賃上げできる環境整備が必要と強調。政府と福井県、福井労働局に支援の充実を求めており、賃上げを要請した政府や福井県などには、これに応える責任がある。賃上げの持続性を保つために、生産性向上など中小企業の稼ぐ力を高める対策を考え抜くべきだ。

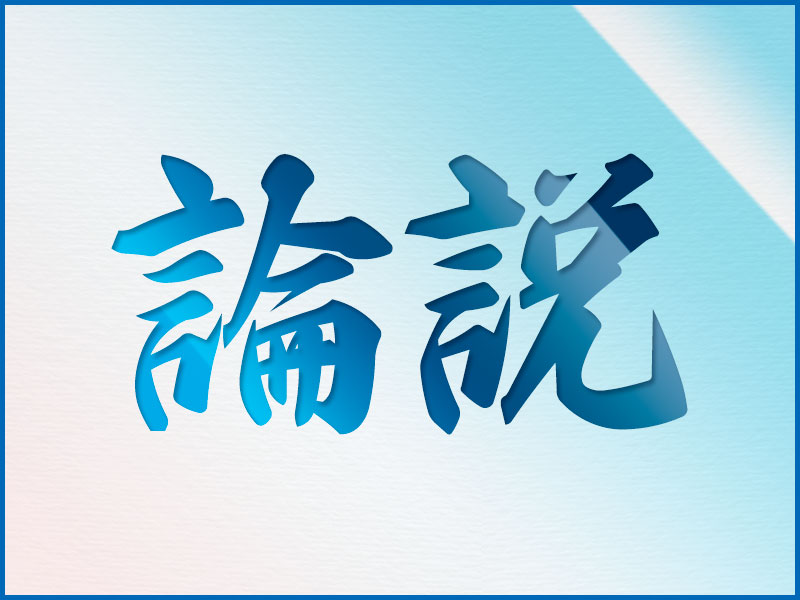
WACOCA: People, Life, Style.