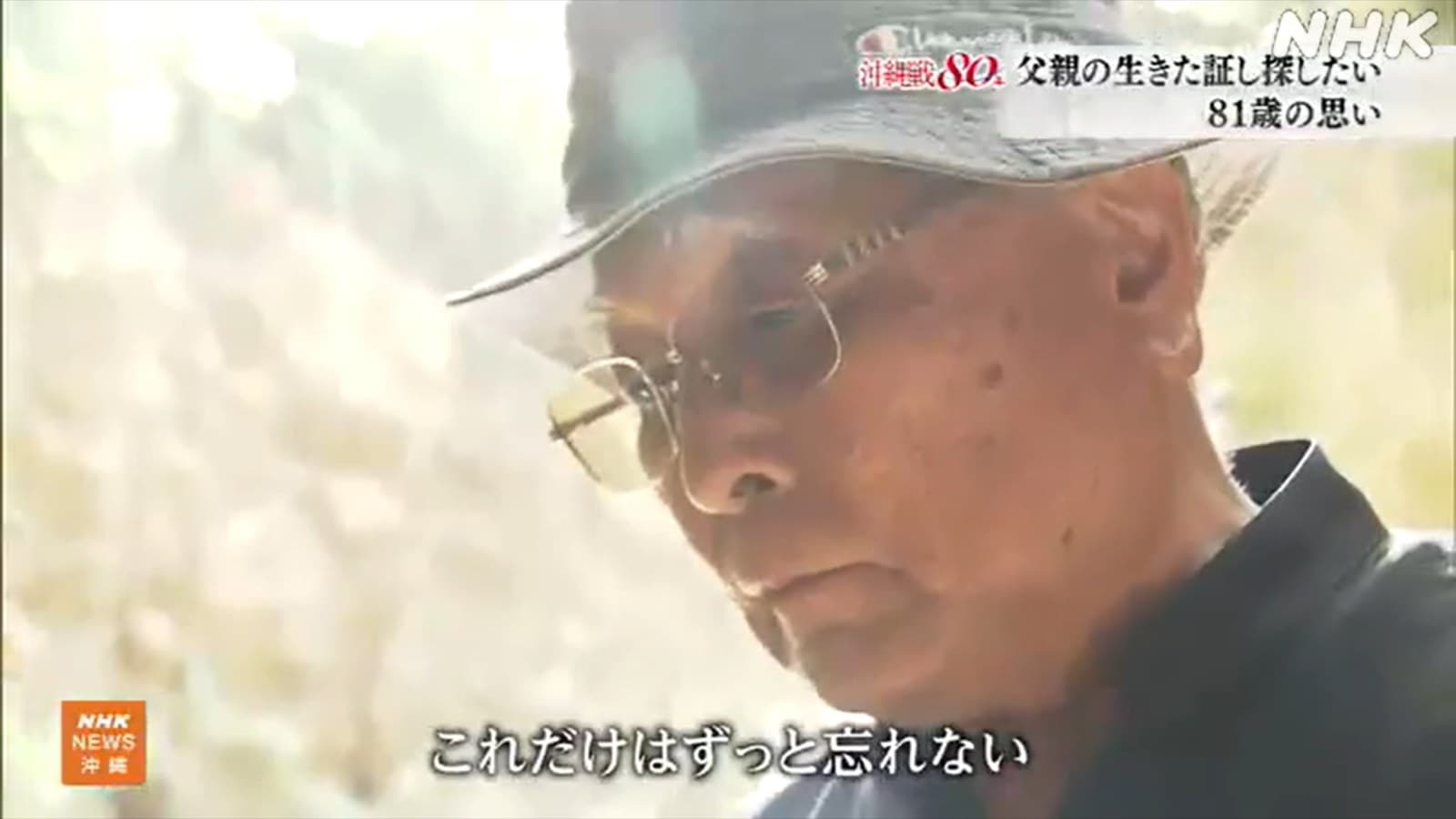
80年前の沖縄を伝えるシリーズ「沖縄戦タイムライン」です。きょうは80年前の6月中旬の本島南部の状況です。
(NHK沖縄 上地依理子記者)
80年前の6月中旬は
日本軍が本島南部に撤退し、「戦いはすんだ。あとは掃討戦だ」とアメリカ軍は考えていました。しかし、日本軍は、八重瀬岳や与座岳、それに国吉丘陵などに残った兵士や武器を集めて、激しい抵抗を繰り広げました。

アメリカ軍は「炎の河」と呼ばれたほどの大量の火炎放射で攻撃するなど、地上戦は凄惨さを増していきます。そうした戦闘に住民が巻き込まれていったのです。当時、離ればなれになりながら、南部の戦闘に巻き込まれた家族についてです。
父親の生きた証しを探す81歳
糸満市に住む山城幸次郎さん(81)は沖縄戦で父親の蒲助さんを亡くしました。2年前から、糸満市伊原周辺で父親が命を落としたかもしれない場所を探し続けてきました。

山城さんは沖縄戦当時の記憶はほとんどありません。ただ、戦後母親から、防衛召集されていた父親が、家族が避難していた壕へ会いに来てくれたと聞きました。

おんぶされている私の頭をたたきながら「そーいりよーや」。方言で「そーいりよーや」って言ったら「お利口さんになりなさい」って、「まぎくなりよー」「大きくなりなさいね」って。
記憶のない父親を見つける作業始める
父親の最期は家族も分かっていませんでした。そうした中、15年あまり前に、自身の所有地に旧日本軍の「埋没壕」がある可能性が出てきました。埋没壕とはアメリカ軍の攻撃などで崩壊し、どこにあるか分からくなった壕のことです。

「身近な場所にお父さんが眠っているのではないか」
年を重ねるにつれて、探したいと思うようになりました。
証言をもとに地形などから壕の場所を想定して作業を始めました。そして10メートル近くあった岩場を重機をリースして取り除いていきました。まだ壕は特定できていませんが、現場近くには遺骨や、手りゅう弾やシャツのボタンといった遺留品が見つかりました。

作業を手伝う平和ガイドは
作業は沖縄戦に詳しい平和ガイドの仲村真さんたちにも協力してもらっています。

(仲村真さん)
ここの地形自体は日本兵が隠れたり、敵の攻撃から身を守る岩の溝になっているので、ここに隠れるというのは当然の場所です。米軍が馬乗り攻撃的に爆破している。ここの入り口が仮に1箇所しかなかったらそこを爆破して、岩にとかうまったら生き埋めですね。
仲村さんは、こうした埋没壕も沖縄戦の残された課題の1つだと指摘します。

(仲村真さん)
80年たっていますから不確定になってきているんですよ。不確定のなかで掘ったり調査しています。仮に埋没壕だったら缶詰めの蓋を開けたような状態です。埋没壕の遺骨については戦後処理なのでしっかりしていないといけない。
戦後80年たった今も募る父親への思い
戦後80年たった今も募る思い。山城さんは父親の生きた証しを探しつづけます。

会えたらいいなって。ずっと忘れないですね。沖縄には私みたいな方がたくさんいる。早く見つかってお墓にでも入れてもらいたいなって。
取材後記
山城さんは、見つかった遺骨について、厚生労働省にDNA鑑定を申請しているということです。これからもできる限り、父親の生きた証を探し続けていきたいと話していました。

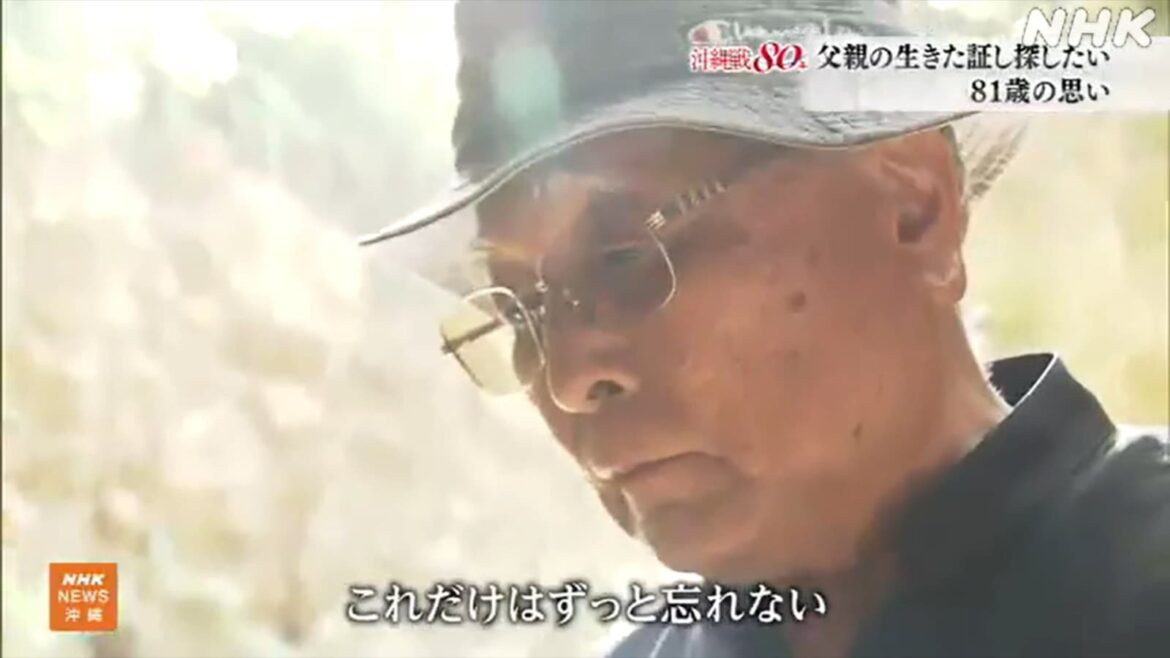
WACOCA: People, Life, Style.