──状況を好転させるために必要なことはどんなことですか?
「これって本当に難しい問題で、結局選手の今の常識で、誰かがディフェンスラインでボールにチャレンジしたら、5バックのときは他の4人は絶対にカバーするポジションをとらなきゃいけないのが鉄則なんですけど、『自分のところにマークがいないから自分はカバーしなくていいや』とか、『負けている状況だからカバーしなくていいや』って言ってカバーしないと、本当にカバーしなきゃいけない状況のときにも(習慣が付いていないことで)戻れなくなるっていうのが大きなリスクとしてあります。今はこのリスキーな場面が多過ぎる。相手選手がいようがいなかろうが、カバーするべきところはカバーしなきゃいけないし、逆に攻撃で言えば、1本のパスが得点につながるっていう思いでプレーしなきゃいけないけど、その1本のパスが雑になってしまったりしている。だから、もっとこだわれるようになるためには、自分の今までの常識を覆して、これまでの非常識を常識にしなきゃいけない。まずは自分の現状を一人ひとりが受け入れて、1本のパス、シュート、チャレンジ&カバー、球際のところとかをもっと変えていかなきゃいけない。去年Jリーグにいて、今年アマチュアリーグ、JFLに落ちたというチーム状況ですけど、現状は選手個々のメンタリティーもまだまだプロフェッショナルではないことが一番の問題なのかなと思います。
そこの改善のためには、練習から『1本のシュートが試合の勝敗を分ける』『1本のパスが勝敗を分ける』『1本のトラップが勝敗を分ける』『1つの競り合いが勝敗を分ける』『球際が勝敗を分ける』という意識で練習の1個1個のプレーをしなきゃいけないんですけど、そこの意識を変えていかなければ、なかなか改善はできないのかなって思います」
──こだわりや意識の変化についてですが、もっと向上させなければいけない選手たちがそこに気付く瞬間は、どういったきっかけがあるのでしょうか?中里選手は例えば若手の頃とか、カズさん(三浦知良選手)と一緒にやったことで何かを得た、など、どこができっかけがあったかと思います。
「いや、多分、多くの選手は気付かないで終わっていくと思います。だからそれに気付く選手が(プロとして)残っていくっていうだけの話。現状、このチームで昇格を狙ってこれだけ負けてしまって、このまま行くとすると、ここにいる多くの選手は多分来年残れないと思います。そうなるとやっぱり『もっとああしとけばよかった、こうしとけばよかった』って気付くのは、年末になるんじゃないですかね。自分が契約をここで終わってしまった時に、『もっとできることがあったな』と思うんじゃないですか。でもそれじゃ遅いし、自分の価値は契約があるうちに自分でしか高められないので、そこを高められれば来年の契約ももらえるだろうし、もっといい環境でやれるかもしれないし。だから、そういったところの気付きは、本当に自分の中の非常識を常識に変えていかなきゃいけないところなので、すごく難しいところだとは思います。
だから、気付かない人の方が多いというのはそういうことで、結局周りが何を言おうが、『変わっていこう、変えていこう』と思うのは自分次第。その意識のところを一番難しいと感じているのはコーチングスタッフじゃないかなって思います。
僕ら選手に対して、もっと意識を高く持って練習してほしいだとか、人の人生が懸かっていることに気付いてほしくて、いろいろな練習メニューを考えたりとか、ミーティングでビジョンを共有できるようにいろいろな映像を作って見せたりしてくれているけど、じゃあ僕たち選手はピッチ上で本当に100%で取り組もうとしているのかなっていうところ。そこの甘さがものすごくあるかなって思います」
──例えばそれは若手だから、あるいはJFLというリーグだから、というようなスキや甘さが関係しているのでしょうか?
「いや、どうなんですかね。でもやっぱり
(残り 1517文字/全文: 3159文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

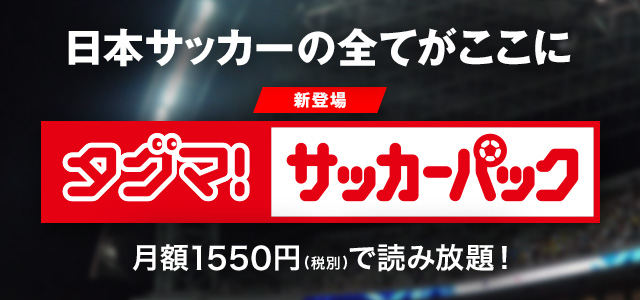
会員の方は、ログインしてください。
タグマ!アカウントでログイン


WACOCA: People, Life, Style.