
コメの価格高騰が続く中、政府の備蓄米がついに放出されることになりました。
その量、21万トン。ごはん茶わんおよそ29億杯※にあたります。
コメの値段は安くなる?いつ買える?どうしてこの量?
さまざまな備蓄米のギモン、経済部の農林水産省担当記者がまとめて答えます。
(経済部記者 富岡美帆)
※玄米21万トンを精米に換算。炊く前の精米65グラムで茶わん1杯分を計算
備蓄米とは?
Q. 政府の備蓄米って何ですか?
A. コメの生産量が大幅に減った場合に備えて、法律に基づいて国が保管している主食用のコメです。
10年に1度の深刻な不作や2年連続の不作にも対応できるよう、毎年約20万トンずつ、合わせて5年分=100万トン程度が全国300余りの倉庫に保管されています。

Q. どのように保管されていますか?
A. 倉庫にあるコメはほとんどが玄米のかたちで保管されています。
保管のルールも決まっていて、倉庫の内部は年間を通して温度は15度以下、湿度は60%から65%に保たれているということで、農林水産省は5年間保管されたコメでもおいしく食べられるとしています。

Q. 利用されたことはありますか?
A. 現在の仕組みになった2011年以降、主食用のコメとして備蓄米が活用されたケースは大きな地震後に2回ありました。
1回目は2011年に東日本大震災の際に被害を受けた流通業者向けに4万トン、2回目は2016年の熊本地震の時に熊本県におよそ90トンがそれぞれ販売されました。
一方、主食用米が不足したことで備蓄米を放出したケースはこれまでありません。
このほか去年にはせんべいなどの原料になるコメが不足したことを受けて、加工用として1万トンが販売されたということです。
Q. 使われなかったときはどうなりますか?
A. 5年間利用がなかった場合、家畜の餌として販売されているということです。
備蓄米制度を運営するため、昨年度(2023年度)は国費から478億円が支出されたということです。
備蓄米 なぜ放出?
Q. 市場に放出することになった理由は?
A. 農林水産省はコメの流通の目詰まりの解消がねらいとしています。
流通が滞った結果、コメの価格の高騰は続いています。
農林水産省のまとめでは、全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、値上がり前の去年5月には5キロあたり2100円程度でしたが、一部のスーパーなどで品薄となった8月には2600円を超えます。
その後も値上がりは続き、直近の2月9日までの1週間では3829円と前の週に比べて141円、前の年の同じ時期に比べると1811円、率にして89%高くなっています。

Q. なぜコメの価格は高いのですか?
A. 農林水産省は、市場に十分な量のコメがないためだとみています。
去年国内で生産された主食用米は前の年より18万トン増えたにもかかわらず、JAなどの主な集荷業者が集めることができたコメは逆に前の年より21万トン減りました。
「本当なら市場には多くのコメが出回っているはずなのに、出ていないのは誰かが流通させていないからではないか」と考えた農林水産省は今回、コメの流通を促す「切り札」として、集荷業者が集められなかった量と同じ21万トンの備蓄米を市場に放出することにしたのです。

江藤農林水産大臣は2月14日の会見で「ほかに手がない。そして、あまりにも(コメの価格が)高い。(備蓄米の放出という)このカードよりほかに手がないということなので、私が責任を取るという覚悟のもとに、カードを切ったということになる」と述べ、政府としてコメの価格の高止まりに対する有効な打ち手がほかになく、苦渋の決断だったことを明らかにしました。
もっと早く放出できなかった?
Q. コメの値上がり前に備蓄米を放出できなかったのですか?
A. コメが品薄になった去年夏の段階でも備蓄米の活用を求める声がありましたが、この時、農林水産省は終始、慎重な姿勢を崩しませんでした。

坂本農林水産大臣(当時)は、新米が本格的に出回ればコメの品薄は順次回復し、価格も一定の水準に落ち着いてくるという見通しを示し、備蓄米の放出については「民間流通が基本のコメの需給や価格に影響を与えるおそれがあり、慎重に考えるべきだ」と話していました。
Q. 農林水産省が放出をためらった背景は?
A.農林水産省は日本の主食のコメについて安定的な生産を続けられるよう、長年、需要と供給のバランスをとる実質的な“生産調整”を行うなど、特別な配慮を行ってきました。
農家にしてみれば、ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で農業に使う資材や肥料などの生産コストが軒並み高騰し、厳しい経営が続いていた中、今回のコメの値上がりでようやく稲作で利益が出る水準になってきたという側面もありました。
こうした中で農林水産省にとっては備蓄米の放出でコメの需給バランスが崩れ、大きく値下がりすることだけは避けたかったというのが本音かもしれません。

Q. 農林水産省が方針を転換したきっかけは?
A. 止まらないコメの価格の高騰が背中を押したといえます。
コメの価格は下がるどころか、上がり続け、2月上旬の小売価格は去年の2倍近くになりました。
こうした状況に農林水産省はついに備蓄米放出の方針を転換。
深刻な不作や災害などに限っていた運用指針を変更し、流通に支障が出た場合でも認めることにしたのです。
江藤大臣は2月14日の会見で「この約半年余りの間に何でもっと早く決断できなかったという批判は甘んじて受け止める」と述べました。
備蓄米はいつ私たちの手元に?どんなかたちで?
Q. 今回放出されるのはどんなコメですか?
A. 初回の放出量15万トンのうち、10万トンは2024年産、5万トンは2023年産が予定されています。
24年産は主に小売向け、23年産は外食や弁当などの中食向けとしての販売が想定されています。
Q. 備蓄米を買うことはできますか?
A. スーパーなどの店頭では3月下旬以降、順次、並び始めるとみられています。
コメの流通ルートは多くの場合、生産者からJAなどの集荷業者、卸売業者、そしてスーパーやコメの専門店などの小売業者を経て、消費者が購入します。
今回放出される備蓄米はまずは集荷業者に入札で売り渡されます。
入札は3月に行われ、3月半ばには集荷業者への引き渡しが始まる見通しです。


消費者の手元に届く時期について、江藤大臣は2月14日の会見で「集荷業者はだいたい1週間程度で卸売業者に売り渡し、その後、数日から1週間程度でスーパーに届くとみられる」と述べ、3月下旬以降、スーパーにあるコメの在庫が切り替わりしだい、消費者の手元に順次、届くという見方を示しています。
備蓄米が十分に流通しているか、農林水産省は状況を確認することにしていて、備蓄米の売り渡し先には2週間に1度、販売数量や金額を報告するよう義務づけられます。
Q. 備蓄米はどんなコメですか?
A. 販売される備蓄米の具体的な品種はまだ公表されていませんが、保管されている備蓄米には「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」など、スーパーでもおなじみの品種に加えて、地域のオリジナル品種などもあります。

Q. スーパーではどのコメが備蓄米か分かりますか?
A. 国は「備蓄米」と明示する必要は無いとしていて、店頭に並んだ場合、備蓄米であることを表示するかどうかは、その事業者の判断によりそうです。
農林水産省はスーパーなどが備蓄米を店頭で販売する際に考えられるケースとして
▽備蓄米だけで販売する場合と
▽ほかのコメと混ぜて販売する場合の2パターンあると見ています。
「備蓄米」と表示する場合、表示しない場合のいずれもあるとしています。
ただ、流通の段階で備蓄米をほかのコメと区別すると手間と時間がかかるため、わざわざ区別せずほかのコメと一緒にして販売するケースが多いのではないかとみています。

Q. 備蓄米はどんな味がしますか?
A. 備蓄米は5年間たっても味や品質が劣化しないよう、湿度が一定に保たれた低温倉庫で保管されているということです。
備蓄米をおにぎりにして食べたという江藤大臣は「全くですね、どれが6年なのか、5年なのか区別がつきません。私も局長も課長も、誰も区別がつかない」と話していました。
コメの価格はどうなる?
Q. 備蓄米の放出でコメは安くなりますか?
A. 専門家からは「短期的には価格が下がるのではないか」との見方が出ています。

コメの生産や流通に詳しい茨城大学の西川邦夫准教授は「21万トンという量は現時点では適切だと考えている。供給量が増えたら価格は下がると考えるのが自然だ。備蓄米が流通業者のもとに渡ると、現物が手に入ることで安心感が広がる。そういった面からも価格は下落する方向にいくのではないか」と述べました。
今回放出される備蓄米21万トンは国内で1年間に消費されるコメのおよそ3%に相当する量にあたります。
Q. ことしのコメの価格はどうなりますか?
A. 西川邦夫准教授は、この先のコメの価格について「中長期的には市場のなかで調整が働くので備蓄米の放出の効果はならされてくる。短期的にコメの価格が下落することでことしのコメの生産が抑制される可能性もあり、その場合には新米が出回る前の端境期にかけてまた需給がひっ迫し、価格が上昇することも考えられる」と述べ、中長期的には需給に応じて価格が変動していくという見方を示しています。
Q. 備蓄米を買い戻すという話もききました。本当ですか?
A. 備蓄米は放出後、政府が原則1年以内に売り渡した業者から同じ量を買い戻すことになります。
これについて西川准教授は「基本的には市場からコメを引き上げることになるので、需給をひっ迫させる要因になる。いつ返すのかというタイミングは非常に難しい」と話しています。
Q. 買い戻しでまたコメ不足にならないですか?
A. 農林水産省も同じ懸念を持っています。
江藤大臣も2月14日の会見で、ことしのコメの収穫の状況が見通せないとして1年にこだわらない考えを示しました。
また、コメの流通の円滑化を促すために必要であれば放出量をさらに拡大することも考えることを明らかにし、今後の流通の状況をみながら判断していくとしています。

そもそも日本ではコメの値崩れを防ごうと需要量に合わせた生産が行われているため、予期しないことが起きると、需給がひっ迫しやすいと指摘されています。
コメの価格を安定させるためには、こうした構造的な問題に手を付ける必要があるという声もあり、今回の問題をきっかけに、改めて日本のコメ政策に注目が集まりそうです。
(2月14日 「ニュースウオッチ9」などで放送)

経済部記者
富岡 美帆
2019年入局
高松局を経て現所属
農林水産省を担当

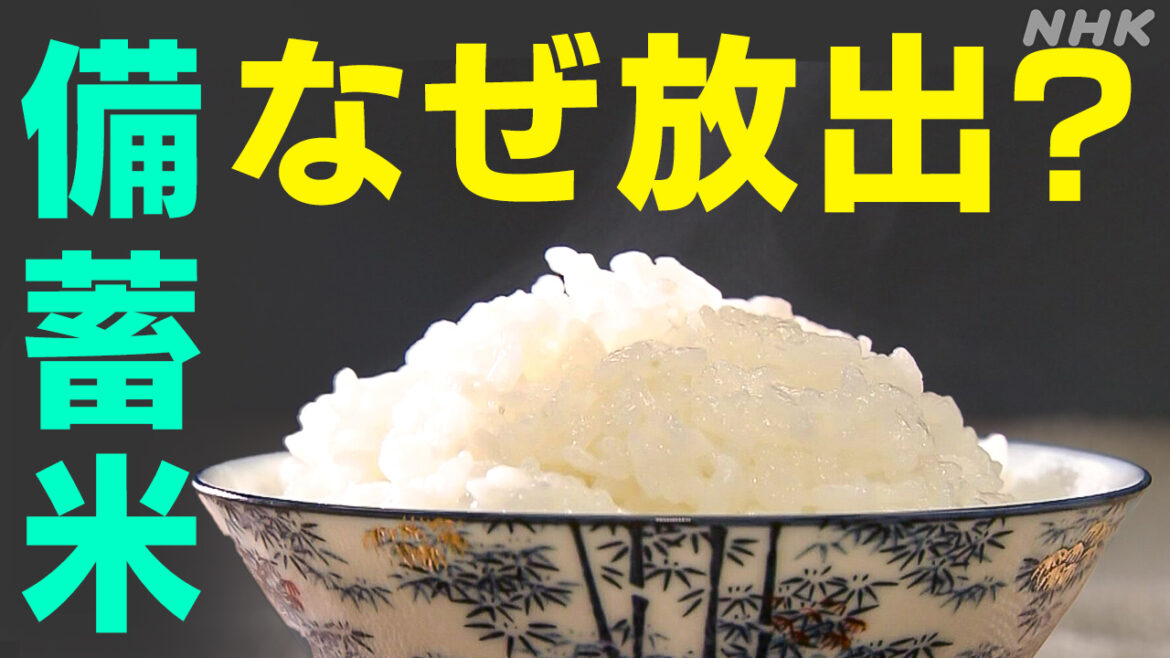
WACOCA: People, Life, Style.