
シリーズでお伝えしている「2025年の論点」。
今回は、戦後80年となることし、核なき世界への道筋をどう考えればいいのか、取材しました。
(報道局 政経・国際番組部ディレクター 柳沼玲花)
日本被団協 石破首相と面会

1月8日、官邸を訪れた、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会のメンバー。
面会した石破総理は、ノーベル平和賞の受賞に祝意を伝えました。

石破首相
「皆様方の長年のご努力に対しまして、心から敬意を表しそして感謝を申し上げる」
これに対し、日本被団協のメンバーは、ことし3月に開かれる核兵器禁止条約の締約国会議に日本がオブザーバーとして参加するよう求めました。
田中熙巳代表委員は「要望を伝える時間が設けられていなかった」としたうえで…。

田中代表委員
「収穫ある総理との会見だったということには、私の受け止め方としてはなかったというのが残念なこと。しつこく会見を申し入れて議論をしていきたい」
戦後80年 核なき世界への道筋は
日本被団協が政府に参加を求めているのが、「核兵器禁止条約」です。

これは、核兵器の開発、製造や保有、使用を禁止する初めての国際条約で、2017年に国連で採択されました。ただ、アメリカなどの核兵器保有国は参加していません。
日本政府は「核兵器国が1か国も参加していない」などとして、参加に慎重な姿勢を示しています。
戦後80年となることし、核なき世界への道筋をどう考えればいいのか。

ノーベル平和賞を受賞した日本被団協で事務局長を務める木戸季市さんです。自身も5歳のときに長崎で被爆しました。
Q.被爆者のお一人として、その80年、率直な感想はいかがでしょうか。
木戸季市さん
「やっぱりあの日のことを思い浮かべます。母が防空壕の前で、もうね、顔、胸にやけどして横たわっているのに、父親が来てね、『ああ、みんな無事でよかった』と言ったのがね、命があるということが無事という、そういう状態だったという、その言葉、本当に忘れられません」
Q.この80年たったいまの核軍縮の状況をどう見ていますか?
木戸季市さん
「いや大変危険だと、危機というのは常にあるんでしょうけどね。プーチンも使おうと公言しているわけですからね、こんな危険な状況で、やっぱり一番使われる危険性が強まっているんじゃないでしょうかね、戦後80年の中で」
そのうえで、木戸さんは、核廃絶に向けて、日本は核兵器禁止条約に参加するべきだと訴えました。
木戸季市さん
「もう、オブザーバーなんて言わずに真正面から取り組んでね、日本が取り組まないといけない。被爆した国は日本ですからね。(日本には)心底、核兵器をなくすという国の代表になっていただきたいと強く感じますね」
なぜ核兵器禁止条約に慎重?

日本政府は、なぜ核兵器禁止条約への参加に慎重なのか…。
それは、「核兵器禁止条約」より前に発効された「NPT=核拡散防止条約」という別の枠組みを重視しているからです。

「核兵器禁止条約」と異なり、NPTにはアメリカなど核兵器を保有する5か国も参加し核軍縮に向けた交渉を義務づけています。
しかし近年は、欧米とロシア・中国などとの間の対立で核軍縮への道のりが厳しくなっている現状もあります。
どう核廃絶に取り組むのか
戦後80年となることし、政府はどう核廃絶に取り組んでいくのか。
岩屋外務大臣に問いました。

岩屋外相
「核兵器国、また非核兵器国が幅広く参加する唯一の枠組みであるNPT体制を大切に考えて参りました。核軍縮あるいは核兵器のない世界に向けた現実的で実践的な取り組みを行っていきたいと考えております」
一方で、ことし3月に締約国会議が開かれる核兵器禁止条約への対応については…。
岩屋外相
「いかなる対応が適切かということを、現在予断なく検証している。しかるべき時期に判断をしていきたい」
若者たち 核なき世界への道筋を模索
被爆者の高齢化が進む中、次世代を担う若者たちも核なき世界への道筋を模索しています。

長崎で行われている、核軍縮について学ぶプロジェクトです。学生たちが、世界の核軍縮の方向性を議論する国際会議に参加するため週に1度、勉強会を行っています。

樋川和子教授
「NPTはみんなが合意しやすい内容にするための努力が行われて、逆に言えば内容は甘くなっているわけですよ。一方、核禁条約のほうは、ものすごく野心的な内容にして、だけれども、やっぱり反対している国は入らないわけですよね。だから、どっちがいいのかという議論ではないんです。簡単な議論じゃないんです」

学生
「日本政府が言っているように NPT体制の中で核廃絶の方向に向かっていきたいというのであれば、保有国と非保有国の橋渡しというのを実行に移してほしい」

学生
「大事なのって核兵器の数とかじゃなくて、そもそも武力で何かを解決しようという考え方の根本的な部分を廃絶しないことには世界平和にはつながらないのかなと」
今後、議論の成果をもとに、海外の若者たちとも核軍縮の道筋について話し合っていく予定です。

学生
「多くの意見を持つ人々と交流を重ねて核兵器に関する新たな視点を得ていきたい。今後の平和活動に生かしていけたらいいなと思っています」
【取材後記】
戦後80年、依然として核兵器は存在し続け、むしろ今、使われかねない危険性すら高まっています。
日本被団協の木戸さんは「核なき世界の実現は広島・長崎だけでなく世界すべての人の課題だ。対話を通じていまの現実を変えていくことが現代に生きる私たちの使命だ」と訴えていました。
そして「命あるかぎり、対話に向けた努力を続けていく」と力強く話していたことが印象に残りました。
一方、長崎大学で学生たちの指導にあたっている樋川教授は、かつて外務省の担当官として各国との軍縮交渉に携わってきた経歴があります。
「世界の核弾頭の数は、冷戦時代のピークで約7万発だったが、いまは1万2千程度に減少している。確実に軍縮が進んでいる事実もある」としたうえで「いかに各国の安全を損なわない形で軍縮を進められるか、悲観せずに知恵を出し合っていくことが大事だ」と話していました。
「核なき世界」という目標に近づくために何ができるのか。各国が、自国の安全保障と向き合いながらも、妥協点を探り、合意できる道筋を考え続けていく必要があります。今後も、取材を続けていきたいと思います。
(1月8日「ニュースウオッチ9」で放送)
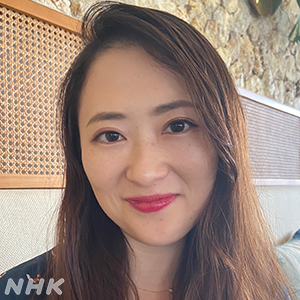
柳沼玲花
報道局 政経・国際番組部ディレクター
2017年入局 福島県出身 札幌局を経て現在は政治番組班に所属。政治改革やいじめ問題などを中心に取材。


WACOCA: People, Life, Style.