「地球最初の生命はRNAワールドから生まれた」
圧倒的人気を誇るこのシナリオには、困った問題があります。生命が存在しない原始の地球でRNAの材料が正しくつながり「完成品」となる確率は、かぎりなくゼロに近いのです。ならば、生命はなぜできたのでしょうか?
この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。本書刊行を記念して、その読みどころを、数回にわたってご紹介しています。
今回は、著者が提唱する「がらくたワールド」を構成する「がらくた分子」がどういうものかについて、筆者自身の解説をお届けします。
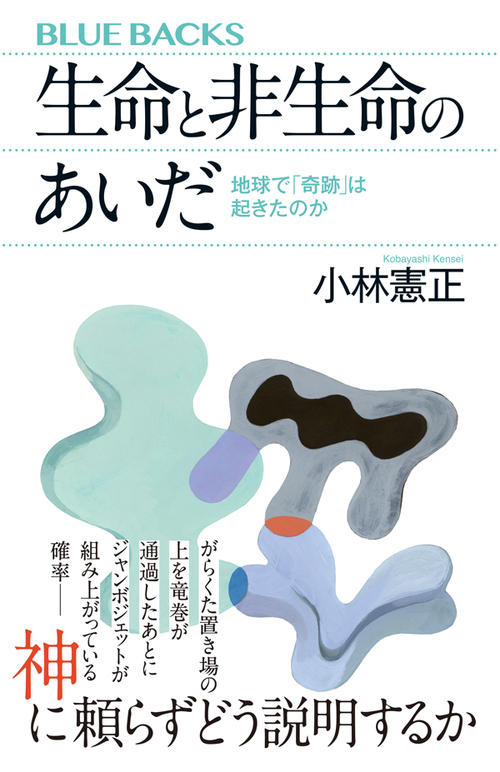
*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。
放射線によってできる「がらくた分子」
原始大気や宇宙空間などで、放射線の影響によりアミノ酸前駆体が生成することを述べてきました。
では、こうしてできるアミノ酸前駆体とは、どのようなものなのでしょうか。
もし、ミラーや欧米の多くの研究者が考えるように、アミノ酸がストレッカー合成*でできるならば、その前駆体はアミノアセトニトリルという比較的単純な分子(図2 ‒ 5)のはずです。
しかし、加速器実験による生成物を加水分解する前に分析したところ、アミノアセトニトリルは少量しか存在せず、加水分解後に生じるアミノ酸のごく一部しか説明できないことがわかりました。では、ここでのアミノ酸前駆体とは、おもにどのような分子なのでしょうか。
*ストレッカー合成:アルデヒド(またはケトン)とアンモニア、シアン化水素との反応により、アミノ酸を合成する反応。詳しくは、『生命と非生命のあいだ』第2章、もしくは記事〈残念ながら、原始地球の大気に「メタンありき」は、思い込みだった…衝撃的だった「ミラーの実験」が残した「1つの功績と2つの罪」〉参照。
 アミノ酸前駆体とは、おもにどのような分子なのか photo by gettyimages
アミノ酸前駆体とは、おもにどのような分子なのか photo by gettyimages
原始大気や星間物質をモデルにした単純な分子(たとえば一酸化炭素、アンモニア、水蒸気の混合物)に、宇宙線を模した高エネルギーの陽子線を照射して、調べてみました。照射を始めるとまず、気相中に「もや」が生じます。
このもやは、水によく溶けます。もやの溶けた水溶液を取り出して分析すると、分子量が1000以上のものが多くできていることがわかりました。これを加水分解すると、いろいろなアミノ酸が生じてきます。したがって、この分子量1000以上のものは、アミノ酸前駆体を含むことがわかりました。
加水分解してアミノ酸ができる分子量の大きいものというと、タンパク質が思い浮かびます。タンパク質はアミノ酸がきれいに一列に並んでつながった分子なので、加水分解すると、ほとんどすべてがアミノ酸になる、優れた生化学的機能を持つ洗練された分子です。
ところが、陽子線照射でできた分子を加水分解してできるアミノ酸は、もとの分子の数%にすぎないことがわかりました。つまり、もとの分子の90%以上は、アミノ酸以外の分子ということになるわけです。

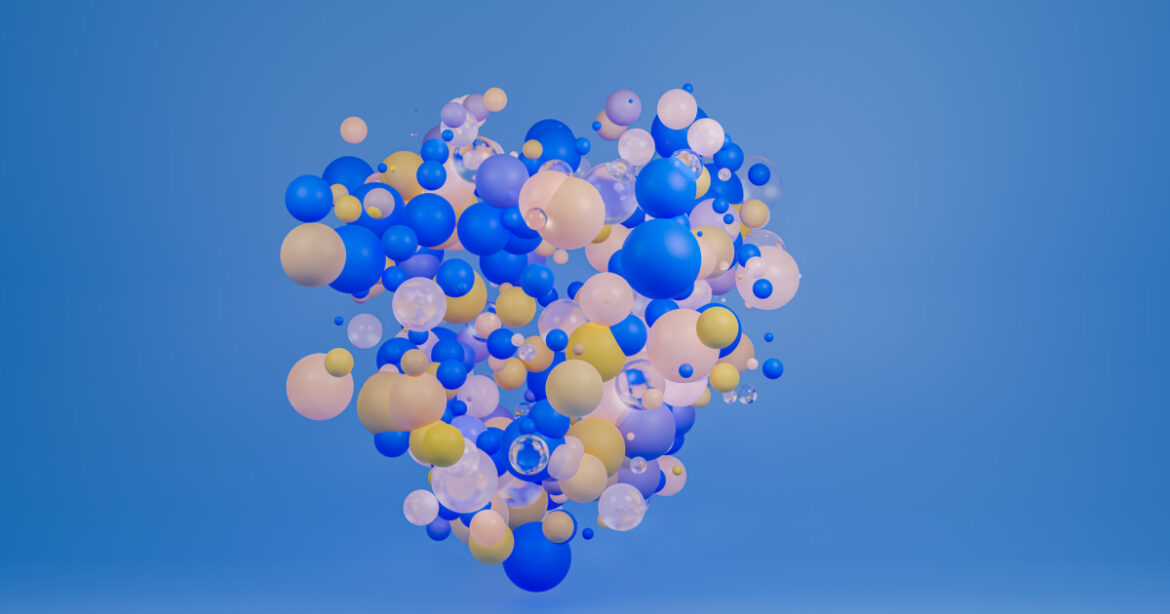
WACOCA: People, Life, Style.