EMC設計オーディオ専用電源vs家庭用電源(対策済み)としてPART7までお届けしたこのシリーズですが、前々回PART8より無対策の家庭用電源を加えた3種類比較の新たなシリーズとしてお届けしております。
新しい3種類比較動画は単一の楽器や声の音源にて行っています。
前々回のピアノソロ、前回のチェロ独奏に続いてスザンヌ・ヴェガの独唱(アカペラ)になります。
これまで同様、完全無編集動画になります。
「EMC設計電源工事の真実」
家庭用電源との比較空気録音 PART10(スザンヌ・ヴェガ独唱編)
女性ヴォーカルのアカペラでも電源の違いは如実に表れました。
さすがに今回の違いが判らない方はいらっしゃらないのではないでしょうか?
EMC設計電源ではこれまでの動画にてハイハットやシンバルが強調されたのと同様に、今回の女性ヴォーカルの場合は歯擦音(しさつおん)や子音(しいん)と呼ばれるサ行が異様に強調され耳に突き刺さります。
もはや「シッ」が「チッ!」となってしまっているかのよう鋭さで楽器以上に耳障りで痛い声となってしまいます。
無対策家庭電源でも多少は歯擦音が乗りますが、EMC設計の電源のように耳に刺さることはありませんし、対策済み家庭用電源においては歯擦音がなくなり自然な生声の質感になっていることが誰が聴いても判るはずです。
EMC電源では、当時28歳のスザンヌ・ヴェガの声がまるで舌足らずな素人の少女が歌っているのかと思えるほどニュアンスが乏しくピーキーかつ一本調子の印象を与えます。
完全対策された家庭電源では、彼女の歌声が年齢相応の落ち着きを取り戻し一つ一つの言葉の発音にまで気を配った抑揚豊かな歌唱であることが判りますし「R」発音時の倍音の消え際までしっかり聴き取れます。
田舎から出てきたばかりのあどけない少女ではなく、都会の大人の女性の憂いをしっかりと醸し出しています。
女性シンガーの呟きにも似た歌唱ですが、対策済み家庭用電源ではその印象も大きく変わり、スザンヌ・ヴェガにこれまで深い興味が無い人にまで「ただ者では無い表現者」であることを気づかせてくれます。
彼女の真価は対策済み家庭用電源で初めて知ることが出来るといっても過言ではありませんし、
EMC設計電源のクオリティでは到底真価を知ることが出来なければ歌手として評価すら変わってしまうことでしょう。
仮に歯擦音全開のEMC設計電源の音が良いという方がいるのであれば、もはやそれは生の歌声を聴いたことがない人と言われても仕方ないと思います。
スザンヌ・ヴェガはボーカロイドではありません。
今回の女性ヴォーカルではもう一つ重要なチェックポイントがあります。
それはヴォーカルの周りに存在する「空間」や「空気感」です。
おそらくスタジオの録音ブース内の空間に漂う音が収録されているのだと思いますが、対策済み家庭用電源ではヴォーカルの周りに明らかにこの「空気感」が存在することが判ります。
声の消え際に注意して聴けばこの「空気感」が存在することが確実に判るはずです。
この「空気感」は無対策家庭用電源においても判ります。
対策済み家庭用電源に比べれば明らかに見通しが悪く感じにくくはなっていますが、「空気感」は確実に存在していることが判ります。
しかし、EMC設計電源では歪んで異様に強調された歯擦音にかき消されて、この「空気感」が全く見えなく(聴こえなく)なってしまっています。
これでは生身の歌手が唄っているのではなく、正に打ち込みのボーカロイドそのものですね。
高級オーディオの価値はこの「空気感」のような微細な情報を克明に再現することで演奏や歌唱のニュアンスや抑揚を浮き彫りにすることで音楽的感動度が高まることにあるはずです。
それは高級オーディオだけでなく、オーディオの電源クオリティにも全く同じことが言えるはずです。
このような形で繊細微細な情報が消滅してしまうのであれば、高級オーディオもオーディオ専用電源工事も必要ありませんよね?
厳しい言い方だと思いますが、この事実を冷静に考えていただければ幸いです。
ヘッドフォン、またはスマホからBluetoothでDAコンバーターやネットワークオーディオに飛ばせる方はご自身のスピーカーシステムでご試聴ください。
下記のURLや秒数をリンクをクリック/ タップすることで頭出しスキップもできます。瞬時に比較出来るので どうぞご活用ください。
【比較用頭出しスキップ】
( “Tom’s Diner” by Suzanne Vega / EMC設計専用電源)
03:37
( “Tom’s Diner” by Suzanne Vega / 無対策家庭電源)
09:19
( “Tom’s Diner” by Suzanne Vega / 完全対策家庭電源)
15:26
(以下の文章は前回までと同文になります。)
今回の動画検証は、余りにもショックな結果となりましたので、自戒も含めてここに公開します。
ボクがEMC設計の電源工事をやって2年と4ヶ月、いまやEMC設計はオーディオ専用電源工事業者として押しも押されもせぬ存在となり全国のオーディオマニアから引っ張りだことなっています。
そのEMC設計オーディオ専用電源工事の最初のユーザーとなり、オーディオにおける電源工事の重要性を事あるごとに発信して来た身としてEMC設計の大成功は感慨深いものがあります。
しかし。。。
先日公開したボクの電源ケーブル徹底比較動画
の中でふとした疑念が生まれてしまったのです。
それはEMC設計の鈴木氏曰く6万円もするEMC設計電源製電源ケーブルが比較した中で一番駄目だったこと。
EMC設計製よりも高額な電源ケーブルに負けるのは当然としてもEMC設計製よりも安価なケーブルや数十年前の電源ケーブルに完敗してしまったこと、さらにはアンプの付属電源ケーブルにさえ部分的に劣るのが判ってしまったことです。
EMC設計製の電源ケーブルがこんなに駄目だとしたら、EMC設計の電源工事に使われている配線材は大丈夫なのだろうか???
激しい疑念と不安が生まれる中、
追い討ちをかけるようなYouTube動画をみつけてしまいました。
(OTAI AUDIOさんYoutubeより)
上記のOTAI AUDIOさんの二つのYouTube動画はEMC設計を行った空気録音と、EMC設計の電源タップを他社の電源BOXに交換した空気録音が聴けます。
つまり、EMC設計電源工事のみの実力とEMC設計電源工事をした状態に高級電源BOXを導入した場合の実際の音質が比較出来てしまうということです。
改めてOTAI AUDIOさんのYouTube動画を聴き比べてみて愕然としました。
こんなにもクオリティが違うのか。。。
しかも、OTAI AUDIOさんのEMC設計電源工事の分電盤の内部配線はこの電源BOXのメーカー製の配線材、一方、ボクの家の分電盤の内部配線はEMC設計製。。。
疑念は決定的となり、無料貸し出しを行っている電源BOXのメーカーへすぐさま電源製品一式をレンタル申し込みをして実験してみたのが今回の結果になります。
結果はあえてボクからは感想を述べません。
誰が聴いても一聴瞭然で判る違いです。
楽器や声の質感やリアリティ、周波数レンジ、ダイナミックレンジ、立体感、空間表現等々、
同じシステムとは到底思えない驚愕の違いです。
2年間、オーディオ専用電源工事をやって良くなったと思い込み、多くの方に推薦してきてしまった立場のボクには、とてつもなく残酷な結果となってしまいました。
自称EMC設計の非公式スポークスマンとしてオーディオ専用電源工事を推薦してしまった恥ずかしさと罪の深さに打ちひしがれる反面で、この動画を公開することで、これ以上の被害者を出さないようにするのがボクに課せられた使命だと考えることにしました。
以下は、決して言い訳ではないので聞いて下さい。
EMC設計の電源工事を推薦している方はボク以外にも著名なオーディオ評論家やレコーディングエンジニア、音楽家、オーディオショップがあります。
その誰もがボクなんか足元にも及ばない知名度と知識、経験値をお持ちの方々です。
オーディオ評論家の中には「EMC設計の電源工事をすれば
他に何もいらない!」と豪語する方までおられました。
しかし、現実はこの動画の通りなのです。
音は誤魔化しが利きません。
当然アンプのボリュームは固定、EMC設計の電源タップと某社の電源BOX以降は全て共通で何一つ変わりません。
ですので、ボクと同じくEMC設計電源工事を推薦してしまったオーディオ評論家やレコーディングエンジニア、音楽家やオーディオショップはこの現実を受けとめていただくしかないのです。
なぜ、このような致命的ともいえる思い込みや履き違えが起こってしまうのか?
それは正に人の思い込み、つまりプラシーボ効果によるものでしょう。
「元の電源から良くすれば全て良くなる」
「大元の電源を変えるのが一番効くに決まってる」
このような強い思い込みに、工事施工業者による説法や講釈が加わることでプラシーボ効果は一層強固なものになるのでしょう。
それはボク自身がそうでしたし、評論家やエンジニアの方も同じだったのだと思います。
ならば罪はないか?といえば答えはノーです。
ボクは自戒を込めて衝撃の事実となったこの動画を公開することでせめてもの罪滅ぼしとさせていただきます。
良質な電源ケーブルや電源製品を使った家庭用電源との比較もせず、EMC設計電源工事があれば何もいらないとまで豪語したオーディオ評論家、無闇に導入を薦めるレコーディングエンジニアやオーディオショップの方々にも猛省していただきたいと思います。
#オーディオ専用電源 #オーディオ電源 #EMC設計 #EMC

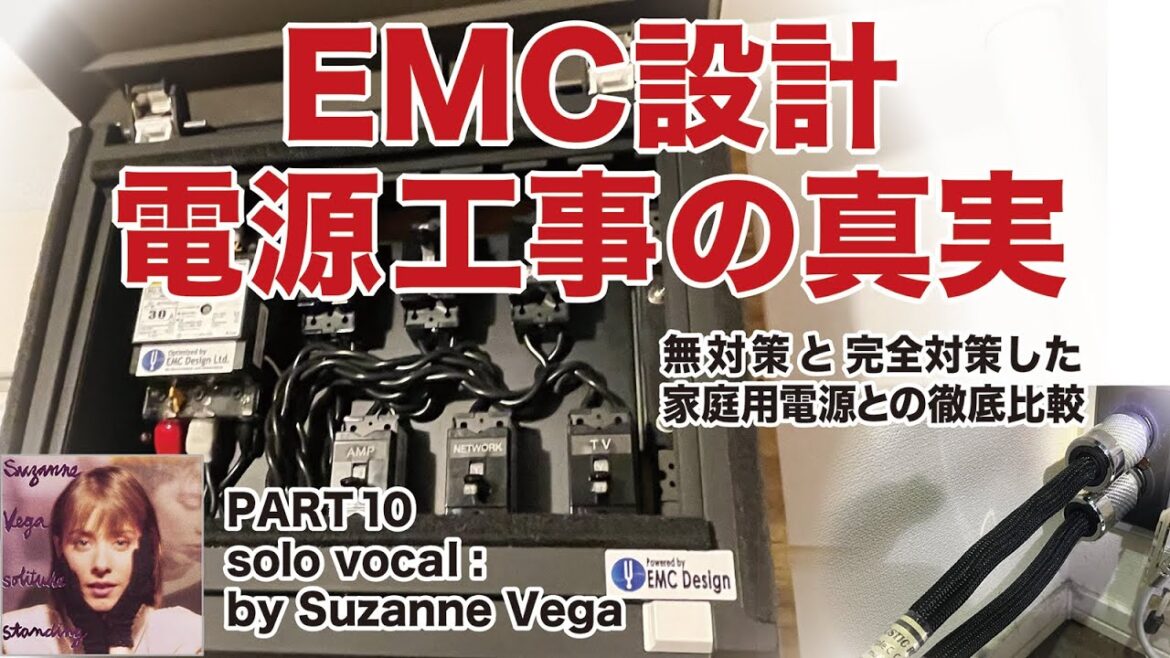
1 Comment
これまでの動画を拝見させて頂きましたが、やはり空気録音では限界がある感じます。こちら側との再生システムとの相性もあるので。何か周波数を図るようなものでやられた方がよりはっきりわかると思います。何も知らないのにコメントしてしまいすいません。興味ある内容でしたのでついつい書き込みました。ご不快でしたら削除してください。