共感やリクエストなどありましたら、是非コメント欄で教えてください。
チャンネル登録をして、次回の動画でもお会いできますと嬉しいです!
コメントや高評価もお待ちしております!
<素材のお借り先>
Peritune
https://peritune.com/
ニコニ・コモンズ
https://commons.nicovideo.jp/
びたちー素材館
http://www.vita-chi.net/sozai1.htm
写真AC
https://www.photo-ac.com/
ぱくたそ
https://www.pakutaso.com/
Adobe Stock
https://stock.adobe.com/jp/
イラストAC
https://www.ac-illust.com/
君の名は – 新海誠
http://www.kiminona.com/
#人間の雑学 #ゆっくり解説 #日本人の雑学

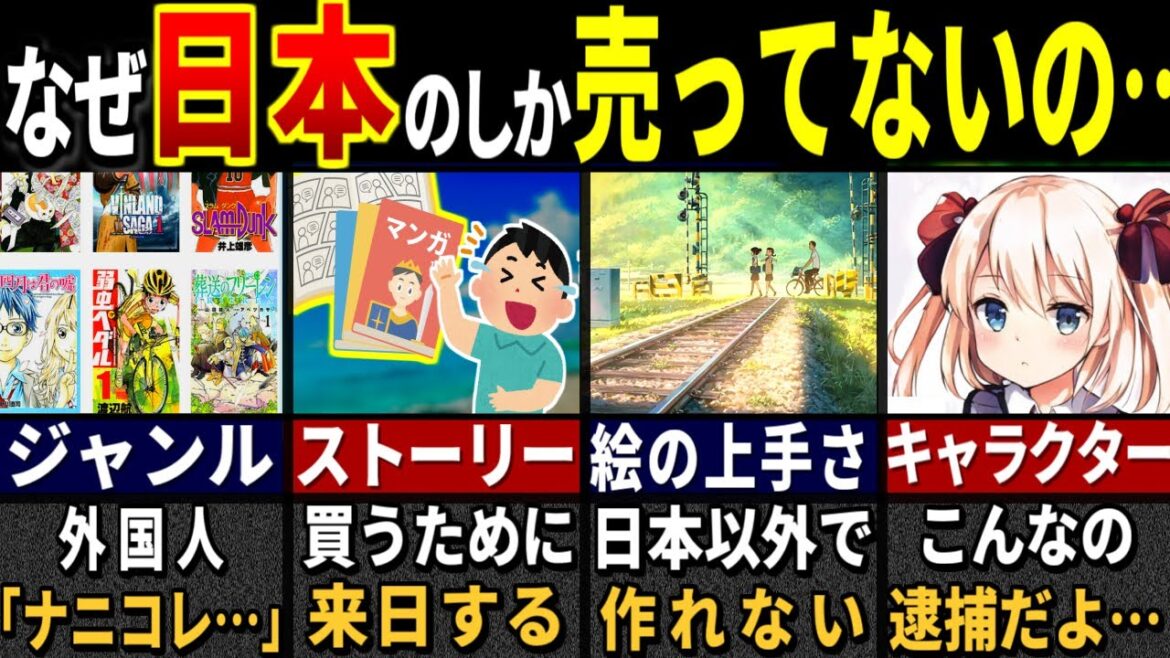
44 Comments
マリとシンゴはキハラ先生によるLGBTQQIAAPPO2S話なのニャ
日本のテレビも表現を規制され続けてつまらなくなったしね……
人形浄瑠璃→アニメ
歌舞伎→特撮
実際にはフェミニズムって差別する事になってると思う
ビックサイトに3日間で入りきれないくらい、絵が上手い人いるんだよな…
なぜ日本の漫画が大人も読めるかというと、戦後、映画好きな若者が映画を作るのにはまだ貧しくて、安価に自己表現できるツールとして漫画を選らんだからなんだ。
第二次世界大戦勝利者だったら…手塚治虫はどんな漫画描いていただろう?
これ作った人へたくそやな。
クール・ジャパンバブルもいい加減このままだと弾ける気がするけどね。
漫画等の絵柄はかなり日本的になってる海外の作家も多い
『マトリックス』は撮影時のカメラワークは日本のマンガのコマ割りを参考にしたって聞いたことがある
携帯漫画は縦スクロールものだが、絵巻物は横スクロールしながら坊さんとかが絵説き話してた
私は7歳位にキン肉マンを
教えて貰ったのが最初です
今年7月にアニメが放送開始されますし、40代後半になっても漫画は読んでますし大好き。
アメコミは多様性じゃなくただの虹色に統一で、多様なジャンルから好きな色を選べってのが多様性だと思うんだけどね
日本の漫画出版社が海外で漫画・シナリオ学校とか作ったら面白いことになりそう。
スポーツ以外のジャンルは手塚治虫がほぼ作っていて
松本零士、赤塚不二夫、水島新司、大友克洋とかある方向のスペシャリストみたいな人が後に続くいろんな漫画家先生へ影響を与えて…って考えると凄いよね。
アメコミは絵のタッチのカッコ良さみたいなものから入るから、それに見合う内容ということでどうも型どおりのものが多くなって「子供向け」のままになってしまった…とアメリカから来てる人は話していた。
だけどなぜあの陰影の強いタッチに拘るのか、たしかに不思議だわ
18禁作品みたいにポリティカルコネクトフリー(規制なし)シールでも用意して何ら作品の改定なく売ってますコーナーに並べるとかすればいいのだ。
あー……
昔々、海外に住んでてたまに帰ってくる親戚がうちに来て、「なんか漫画貸して」と言われて貸すと貪るように読んでたわw
そして読み終わると「完結してないじゃん!!」と理不尽に怒られたw(冗談交じりに残念そうに)
種類は少ないし、あっても高いしで、簡単に読めないんだってさ。すまんかったw
手塚治虫氏以後が漫画が変わって行った。
日本のマンガのタッチは浮世絵がベースになったって話好き
アメコミって『キャラがリアル(等身大米人)』『表情が一辺倒』『起承転結が唐突』『動きの線と移動経路』『元となった作品のif展開作品』って感じですかね
総じて思うのはアメコミって日本で言うところの『同人誌』なんすよね
新しい作品はあまり生み出されず、過去作のifリメイクばっかり、その中で名作もあるのかも知れんけど、同じ作品ばかりじゃ飽きるよね
あと最近はポリコレの影響で風刺で『米のマンガは全て虹色、日本のマンガは1作1作が別々の色で虹色以上の種類がある』って感じの絵があったよね
ただ、虹色って絵具に例えると虹色を全て混ぜると、黒になるのよね。全部乗せで混ぜ混ぜで全部黒いのよ米の作品って
日本のは2~3色合わせた色なんよね、だからそれぞれ違った色が出来上がるんよ
別に戦後、子供向けだったワケではないですよ。
有名作品も多々あるので調べてみてくだい
この話題なら貸し本というシステムについての言及は必要だと思う
「紙とペンさえあれば生み出せる」は世界的に見ると正しいと言えるだろうか? 確かに日本は気軽にストーリーを創作して黒歴史の一つや二つ誰でも持ってるけど、アメリカ何かでは創作に対するハードルはもっと高いのでは? そう考えないと「自分で作れ」と言いたくなるようなことを堂々と言うやつがあんなにいることが説明できない。
ポリコレが多様性だとは考えていません。
多様性は人種などといったものだけでなく、個人の個性を尊重するべきものですが、ポリコレは規制する事で「個人が行う事が出来る」事まで規制していますから。
今のポリコレェはアメリカでヒーローモノのコミックしか残らなかった歴史を踏襲しているように見えるよ。
1990~2010年代は、作者はかなり作者も取材していた印象だよ。
異世界系は、松本人志位の大発明。
科学的な事を無視して、独自のルールで展開。
それを、最近韓国がパクりはじめた。
後、子供が子供だけで自由に買えると言うのもでかい
週刊漫画雑誌で多種多様な漫画家さんの作品を読めたのは、今にして思えば幸せだった。
空想科学雑誌なんかでいろいろ想像していたこともあった気がする。
あと、新聞の4コマ漫画とかかな。それにしても半世紀以上経過したのか。
そう言えば石ノ森先生は仮面ライダーのテレビドラマは子供が楽しむ様に作って、自身が描く漫画は小学生や中学生等の文字を読める様になった子供の為に作りましたと文庫版の漫画に書いてあったのを思い出しました
多様性という名の拘束具が、作品を縛り付けてるんだな。それが怪物のように顕在化したのが今のアメリカだな。
日本に来るアメリカ人はみんな口を揃えて言うよね
アメリカなんかより日本の方が自由の国だって
アメリカに自由なんて何一つないって
出版社がストーリー考えるなら、そらポリコレ一色にもなりますわ
おおむね同意だが
「手塚治虫」がスルーされてるのに
違和感を感じました。
金がないというより物資が無いんだよ。資本家は金は持ってた。アメリカが日本に向けた小麦だって日本は買ってたんだぜ。ただじゃないからな。
日本はイデオロギーよりも商業主義だから消費者が雑誌を買ってくれるか?買わないか?の単純な原理から成り立ってる、だからどんなに有名でどんなに人気が有る漫画家でも駄作を創れば見向きもされない、極めてシビアな世界で育んで来たから日本の漫画家は面白いし多用性がある、キャラもアメリカのフェミが批判するけど現実味が無いからウケるのでありアメコミのキャラは劇画タッチだから批判しやすいんだと思う。
日本は古くから鳥獣戯画から続いてらけどアメリカはアメコミだからつまらんわな
鬼滅の刃やゴールデンカムイみたいに明治後期から大正時代のなんて一般人には馴染みの薄い時代の漫画が受けてるからな
漫画の歴史を振り返るのに、いきなり鳥獣戯画から現代漫画は飛躍し過ぎ。
「のらくろ」
「ヤネウラ三ちゃん」
「タンクタンクロー」
など昔の漫画には触れられていない。
また
「ザザエさん」
「フジ三太郎」
「まっぴら君」
など新聞連載四コマ漫画にも。
あと子供向けの漫画を大人が読み始めた
というのも語弊がある。
というのも昔は今のように「ヤング◯◯◯ン」
など青年向け漫画雑誌が存在しなかった。
「ビッグコミック」はあるにはあるが、読者層は限られていた。
「週間漫画アクション」も大人気とまではいかなかった。
だから、大学生は仕方なくマガジンやサンデー、ジャンプを読んでいたと言っても過言ではない。
出版社もそのことは百も承知。
だから、1970年頃は明らかに青年向け作品も掲載されていた。
永井豪先生の「デビルマン」は漫画の革命だった。
神曲か黙示録を思わせる壮大なスケール。
神と悪魔の闘いを初めて漫画で表現した。
終盤、善と悪とが逆転する、どんでん返し。
これを描くのは生命力を相当消耗したようで、身体も心も疲弊しながら描いていたとか。
ポリコレを理由で海外で販売中止したらどうなるだろうね。ポリコレ勢喜びそうだけどな
ポリコレ的には日本の漫画はレギュレーションを大きく逸脱している、ズルいって思っていそう。
アメコミも70年代はシルモトルームが推していた所為でバンピレラを始めとして結構面白いモノが手に入ったんだけどなァ。コーベンやニーニュ辺りは日本人にも受けていたし……結局X-MENが大売れしたのがヒーロー物一辺倒になる途を決めちゃったな。あの神風みたいなブームが無ければアメコミも方向性模索したかも知れないが、当時は「アメコミ復活!!!」ってんで、そんな懸念は持たなかったんだろね
ポリコレとかフェミとかジェンダーとか、行き過ぎたアホ規制が随分と増えた。
ちょっと前に、ちばてつや先生も「表現の自由」を危惧したコメントしてたよね。
映画やTVなんかはもうヤラレてる、マンガが最後の砦となるかもしれないな。。絶対にシ守するぞ!!!
フェミニズムはわかるけど、それで可愛らしい格好ができないのは変だよね。
男女関係無く、かっこいい格好でも可愛い格好でも好きにすればいいじゃないか。
コマ割りによるモーション表現と視線誘導は明らかに手塚治虫の功績だよなぁ
手塚以降の漫画家はその技法を取り込んで発展させている