今後の伝承のあり方は 大川小遺族が講演 東日本大震災からまもなく13年<岩手県> (24/02/07 21:55)
未来につなぐ宮城県石市の大川小学校を 襲った津波で娘をなくした男性が盛岡市で 公演しましたの半島自身が発生した中今後 の伝承のあり方にも思いを巡らせながら 言葉をつみまし た今月3日1人の男性が盛岡市を訪れまし たしお願いし ます県石市に住む佐藤郎さんですこの日 県立図書館が開いた模しで講演することに なっていまし たします今日はわざわざ本盛岡まで ありがとうございました もう佐藤さんは東日本大震災の津波で児童 と教職員84人が犠牲になった石市の大川 小学校で教訓を伝える活動に取り組んでい ます 自身も6年生だった次女みずほさんを泣き しまし た眠ってるみたいなんですよね起きろて すぐ起きそうなみずほはみずほって言っ たら涙を流しました右目から涙が流学校の そばでその学校の子供たちがドロトラック でブルシット被せられて何十にも流されて 並べられていてはダメだと思います なるべくとかできるだけじゃないですよね これ絶対ダメだなと思うんですよね そのその佐藤さんを師に招いたのは県立 図書館の森本深夜館長 [音楽] です森本館長は震災前か市東中学校で防災 教育の中心を担っていまし た過去の津波の高さを校舎に矢印で示し たり津波を想定した速さで走る車と生徒が 競争し たりそうしたユニークな組が表し震災当日 子供たちは津波から逃れることができまし たどうやったら少しでもこう実感を伴って この災害を自分ごとしてできるかなって いうのを考えている中で学習を楽しみ ながらやっていくのも必要なんじゃない かって思ってましたの でその後文部科学省で安全教育調査官を 務めた後今年度から長となりまし た防災にりんできた2人日の半島自身が 話題に登りますいろんな教訓もあったのに もうちょっと伝わってればとかもう ちょっとうまくあのその後のことも伝わっ てるとよかいいよなっていう県とかは たくさんあの教訓集とか出してんですけど 県民市民レベルでもちゃんともう1回 振り返りをしてやっぱりこう整理して もっと伝えていける部分は伝えていこうっ て保険に入ってた人の話を聞くとやっぱり 東北に親戚がいいだとああだからこれ まずいなと思って入ってたていうだから
伝えることによってそれは改善 できる教訓はもっと行かせたのではないか これから何をすべきなのかそれはなんか こう2人はそれを考えていましたそれぞれ 別々の話の半島で本当に辛い思いをされ てる方たくさんいらっしゃると思うんです がその先が見えない中で私たちの経験が 何かこう次のこう明りになるんじゃないか 13年経ってえ石川でも災害があって もっと強くもっと広く遠くに伝えることが うんこれからは必要になってくるんだなと いう風に思い ますそうして始まった講演会およそ80人 が集まりまし た人間の行事やえ都合は実は関係ないん ですよね地球の都合でって今年の1月1日 お正月ですよねお正月にも地震が来 るっていうことまざまざと見せつけられ ましたよねったとこ震災当時中学校の国語 の教員をしていた佐藤さん多くの生徒が 被災した中でどんな事業をすべきか当初 苦慮したと言い ますこの現実にどう向き合わせたらいいん だろうかっていうことがやっぱり1番え心 を分でもあり ます手探りの中震災の2ヶ月後生徒たちと 俳句作りに取り組みましたそれから素直な 気持ちをゴシ号にしましょうっていう故郷 を奪わないでと手を伸ばすて書いてある ただいまと聞きたい声が聞こえないって 書いてましたもう説明いらないですよね 会いたくてでも会えなくて会いたくてって 書いてましたもうこんな重いのこったご ですよでもまず 振りました情報ました机が大で最愛の娘を 失った体験も伝えます大だっ家で眠ってん のと同じ顔してる呼べば返事してくれそう だったし触ればちょっとお父さんやめて くぐったいなんて言ってくれそうだっただ から何回も呼びました呼んでも呼んでも ピクリともうんともすんとも言わ ない大川では目の前に山がありながら児童 は地震から50分豪邸で待機させられ津波 に会いまし た佐藤さんは備の大切さをこんな言葉で 伝えました命を救うのは山じゃないって ことなんですよ命を少くの山ではなくて山 に登るっていう行動ですよね失うに気づく ことですよね私が今日お話ししたこと全部 この13年間でようやくわかったあの日 言えなかった聞けなかっただ今がいっぱい ありますどんなことがあっても家に たどり着いて元気よくただいま言うまた 行ってきます言って出てくるその繰り返し が防災ですねもうどんなことがあっても
家族に会いたいって思うのが防災ですよ ね大川省を巡る裁判では学校や教育委員会 の防災の不美を認める判決が2019年に 確定その後実現したことがありまし た2020年今度は宮井県の校長先生の 研修会がここで行われるようになりました 10年かかりますここまで是非校長先とか 先生方の研修会に使ってください協力し ますよって言われてもま10年あんまり 相手にしてもらわなかっですよね今は毎年 やってますいいんですよずっとノックをし 続けていればいいと私は思います トントントントントンってずっと叩いてれ ばどっかで鍵が開き始めるかもしれないし 種を負け続けていれば1個ぐらいねいつか 目が出るかもしれま最より聞く人に響く 言葉をそんな思いが込められた1時間でし たいつあるかわからないっていうことは 伝えなきゃいけないしやっぱり語り続けて いかなければいけないことなのだっていう 気持ちを新たに思いました本当にもう自分 ごとしてみんな考えなきゃないんだなって いうことを突きつけられてるんだろうなっ ていう風に思いました ね森長は今後も連携した企画に取り組む ことを約束していましたどっからどこまで 被災地被災者というもう括りはもうなくさ ないとだめだなてオールジャパンでえ みんな でいろんな方向からドをドアをノックする ようなそういう取り組みになればいいなと 思い ます震災の中身あの教訓を整理してで もっと他の方々にもちょっとずつでもいい のでお伝えしていけることができるまた 自分たちもそこからもう1回学び直して 自分たちの備えもしっかりしていけるよう にその1つの学習拠点として県立図書館が 役割を果たしていけれ ばあの日からまもなく13年地道により 深くより遠くへ新たな伝承のあり方を 追い求める動きが始まってい ますDET
宮城県石巻市の大川小学校を襲った東日本大震災の津波で娘を亡くした男性が、岩手県盛岡市で講演した。
能登半島地震が発生した中、今後の伝承のあり方にも思いを巡らせながら言葉を紡いだ。
2月3日、一人の男性が盛岡市を訪れた。宮城県石巻市に住む佐藤敏郎さん(60)だ。
この日、県立図書館が開いた催しで講演することになっていた。
佐藤さんは、東日本大震災の津波で児童と教職員84人が犠牲になった石巻市の大川小学校で教訓を伝える活動に取り組んでいる。
自身も、6年生(当時12)だった次女・みずほさんを亡くした。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「眠っているみたいなんです。『起きろ』と言えばすぐ起きそうな。みずほに『みずほ』って言ったら涙を流しました、右目から。学校のそばで学校の子どもたちが、泥だらけでブルーシートをかぶせられて、何十人も並べられていてはだめだと思う。なるべくとか、できるだけではなく、絶対だめだと思う」
その佐藤さんを講師に招いたのは、県立図書館の森本晋也館長(56)。
森本館長は震災前、釜石東中学校で防災教育の中心を担っていた。
過去の津波の高さを校舎に矢印で示したり、津波を想定した速さで走る車と生徒で競走したり、そうしたユニークな取り組みが効果を表し、震災当日子どもたちは津波から逃れることができた。
森本晋也さん(2021年取材)
「どうやったら少しでも実感を伴って、災害を自分事としてできるかと考える中で、学習を楽しみながらやっていくのも必要なんじゃないかと思っていた」
その後、文部科学省で安全教育調査官を務めた後、2023年度から館長となった。
最前線で防災に取り組んできた2人。元日の能登半島地震が話題に上る。
県立図書館 森本晋也館長
「色々な教訓もあったのに、もうちょっと伝わっていれば。もうちょっとうまく(被災)後のことも伝わっているとよかった。県とかはたくさん“教訓集”などを出しているけど、県民・市民レベルでもちゃんともう一回振り返りをして、整理をして、もっと伝えていけることは伝えていこうと」
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「地震保険に入っていた人の話を聞くと、東北に親戚がいて、まずいと思ったと。だから伝えることによって、それは改善できる」
“教訓はもっと生かせたのではないか”
“これから何をすべきなのか”
2人はそれを考えていた。
県立図書館 森本晋也館長
「能登半島でつらい思いをされている方、たくさんいると思うが、先が見えない中で私たちの経験が、何か次の明かりになるのではないか」
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「13年経って石川でも災害があって、もっと強くもっと広く遠くに伝えることが、これから必要になってくるんだなと思う」
そうして始まった講演会には、約80人が集まった。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「(災害は)人間の行事や都合は実は関係ない、地球の都合であって。お正月にも地震が来るっていうことをまざまざと見せつけられましたよね」
震災当時、中学校の国語の教員をしていた佐藤さんは、多くの生徒が被災した中で、どんな授業をすべきか当初苦慮したと言う。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「この現実にどう向き合わせたらいいんだろうということが、一番心を砕いた部分」
手探りの中、震災の2カ月後生徒たちと俳句づくりに取り組んだ。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「素直な気持ちを五七五にしましょう」
(生徒の作品)
『故郷を 奪わないでと 手を伸ばす』
『ただいまと 聞きたい声が 聞こえない』
『逢いたくて でも会えなくて 逢いたくて』
短い言葉で互いの思いを分かち合うことができたと振り返った。
そして大川小で最愛の娘を失った体験も伝える。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「家で眠っているのと同じ顔をしている。呼べば返事してくれそうだったし、触ればお父さんやめてと言ってくれそうだった。だから何回も呼びました。呼んでも呼んでも、ピクリとも、うんともすんとも言わない」
大川小では、目の前に山がありながら児童は地震から50分校庭で待機させられ、津波に遭った。佐藤さんは備えの大切さをこんな言葉で伝えた。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「命を救うのは山じゃないということ。命を救うのは山ではなくて、山に登るという行動。失う前に気づくべきこと。私がきょうお話ししたこと全部、この13年間でようやくわかった。あの日言えなかった、聞けなかった『ただいま』がいっぱいある。どんなことがあっても家にたどり着いて元気よく『ただいま』と言う。そして『行ってきます』と言って出ていく。その繰り返しが防災。どんなことがあっても、家族に会いたいと思うのが防災」
大川小を巡る裁判では、学校や教育委員会の防災の不備を認める判決が2019年に確定した。
その後、実現したことがあった。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「2020年、宮城県の校長先生の研修会がここで行われるようになった。10年かかりました、ここまで。(教育委員会に)ぜひ校長先生の研修会で使ってください、協力しますよと言っても、10年あまり相手にしてもらえなかった。今は毎年やっています。いいんですよ、ずっとノックし続ければいいと私は思う。トントンってずっとたたいていれば、どこかで鍵が開き始めるかもしれないし、種をまき続けていれば、1個ぐらいいつか芽が出るかもしれない」
“より、聞く人に響く言葉を”
そんな思いが込められた1時間だった。
盛岡市内の教員
「いつあるか分からないということは伝えなければならないし、やっぱり語り続けていかなければと新たに思った」
一関在住の元教員
「本当に自分事としてみんな考えなければならないということを、突き付けられているのだろうと思った」
終了後、佐藤さんと森本館長は今後も連携した企画に取り組むことを約束していた。
大川伝承の会 佐藤敏郎さん
「どこからどこまで被災地・被災者というくくりは、もう無くさないとだめだなって。オールジャパンで、みんなで色々な方向からドアをノックするような、そういう取り組みになればいいなと思う」
県立図書館 森本晋也館長
「震災の中身・教訓を整理して、もっと他地域にもちょっとずつでも伝えていくことができる。また自分たちもそこからもう一回学び直して、備えもしっかりしていけるように、一つの学習拠点として県立図書館が役割を果たしていければ」
あの日からまもなく13年、地道に、より深く、より遠くへ。
新たな伝承の在り方を追い求める動きが始まっている。

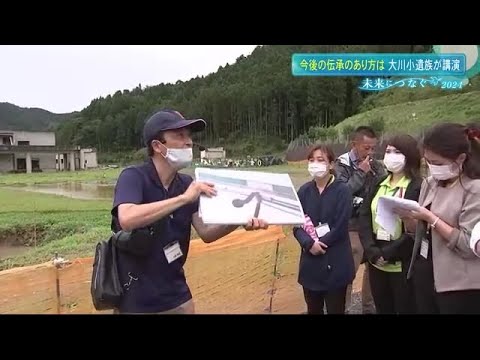
WACOCA: People, Life, Style.