
▼参考文献
戦国武将合戦事典
https://amzn.to/44GADrR
近世における京都室町商人の系譜
※※※※※※※※※※※※※※※※※
【目次】
※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆チャンネル登録はこちらからお願いするでござる!
https://www.youtube.com/sengokubanashi?sub_confirmation=1
◆サブチャンネル『ミスター武士道ch』
https://www.youtube.com/channel/UCp1o7vb0aWiashQAgmL9XDw
◆戦国BANASHIの公式Twitter
◆戦国BANASHI公式サイト
https://sengokubanashi.net/
※参考文献リンクURLはAmazonアソシエイトのリンクを使用しています。
■協力
株式会社メディアエクシード
https://mediaexceed.co.jp/
#日本史 #歴史 #戦国時代

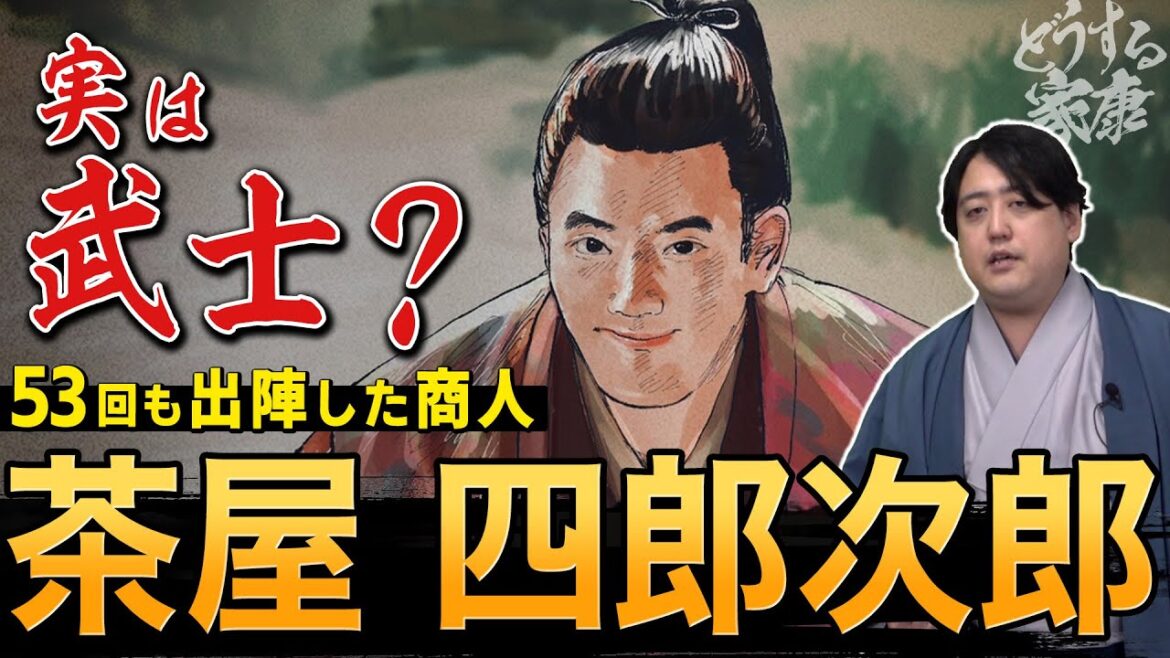
21 Comments
オリキャラかと思ってた…
こういう名前変わってるから気になってるけど良くわからない系の人物解説めっちゃ嬉しいです
どこからともなく現れて
「そのことなら、ワタクシにお任せあれ!」
そつなくこなす、2人だか1人だか分からん名前の四郎二郎…実在してソレもかなりの活躍ぶり…
武士道さんの解説なかったらオリキャラだとスルーしていました😅
この人を主人公の大河とか面白いかもしれませんね。
三越とか松坂屋も元々は武士の家系ですね。
逆パターン初知り茶屋じゃないのに茶屋てよばれてたんだ兵糧,武具調達👍
戦国時代の平均寿命は50歳ぐらいと聞いたことあるので、55歳なら充分天寿を全うしたと思うけどね
今もそうですが、時代の流れに乗ったり乗り損ねたりで、運命が大きく変わってしまうのでしょうね。茶屋家も江戸、名古屋、京都、大阪の四家に分かれましたが、今残っているのは名古屋のみです。その子孫は?というと、私が以前教えていた大学の理事長をしてますよ。
武士から商人に…パッと思い浮かぶのは、この動画でも名前が出ていた鴻池でしょうか。
山中鹿助の子が酒造業を始め、鴻池財閥になっていったということを知った時はビックリでした。
信長が軍事的に強かったのは、兵卒まで職業軍人にし、兵站を丹羽長秀が支え何年も戦争を継続できる能力を持っていたからだそうです、織田軍に同行したり秀吉軍に対抗できたのは、茶屋四郎次郎の働きがあったからかもしれませんね・・・しかし、徳川家臣団から見て茶屋四郎次郎は秀吉にも取り入る、胡散臭い奴と写ったのかもしれません
兵站担当という意味では、豊臣家における石田三成みたいな役どころだったのかもですね。しかも表向きは「商人」として認知されてるから、三成みたいに家中から過剰なヘイトも買わないという良いポジション
この茶屋四郎次郎に注目すると、当時の商人の重要性がよく分かります。武器弾薬などの物資を確実に調達するためには、大商人との提携は必須ですが、茶屋はそれ以上に徳川への改姓や伊賀越えにまで協力しています。特に圧巻なのは、本能寺の変直後にすぐそれを家康に伝え、三河帰還の大きな貢献となる金銭面での援助です。こういう事件が起こると、初動が最も大事で、この時もすぐさま帰還しようとしたことが、勝敗を分けたと思います。なぜ家康がこんな情勢不安な中安全に戻れたのか不思議でしたが、地侍へ金銭を与え落ち武者狩りを防いでいたと知りました。また、今で言えばスパイ活動も行っていて、京都やその周辺の情勢を的確に掴み家康に伝えていたのです。商人という隠れ蓑が、まさにうってつけの役割です。さらに、朝廷工作のための献金もしていたとは、パーフェクトな活躍です!彼の子孫は、関ヶ原の戦いでも京都の商人を介して東軍側に付いているのも、地理的面を考えると凄いことです。その協力の源泉は、海外との朱印船貿易を通じての莫大な利益であり、それがさらに幕府の御用商人としての地位を盤石なものにしたわけです。それほどの隆盛を極めた茶屋家も、鎖国による貿易の停止、三井などの新商人の台頭により衰退してしまうのは、時代の趨勢とはいえ、諸行無常感ありですね!
商人というよりも家康が雇った補給部隊の責任者な感じがする
合戦に目が行きがちですが、数千数万の兵を動かすには、武器、食料、寝場所の用意を臨機応変にこなす裏方はとても重要ですね。
長篠の戦いの時「これからは銭を持ってる奴が強い」と秀吉が言ってましたが家康の銭を支えた人物ですね。大久保長安もドラマに出てくるのかなぁ…?
話は変わりますが茶屋は「四郎次郎」、家康は「二郎三郎」で名前が似てるから意気投合したんだったりして…?
鴻池屋そうじゃなかったけ?
茶屋しろじろうさんって商人で凄いね、もしかして武士だったんだ初耳です。
家康の鷹狩りにも、ついていったと言う話も聞いています。
武士の父親から商人になった例としては、山中鹿之介の息子の山中幸元もそうですね
父が毛利家との戦いで亡くなったあと、鴻池新六として商人として生きて成功して、今の鴻池グループのもとになりました
天下人になった徳川家康と関係が深かった茶屋四郎次郎の茶屋は歴史の途中で消えてしまい、そうではない鴻池屋のほうが力を伸ばして、鴻池財閥として現代でも力を持っているのは意外というかなんというか・・・
戦国時代への入りが信長の野望なので、商人はどこの勢力とも均等に仲良くしてくれるイメージになっていましたw冷静に考えたらそんなわけないですね
神屋宗湛(博多商人 九州征伐~朝鮮出兵まで資金援助や兵站支援も務め莫大な利益)とか津田宗及(堺商人 本願寺や信長に接近し茶会で接待受ける身分)とか…豪商の戦国史も映像化されたら面白そう 南蛮商人とこういった豪商や御用商人とのアクセスを楽にするために改宗する人もいたり(有馬晴信も当初は義父の西郷純堯譲りのキリスト教アンチだったけど大村純忠との同盟や教会からの金銭・弾薬等の支援引き出す為に掌返し)、外交の伝手だったり(大友宗麟は島井宗室・津田ルートから秀吉対面に繋げた)ふと見直すと役割物凄いデカい…