3日前、栃木県足利市で発生した山火事は、いまだ消火活動が続いています。山火事の消火は、なぜ困難なのか。その理由を取材しました。
■住宅への延焼懸念で72世帯に避難勧告
栃木県足利市の両崖山(りょうがいさん)で、21日午後3時半すぎに発生した山火事は、今も燃え続けています。
火の勢いが強くなったのは、23日のことです。
現場近くの寺の住職は「きょう(23日)は、はっきり燃えているのが見えるし、広がっているから心配。(燃えている場所が)かなり飛んでいるというか、間が燃えていなくて、違う所に移った感じ」と話していました。
火は大きな固まりになって燃えている部分と、離れた所にポツポツと点在して燃えている部分があり、広範囲に“飛び火”していることが分かります。
山は市街地に近く、火災現場のすぐ近くには、中学校や高校もあります。住宅への延焼が懸念されたため、72世帯に避難勧告が出されました。
避難した住民は「一番近い所、山の一番奥なんで。1日から2日で消えると思ったんですけど、どんどん火が大きくなって、すごく怖いです」と話していました。
■山火事の消火活動が困難な理由
23日、足利市には乾燥注意報と強風注意報が出ていました。宇都宮では、最小湿度19%、最大瞬間風速23.2メートルを観測しています。
風にあおられて飛び散る火の粉。23日に延焼が一気に拡大した原因は、飛び火を誘発した“乾燥と強風”とみられています。
山火事の消火活動が困難な理由について、火災の専門家、元麻布消防署長の坂口隆夫氏は、「広域的に延焼拡大してしまっているということですから、地上部分からホースを延長して消火するというのが、非常に難しい。限界がありますね」と話します。
■大規模な山火事を発生させた原因
栃木県から災害派遣を要請された自衛隊が、22日正午前から、消火活動に加わりました。
4機のヘリコプターが近くのダムから水をくみ上げ、上空から41回、20万5000リットルを散水。さらに、強風の影響で3時間の中断があったものの、23日も43回、21万5000リットルの水がまかれました。
しかし、いまだ鎮火する気配はありません。
坂口氏は「普通の住宅火災であれば、燃えている実体に水をかけますけども、空中消火の場合には、そこから延焼しそうな樹木に水をかけてると。延焼を防ぐために散水をしているということなんです」と話します。
一体、何がこれほど大規模な山火事を発生させたのでしょうか。
坂口氏は「あくまでも推測ですけれども、人為的な原因ということは、間違いないと思いますね。自然発火というのは非常にまれですから」と話していました。
けが人や住宅への被害は、今のところ確認されていません。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

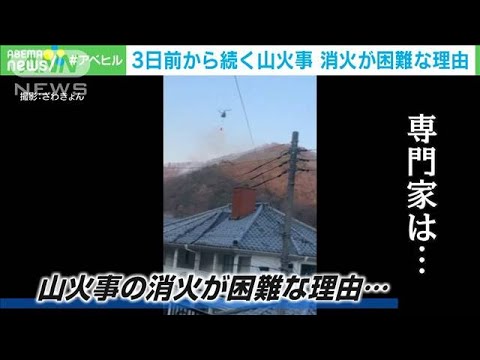
WACOCA: People, Life, Style.