
曲亭馬琴, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=51988 / CC BY SA 3.0
#18世紀日本の小説家
#19世紀日本の小説家
#戯作者
#江戸時代の随筆家
#日本の日記作家
#視覚障害を持つ人物
#武蔵国の人物
#1767年生
#1848年没
#曲亭馬琴
曲亭 馬琴(きょくてい ばきん、明和4年6月9日(1767年7月4日) – 嘉永元年11月6日(1848年12月1日))は、江戸時代後期の読本作者。
本名は滝沢興邦(たきざわ おきくに、旧字体:瀧澤興邦)で、後に解(とく)と改める。
号に著作堂主人(ちょさどうしゅじん)など(#名前について参照)。
代表作は『椿説弓張月』『南総里見八犬伝』。
ほとんど原稿料のみで生計を営むことのできた日本で最初の著述家である。
幼名は春蔵のち倉蔵(くらぞう)、通称は左七郎(さしちろう)、瑣吉(さきち)。
著作堂主人のほか、笠翁(りつおう)、篁民(こうみん)、蓑笠漁隠(さりつぎょいん)、飯台陳人(はんだいちんじん)、玄同(げんどう)など、多くの別号を持った。
多数の号は用途によって厳格に使い分けている。
「曲亭馬琴」は、戯作に用いる戯号である。
滝沢馬琴(たきざわ ばきん)の名でも知られるが、これは明治以降に流布した表記である。
教科書・副読本などで「滝沢馬琴」と表記するものがあるが、これは本名と筆名をつなぎあわせた誤った呼び方であるとして近世文学研究者から批判されている。
曲亭馬琴という戯号について、馬琴自身は「曲亭」は『漢書』陳湯伝に「巴陵曲亭の陽に楽しむ」とある山の名、「馬琴」は『十訓抄』に収録された小野篁(野相公)の「索婦詞」の一節「才馬卿に非ずして、琴を弾くとも能はじ」から取っていると説明している。
「くるわでまこと」(廓で誠)、すなわち遊廓でまじめに遊女に尽くしてしまう野暮な男という意味の俗諺をもじったという解釈もあるが、青年期に武家の嗜みとしておこなった俳諧で用いていた俳号の「曲亭」と「馬琴」が戯号に転じたもので、「くるわでまこと」を由来とするのは妄説であるという反駁がある。
「曲亭馬琴」と組み合わされて明記されるのは、寛政5年(1793年)の『花団子食気物語(はなよりだんごくいけものがたり)』に付された、山東京伝による序においてである。
明和4年(1767年)、江戸深川(現・江東区平野一丁目)の旗本・松平信成の屋敷において、同家用人・滝沢運兵衛興義、門夫妻の五男として生まれる。
ただし、兄2人が早世しているため、三男として育った。
滝沢家には長兄・興旨、次兄・興春、妹2人があった。
馬琴は幼いときから絵草紙などの文芸に親しみ、7歳で発句を詠んだという。
安永4年(1775年)、馬琴9歳の時に父が亡くなり、長兄の興旨が17歳で家督を継いだが、主家は俸禄を半減させたため、翌安永5年(1776年)に興旨は家督を10歳の馬琴に譲り、松平家を去って戸田家に仕えた。
次兄の興春は、これより先に他家に養子に出ていた。
母と妹も興旨とともに戸田家に移ったため、松平家には馬琴一人が残ることになった。
馬琴は主君の孫・八十五郎(やそごろう)に小姓として仕えるが、癇症の八十五郎との生活に耐えかね、安永9年(1780年)、14歳の時に松平家を出て母や長兄と同居した。
天明元年(1781年)、馬琴は叔父のもとで元服して左七郎興邦と名乗った。
俳諧に親しんでいた長兄・興旨(俳号・東岡舎羅文)とともに越谷吾山に師事して俳諧を深めた。
17歳で吾山撰の句集『東海藻』に3句を収録しており、このときはじめて馬琴の号を用いている。
天明7年(1787年)、21歳の時には俳文集『俳諧古文庫』を編集した。
また、医師の山本宗洪、山本宗英親子に医術を、儒者・黒沢右仲、亀田鵬斎に儒書を学んだが、馬琴は医術よりも儒学を好んだ。
馬琴は長兄の紹介で戸田家の徒士になったが、尊大な性格から長続きせず、その後も武家の渡り奉公を転々とした。
この時期の馬琴は放蕩無頼の放浪生活を送っており、のちに「放逸にして行状を修めず、故に母兄歓ばず」と回想している。
天明5年(1785年)、母の臨終の際には馬琴の所在がわからず、兄たちの奔走でようやく間に合った。
また、貧困の中で次兄が急死するなど、馬琴の周囲は不幸が続いた。
寛政2年(1790年)、24歳の時に山東京伝を訪れ、弟子入りを請うた。
京伝は弟子とすることは断ったが、親しく出入りすることをゆるした。
寛政3年(1791年)正月、折から江戸で流行していた壬生狂言を題材に「京伝門人大栄山人」の名義で黄表紙『尽用而二分狂言』(つかいはたしてにぶきょうげん)を刊行、戯作者として出発した。
この年、京伝は…

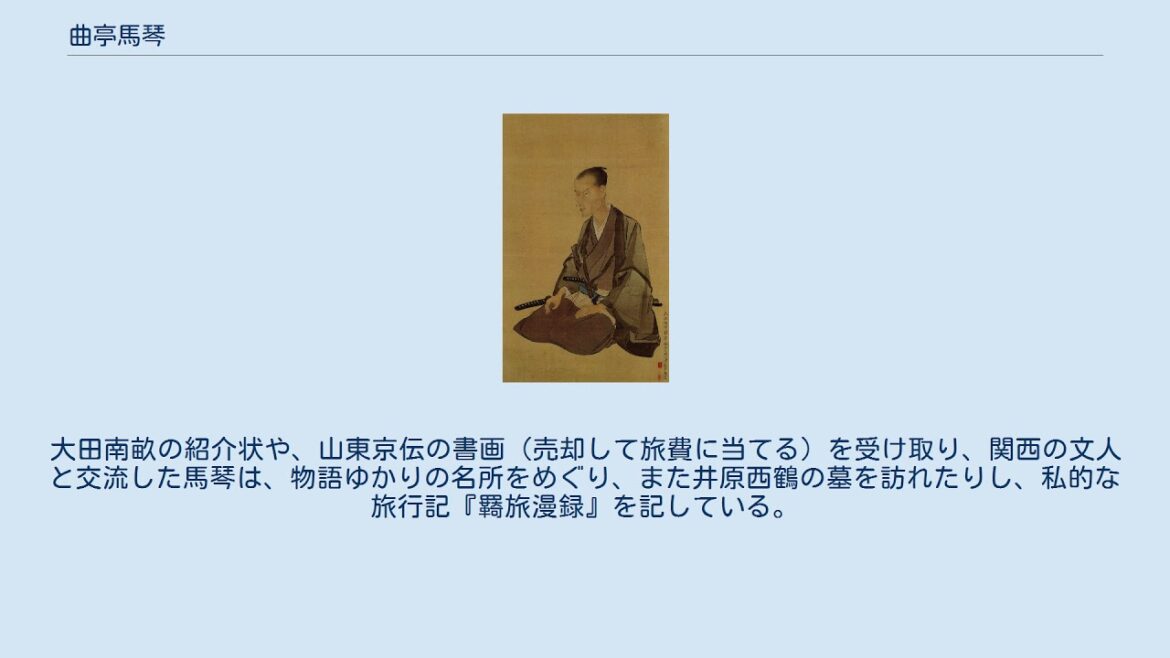
WACOCA: People, Life, Style.