スエズ運河, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=18532 / CC BY SA 3.0
#スエズ運河
#イギリス帝国
#チョークポイント
#スエズ県
#イスマイリア県
#ポートサイド県
#イギリス・エジプト関係
スエズ運河
スエズ運河(スエズうんが、アラビア語:قناة السويس)は、エジプトのスエズ地峡(スエズちきょう)に位置し、地中海と紅海(スエズ湾)を結ぶ、海面と水平な人工運河である。船だけではなく、大東電信会社の電信ケーブルも運河を通った。
1869年11月開通。本運河によりアフリカ大陸を回らずにヨーロッパとアジアを海運で連結することができる。運河は北端のポートサイドと南端のスエズ市タウフィーク港を結び、中間点より北に3キロメートルの運河西岸にはイスマイリアがある。
建設当初のスエズ運河は全長164キロメートル(102マイル)、深さ8メートル(26フィート)だったが、その後何度かの拡張工事を受け、2010年段階では全長193.30キロメートル(120.11マイル)、深さ24メートル(79フィート)、幅205メートル(673フィート)となった。
スエズ運河は南北どちらかの一方通行で運営され、船のすれ違いはバッラ・バイパス(Ballah By-Pass)やグレートビター湖など4か所で可能である。運河には閘門が無いため海水は自由に流れ、主に夏にはグレートビター湖から北へ、冬は南へ水流が生じる。潮目の変化は湖の南で起こる。
運河はエジプト政府が直轄する(SCA)が所有運営している。しかし、国際協定における規定も存在し、1888年のコンスタンチノープル協定では紛争時を除き航行の自由が保障されたが、「有事の際も平時同様、軍事目的の船舶であっても、所属国の如何を問わず」航行が認められるという解釈もなされている 。
運河は、喫水20メートル(66フィート)以下または載貨重量数240,000トン以下かつ水面からの高さが68メートル(223フィート)以下、最大幅77.5メートル(254フィート)以下の船が航行できる。これを上限とする基準をスエズマックスという。この基準では、超大型のタンカーは航行できない。載貨重量数が超過するような場合は、荷物の一部を運河が所有する船に一時的に分載して、通過後に再度載せ直すことも行われる。
1869年に運河が開通するまで、トーマス・フレッチャー・ワグホーンの陸送郵便やロバート・スチーブンソンの鉄道路など、地中海と紅海の間は船から荷降ろしされ陸上を運搬する方法がしばしば用いられていた。
スエズ運河を通過しなければ、アフリカ大陸南端のアガラス岬を回航しなければならない。現在でもこの航路を取る必要があるスエズマックスを超過する船は、ケープサイズと呼ばれる。ロンドン‐横浜間を例に取ると、アフリカ回航では14,500海里(26,900キロメートル)かかるところを、スエズ運河を通れば距離は11,000海里(20,400キロメートル)となり、24%の短縮となる。ただし、21世紀初頭にはソマリア沖の海賊や高い保険料を避けるために、この航路を取る船が増えた。
スエズ運河を挟む地中海と紅海には海面の高度差がほとんど無く、運河中に閘門は設置されていない。運河を通行できる航路は1レーンのみ設定されており、船がすれ違う場所はエル=カンタラ近郊のバッラ・バイパスやグレートビター湖など5カ所に限定される。そこで通常は、10-15隻程度の船団3つを組んで航行することになる。ある一日を例に挙げれば、北から1船団が早朝に進入し、グレートビター湖に停泊すると南から上る船団を待ち、ここですれ違う。この南からの船団はバッラ・バイパスまで進むとここに留まり、北から来る2番目の船団とすれ違う。運河を通過するには約時速15キロメートル(8ノット)の速度で11から16時間かかる。このような低速航行をすることで、運河の岸が波で浸食されることを防いでいる。運河は年中無休で運用されている。
1960年代から運河は全面的な改修が行われた。第1期工事は1961年に始まったがスエズ動乱で長く中断し、1975年に再開され1980年に13億ドルをかけた拡張計画が終了した。これによって航路幅は89メートルから160メートルに、水深は14.5メートルから19.5メートルとなり、通過できる船舶の規模も拡大した。
1995年までに、ヨーロッパで消費された石油の3分の2はスエズ運河を経由した。世界の近海航路を利用する船舶では7.5%がスエズ運河を利用し、2008年の統計では21,415隻が通過し、総計53億8100万ドルの使用料が納められた。1隻あたり平均料金は25万1千ドルである。スエズ…

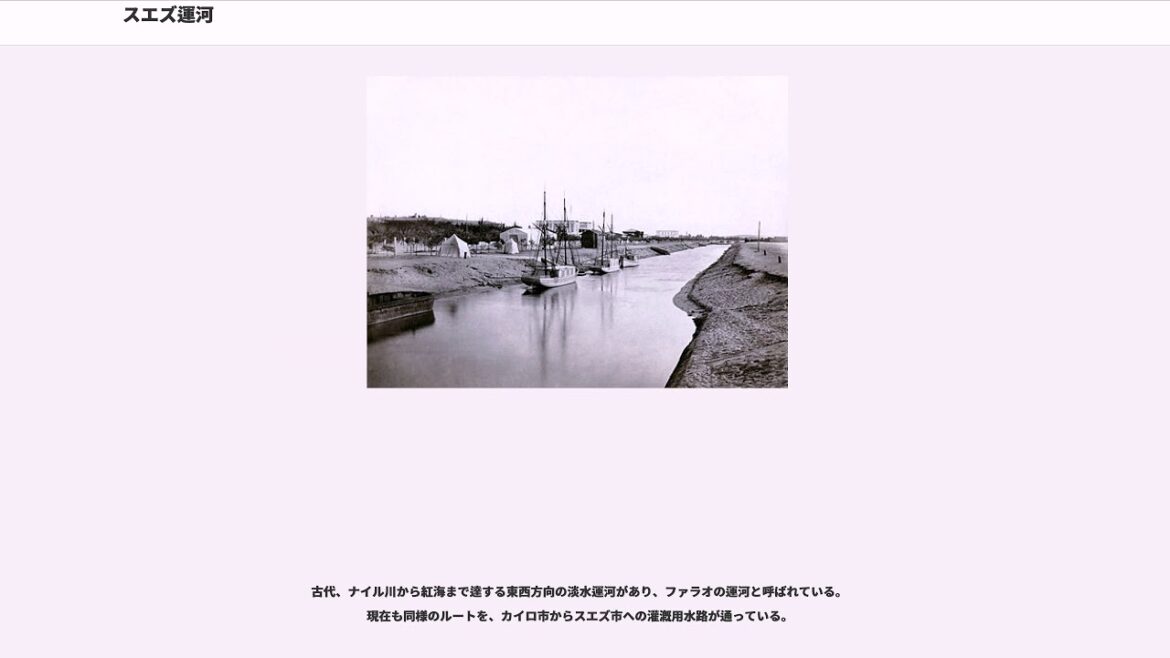
WACOCA: People, Life, Style.