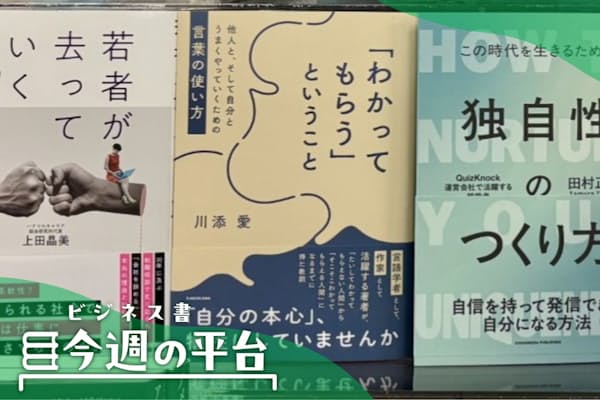売れ筋を並べた平台のランキング紹介コーナーに面陳列で展示する(青山ブックセンター本店)
本はリスキリングの手がかりになる。NIKKEIリスキリングでは、ビジネス街の書店をめぐりながら、その時々のその街の売れ筋本をウオッチし、本探し・本選びの材料を提供していく。
今回は、定点観測している青山ブックセンター本店だ。9月に入っていくぶん鈍ったものの、この夏大きく伸びたビジネス書の売れゆきは好調が続いている。下旬には著者が登壇するイベントの開催も相次ぎ、さらなる上積みに期待がかかる。そんな中、書店員が注目するのは、「わかってもらう」ことをめぐって自身の体験から得た学びをシェアするようにつづった元言語学者の本だった。
大前提は相手に敬意を示すこと
その本は川添愛『「わかってもらう」ということ』(KADOKAWA)。著者の川添氏は言語学、自然言語処理を専門とする1973年生まれの元研究者で、津田塾大学や国立情報学研究所で特任准教授を務めた。最近は文筆活動が中心で、『コンピュータ、どうやってつくったんですか?』『ふだん使いの言語学』といった一般向けの著作のほか、小説作品もあって作家としての顔もある。
そんな著者だが、「話すこと」に苦手意識があるという。それゆえに「どうすればわかってもらえるか」と考えるほうに頭を使ってきたと書く。その過程で自分が体験した「わかってもらう」ためにやってみて良かったこと、大切に思っていたことを中心にまとめたのが本書だ。
まず「わかってもらう」ことを少し掘り下げるところから本書は始まる。「わかってもらうこと」とは「言葉を使うことで、他の人たちと、そして自分自身とうまくやっていくこと」と著者は考える。他の人たちばかりでなく自分ともうまくやるのもポイントだ。他人と自分、自分と自分の関係を調整することでうまい「落としどころ」となるような言葉の使い方はできないか。本書はそこを探っていく。
「わかってもらう」ための大前提と、わかってもらうの手前にある「聞いてもらう」ために必要なことを提示した後、シチュエーション別に「わかってもらうための言葉の使い方」を考えていく。最初は質問、次に連絡・依頼・指示、そこから説明、意見、感覚・感情へと進み、最後の章で「わかってもらう」ための言葉の選び方を考える。
大前提の最初に挙げられるのが、「相手に敬意を示す」ことだ。わかってもらうのだから伝える相手がいる。自分の言葉を届けたい相手をめぐっていろいろな角度で想像力を働かせ、言葉を発するのが「わかってもらう」ための基本となる。
連絡・依頼・指示は「要件の内容をそぎ落とす」
例えば、仕事の局面でよく出てくる「連絡・依頼・指示」では、要件の内容をそぎ落とすことが重要だ。言葉の曖昧さを回避する上で、具体的な情報を一言入れるのも有効だ。「結構です」で済まさずに「ご提案の通りで結構です」のように言えば、こちらの意図が伝わりやすい。
「説明」にしても相手がこちらの説明を聞く目的は何かを考えておくことが重要だ。「わかってもらう」主体は話し手側ではなく、相手側であることがここでも押さえるべきポイントになる。
意見がかみ合わないとき、条件文で述べてみると、少し中立的に眺めることができるといった細かいテクニックも随所に出てくる。「意図を明確に伝えつつも、柔らかい表現」を見つけたら、できるだけメモするといった自身の普段の行動にも触れており、「わかってもらう」を磨くのに参考になるだろう。
「7月の発売だが、じわじわと売れていて、伸びてきている」とビジネス書を担当する神園智也さんは話す。「わかってもらう」はビジネスを含め、社会的に活動するときに欠かせないコミュニケーションスキルだけに気になるビジネスパーソンが多そうだ。
2位に『若者が去っていく職場』
それでは、先週のランキングを見ていこう。
1位は「いきり」という観点から最近の様々な言動や現象を論評した本。様々な雑誌などで時事評論的な連載を多く持つフリーライターが著者だ。若者の離職の本音に迫ったキャリアコンサルタントの本が2位に入った。今回紹介した『「わかってもらう」ということ』は3位だった。
4位は8月の本欄の記事〈クイズノック流「独自性のつくり方」 自己満足をつなげて他人にシェアする〉で紹介した自己啓発本、5位は地方の山の上にパンと日用品の店を開いて人気店にした女性が、自らのビジネスの軌跡と考え方を書き留めた2023年刊の本だった。
(水柿武志)