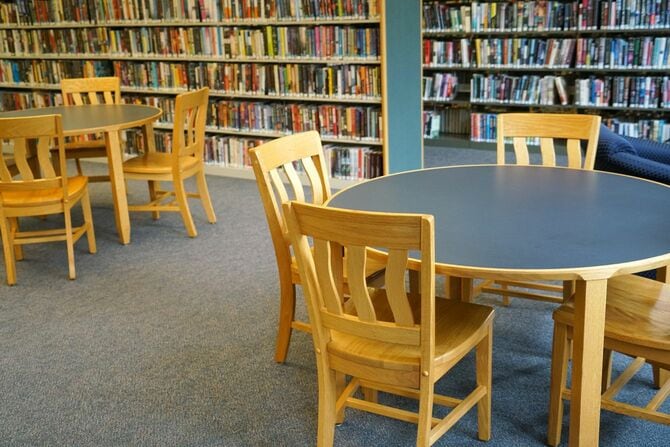※本稿は、堂本かおる『絵本戦争 禁書されるアメリカの未来』(太田出版)の一部を再編集したものです。
絵本や児童書が「禁書」されるアメリカ
いまアメリカ各地で、数々の絵本が禁書となっている。
アメリカの非営利団体「ペン・アメリカ」の調べによると、2023-2024学校年度に4000冊を超える本が禁書となっている。禁書の対象となっているのはヤングアダルト(以下、YA)と呼ばれる若者向けの書籍と絵本を含む児童書であり、少数ながら中高生も読む成人向けの小説も含まれている。
もっとも頻繁に禁書とされる本には、ピューリッツァー賞受賞の黒人女性作家トニ・モリスンの小説『青い眼が欲しい』、ジャーナリスト/ゲイ権利の活動家ジョージ・M・ジョンソンが若者に向けて書いた自伝『All Boys Aren’t Blue』(すべての少年がブルーではない)、オス同士のペンギン・カップルがヒナを子育てした実話に基づく絵本『タンタンタンゴはパパふたり』(ジャスティン・リチャードソン&ピーター・パーネル著)などがある。いずれもベストセラー、またはロングセラーとなっている作品だ。
当初は「黒人史」に関する本がターゲット
2021年に突如として出現した禁書推進グループは「親の権利」というフレーズを多用する。自分の子どもが何を学ぶかは政府や学校ではなく、親に決定権があるとする主張だ。このフレーズは、コロナ禍にマスク着用および学校閉鎖への反対派が使い始めたものだった。彼らはコロナ禍をきっかけに、学校でどのような教材が使用されているのかに関心を持つようになったと言う。
同時期、ニューヨーク・タイムズ・マガジンが2019年に発表した「1619プロジェクト」が議論を巻き起こしていた。奴隷制から始まるアメリカ黒人史を編纂へんさんした同作が高校のカリキュラムに取り入れられたことに対して、保守派が猛烈に反発したのだ。
さらに2020年に起きた黒人男性ジョージ・フロイドが白人警官に殺害された事件をきっかけに、Black Lives Matterが全米にとどまらず世界各地に広がっていった。保守派の白人は黒人の自己表明の勢いにおののき、自身の優越性と既得権の保持に傾いた。こうした流れから、禁書推進グループは当初、黒人史をテーマとする本を禁書のターゲットとしていた。