提供:日鉄興和不動産
“サステナブル”や“SDGs”という言葉は、いまや多くの人にとって耳慣れたものになってきました。けれど、その概念は、実際の暮らしの中に、どれだけ根づいているのでしょうか。
2023年秋、電通が行った「生活者のサステナブルアクション調査」(2003年9月実施/対象は、15〜79歳の男女1400名)によると、「サステナビリティに配慮した生活をしたい」と思っている人は約49.1%。けれど、実際にそれを「できている」と答えた人は、42.1%にとどまりました。
日々の暮らしにアクションを取り入れたいと思いながらも、行動にまでは移せていない人は、少なくありません。この“意識と行動のギャップ”を埋めるために、日鉄興和不動産はこれまでも、生活者の目線に立ったさまざまな取り組みを続けてきました。
そこで今回は、6月にオープンしたばかりの“サステナブルな体験型施設”に込められた想いや、その背景をお届けします。
身近な人からの影響が、行動を促す力に
2024年、シングルライフをより豊かにする暮らしのヒントを届ける、日鉄興和不動産の取り組み「+ONE LIFE LAB」が主導となり、サステナブルな生活に関心の高いFRaU SDGs会員を対象としたワークショップを開催。
「サステナブルな暮らしを日常生活に落とし込むには、なにが必要か?」という問いを起点に開かれたこのワークショップでは、すでにアクションを取り入れているというFRaU SDGs会員らの“行動動機”や“意識しはじめたきっかけ”などのリアルな実体験から、“意識と行動の間に生まれるギャップ”の原因、そしてその解決策を一緒に探りました。

このワークショップでは、サステナブルな暮らしについて、参加者それぞれのリアルな実践や価値観を深掘りするために、3つの議題を設けました。
1 家庭で取り入れている、サステナブルな行動やライフスタイル
2 暮らしや価値観が変わったきっかけ、印象に残っているモノ・コト
3 理想の暮らしかたと、そこに至るうえで感じている住まいの不満や要望
これらのテーマをもとに、ディスカッションを重ねながら、“自分ごと”としてのサステナビリティや、行動の背景にある気づきを、一つひとつ言葉にし、見える化しました。
「参加者から多く挙がったのは、『行動に移せたきっかけは、身近な誰かの存在だった』という声でした。たとえば、子どもの存在が行動を後押ししたという人もいれば、仲のいい友人から教えてもらったことが、自然と暮らしの中に定着したという人も。サステナブルという言葉のイメージだけでは動けなくても、実生活に取り入れてみて、自分自身が“心地よさ”や“メリット”を感じたとき、それがはじめて“自分ごと”として腑に落ちるのだと思います。社会のため、環境のためという大きな視点だけではなく、自分自身にもメリットがあると実感できたとき、人はサステナブルな行動を、自然と日常に取り入れられるのかもしれません」(日鉄興和不動産 山本瑞生さん)

ワークショップを通じて見えてきたのは、サステナブルな行動を〝自分ごと〟として根づかせるため必要な、いくつかの要素。「身近さや手軽さがあることで、人は行動に移しやすくなる」「あえて少し手間をかけることで、モノや体験に愛着が生まれ、それが継続のモチベーションにもつながっていく」ということ。また、興味のあるジャンルと結びついていたり、家族や友人といった身近な存在からの影響を受けているケースも多く、誰かに“語りたくなる”体験”が、新たな行動を生むきっかけにもなっていました。
誰かに伝えたくなる、新感覚の宿泊施設
こうしたリアルな視点を踏まえ、日鉄興和不動産は、2025年6月、東京都目黒区にある環境配慮型木造賃貸マンション「リビオメゾン大岡山」の一室を活用した、サステナブルを体験する無料宿泊施設「BOOK HOTEL 物々語」をオープン。部屋に置かれているのは、すべて中古の家具や雑貨たち。「中古品の再利用」も立派なサステナブルアクション。そんな視点から、中古品に触れてもらうことで、「モノを大切に扱い、不要になったら誰かに手渡していく」という豊かさを、さり気なく伝えていくユニークなコンセプトです。

「サステナブルなアクションを『やったほうがいいのは分かっているけれど、正直めんどうくさい』そんな本音を抱えながら、日々の暮らしのなかで“できていない”ことに、どこか後ろめたさを感じている人もいるかもしれません。サステナブルは大切。でも、それって頑張ることなのでしょうか? 私たちが目指したのは、そんな“できない気持ち”に寄り添いながら、無理のないかたちで行動につながる〝頑張らないサステナブル〟の提案です」(山本さん)
かつて誰かが大切にしていたモノには、その人なりの想いやストーリーが宿っています。その物語に触れ、共感することで、“誰かの中古品”が価値あるものとして受け取られていく。
「使い終わったら捨てるのではなく、次の誰かへ手渡していく。そんな意識の連鎖こそが、自然体のままでできる、サステナブルのひとつのかたちなのです」(山本さん)

また、部屋に置かれた備品のうち10点には、特別な背景があると言います。「大切だったけれど、手放すときが来たもの」をテーマに、10名の作家が、実際に思い入れのある品物と、その物語を寄稿。それぞれのストーリーは、ZINE(小冊子)にまとめられ、滞在中、手にとって読むことができます。

そして、何よりも心をつかまれるのが、この体験が宿泊料無料であるということ。その背景には、ただ泊まるだけでは終わらせない、想いが込められています。
「お金をいただく代わりに、宿泊者の『大切だったけれど、手放すときが来たもの』にまつわる物語を、部屋に置いてあるノートにしたためていただきます。自身の気持ちをアウトプットすることで、誰かに話したくなるのではないかと考えました」(山本さん)
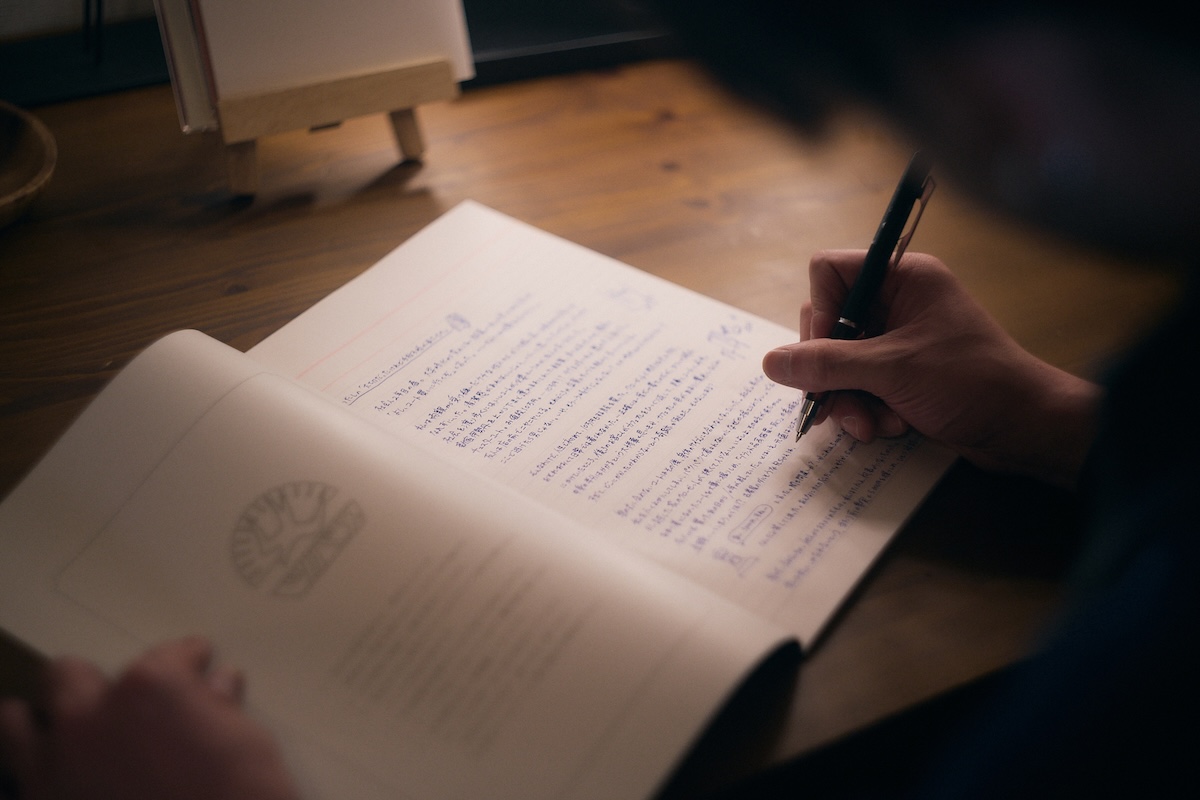
この体験から得た気づきが、宿泊者本人だけでなく、その人のまわりにも広がっていってほしい。そんな想いから生まれた今回のプロジェクト。いちばんの魅力は、「誰かに話したくなる仕掛け」。誰かに伝えること。それは、もっとも自然にできるサステナブルアクションのひとつだと言います。
「もちろん泊まっていただくだけでも十分です。けれど、できるならば、宿泊体験から得た気づきや想いを、誰かに伝えていただきたいですね。ワークショップ参加者の中でも、『行動に移せたきっかけは、身近な誰かの存在だった』という声がいちばん多かったですし、たとえば、『あの宿に泊まってから、自分も使わなくなったものを人に譲ってみたんだ』とか、そんな自然な行動の変化が、次の誰かの気づきや行動につながっていく。そんな連鎖が生まれたら、すごくうれしいです」(山本さん)
今回の拠点となった「リビオメゾン大岡山」は、同社にとって初となる木造の賃貸マンション。内外装にも木材をふんだんに使用し、自然を感じられる空間に。構造面でも、建設時の二酸化炭素排出量は、従来のコンクリート造に比べて40%以上も削減しています。
「正直、どれだけ環境配慮型の賃貸住宅を建てても、それを実際に借りて住んでいただける方との接点に限られてしまうんです。でも今回は、一般に開放するという形で、より多くの方と関われる。その中で生の声を聞かせてもらえるのは、私たちにとってもすごく貴重な機会なんです」(山本さん)
モノの循環、誰かのストーリーを受け取る体験を、楽しみながら味わえる「BOOK HOTEL 物々語」。ただ宿泊するだけではなく、誰かの想いに触れることで、サステナブルな価値観を〝実感〟として持ち帰る。ここには、そんな新しい宿泊のかたちがあります。
宿泊にはオンライン面談が必要。予約に関しては、公式HPよりご確認ください。
<提供>
日鉄興和不動産
https://www.nskre.co.jp
本記事内画像/日鉄興和不動産提供 構成・文/大森奈奈

