【べらぼう】26回解説、ていの涙と歌麿の孤独――三人目の女の意味
日本橋に現れた“行方知れずの母”つよ。その堂々たる振る舞いに、驚きと戸惑いを隠せない蔦重。
しかしこの再会は、彼の“人たらし”としての本質や、母から受け継いだ商才のルーツを照らし出す重要な場面でもありました。
一方、ていは蔦重への想いを自覚しながらも、自分の平凡さに引け目を感じ始めます。
「吉原一の花魁のような女がふさわしい」という言葉の裏にあるのは、瀬川という存在の影。
そして蔦重は、「たった一人の女房」としてていを選ぶ――その告白に込められた真意とは。
さらに静かに涙を流す歌麿の姿が、視聴者に深い余韻を残します。
「生まれ変わるなら女がいい」と語った彼の切なる孤独と承認欲求。
“片想いの終わり”とも言えるその心情の変化が、じんわりと胸に沁みていきます。
そして物語のラストでは、江戸城の政治の場へと視点が移り、田沼親子を巡る不穏な空気が漂い始めます。
この回は、「家族」「承認」「別れ」「再生」というテーマが複層的に描かれた濃密なエピソードでした。
視聴者それぞれが、誰かの立場に自分を重ねたのではないでしょうか。
#ドラマ
#ドラマ感想
#べらぼう
今更何しに来上がった? おっかさんに食わせる飯は一前もないと いうのかい?あんた鬼かい。 物語の冒頭米騒動の夜派で価格が乱光下げ する中、津は日本橋で客に飯を振る舞い なんとか商売をついでいました。 そんな混乱のさ中に現れたのが幼い頃に利 し行方シれずだった母強 驚きと共にその場面に移し出されたのは 彼女が自然とその空間に溶け込み客の1人 としていっているという異様な馴染み方 でした。ここでの強の姿勢は許しをこう母 ではなく勝って知ったる顔でやってきた女 。この大胆那道場が視聴者に強烈な印象を 残します。この母のキャラクターを見て 改めて浮き彫りになるのがスタジュの天生 の人たらしという支出のルーツでしょう。 どれだけ衝突した相手とも最終的には心を 通わせてしまうその才能。それはスタジュ 自身の努力や才能によるものとされてき ましたが、このエピソードによってそれは 母りではないかという別の可能性が定示さ れます。 まるで自分を鏡に移したかのような強の 表評とした言動と身のこなしは見るものに やはり親子だと納得させる説得力を持って いました。 一方でこの再会における中の内面は複雑 です。 ツタジュの表情は喜びとも怒りともつか ない揺れく感情を叩いていました。捨て られた子供としての過去と商人として成功 した現在の自分その間で揺れるの葛藤が 言葉少な演出によって丁寧に表現されてい ます。母の存在を前に強がりながらもどこ か甘えたい、認められたいという未償化の 感情が滲みれていました。 さらに注目すべきは強が見せる詳細です。 強は紙ゆいの技を生かし長旅で乱れた紙を 整えながら高道の商品である西や気病子を 客に進めていきます。 スタジとは違った視点で顧客のついで買 心理を尽く手法を展開する様子は女性の 生活感と観察癌が生きた場面と言える でしょう。 これは江戸という都市における秋内の多様 性を象徴するシーンでもあります。男の 理屈ではなく女の感覚で動く商売の強さが 描かれているのです。 ツタ重のなるへそという一言には強の詳細 に対する瞬時の理解と無言の経緯が込め られていたように感じます。 この場面単に母のアイデアに乗ったという 描写にとまらず、スタジオの中で親を 超えるものとしての自服と親に学ぶものと しての柔軟さが共存していたことを示して いました。そしてスタジはその場の空気を 読み取りながら西へ西郎名君実質集を 切り口に関連作品を次々と紹介していき ます。 ここで特筆すべきは津中の語りが単なる 商品紹介ではなかったという点です。本が 生まれた背景、その時代の空気、作り手の 情熱までも言葉に乗せ、まるで客の目の前 に物語の舞台を立ち上げていくような熱量 がありました。それは視聴者にとっても これまでのツタ中の歩みを振り返る時間と なり、ツタ中が何を背負い、どこを目指し てきたのかを再確認させるきっかけとなっ たのです。そんなツ重の姿に手の目が 明らかに変わっていく描写も印象深いもの でした。 商売のパートナーとして並び立つ関係に あった2人。しかしこの時の手のマ差しに は尊敬と戸惑い。そして淡い連母が 入り混じった複雑な感情が浮かんでいまし た。どんな窮地でもカ路を見出し、情熱を 燃やしながら人を引きつけていくつ重の姿 に手は引かれずにはいられなかったのです 。同時に手は自身の平凡さに気づかされて もいました。 誰よりも華やかで江戸市1の目聞きと消さ れる男の隣に立つには自分のような目立た ない女では力不足ではないか。その思いは 例えば吉原1のおイらを晴れるようなそう いうお方がふさわしいと存じますという天 の口から漏れた言葉に痛いほどに滲んでい ました。 このセリフの背景には視聴者がすぐに早起 するであろうセ川の存在があります。視聴 者もまたの言葉と共にかつて瀬川と中が 交わした約束を思い出さずにはいられ なかったことでしょう。 手は知らないのです。セ川がまさに吉原地 の大イだったこと。 その華やかさゆえに並び立つことができず 、互いの未来を託す形で別れを選んだこと を。 そして今が日本橋で挑んでいる新しい本屋 の形は瀬川から託された夢の続きでもある ということを。このエピソードは一見する と低の劣等感や恋心に焦点が当たっている ようでいて実は銃がどういう過去を経て今 に至っているかという物語の真を支える会 でもあります。セ川の夢を受け継ぎ天の 支えを受けながらスタジは過去を抱えた まま未来を切り開いていく。 そこには人との出会いと別れが1人の人生 をどう形作っていくかというドラマ全体を 貫くテーマが濃縮されていました。一方の 手もまた出会った頃とは全く異なる表情を 見せています。かつては冷静な経営者とし てスタを支える立場に手していた彼女が今 は自分の弱さをようやく言葉にできるよう になった。 中の真っすぐな思いに答えようとする一方 で自分がその隣に立って良いのか その葛藤と躊躇が彼女の表情の奥に 見え隠れしていました。 ツタが俺が俺のためだけにめ聞きした俺の たった1人の尿房と言いきる場面は感情の 集約点とも言える名シンでした。 ここでの目聞きという言葉はこれまで本や 人材に対して使ってきたツ重の職業的な 武器でしたが、今回は人生の伴侶という 私的な対象に向けられている。その語り口 からは底を商売の相棒ではなく、生きる 相手として見始めた心の変化がにみ出れて います。 興味深いのはこれまで何かと女心に疎いと されてきたツタジュがここに来てようやく 人の気持ちに向き合い寄り添うとする姿勢 を見せている点です。かつてのベラボな 鈍感さが嘘のように真剣なしで手の心を 見つめ言葉を選び気持ちを伝えるその定年 さに彼自身の成長がはっきりと移し出され ていました。 とが仕事の相棒を超えて心の奥底で 結びついた瞬間、その温かさに包まれた夜 、画面の片隅でポツンと涙を流す歌まの姿 は視聴者の胸に静かな痛みを残しました。 良かったな。 良かった という言葉には祝福と共に自分自身を 見失いそうになるほどの寂しさが滲んでい たように思います。 タイトルにあった3人目の女はまさにこの 時の歌ま自身なのではないでしょうか。 生まれ変わるなら女がいい特地にしていた 彼の言葉がただのザれ事ではなく深い孤独 と証人欲求の裏返しだったことがこの場面 によってはっきりと浮かび上がってきます 。 かつての傍原にいたのは自分だった。作品 においても生活の場でもどこへ行くにも 一緒だった。 しかし、今スタジュの隣には母強、そして 妻が自然に座っている。 それは歌まにとって居場所を奪われた感覚 に等しかったのではないでしょうか。 津田がたった1人の母親、たった1人の 尿房と語るたびに自分は本当の家族では ないのだと突きつけられる。隠滅町上の弟 という立場がただの仮染めでしかないと いう現実が心に冷たくいていたように感じ られます。もう俺いなくてもこの店回るし という拗ねた言葉の裏には子供のような 不安と承認欲求が見え隠れしています。 自分は大勢の方向人の1人に過ぎなくなっ たのではないか。 そう感じた瞬間、彼の中にはスタジュから の特別な何かを求める気持ちが再び目を 出していたのでしょう。もちろんツタジュ にとって歌まは買の効かない存在です。 歌まの才能を信じ、日本橋という新たな地 でも勝ち目として頼っています。しかし、 それは仕事上の評価に過ぎず、歌まが本当 に欲しかったのはツタにとってのたった 1人の存在になることだったのかもしれ ません。女性たちが自然に得ていったその 位置にどうしても手が届かなかった。 そのもかしさが彼のまざしにはにんでい ました。 正月の宿を込めて書いた金ンピラ子供遊び の中で歌まは歌ま文人千王女と名を記し ました。 つ中にどうしてと尋ねられた時の返答 にも売れてる感じでめでたくね。俺に弟子 がいるってさ。 それは明るく軽く見せかけた答えでしたが 、その裏には切実な願いがあったと考える べきでしょう。 弟子という存在を持つことで自分自身の 存在意義を確かめたかったのか、あるいは 女になりたかった自分と決別するための 儀式だったのか。それともその名前を作品 に刻むことで自分がつをしってきた証を この世に残そうとしたのか。 どの解釈にも深く心を揺さぶる力があり ます。 ここに描かれているのは片思いの終わり です。恋愛ではなく憧れと依存の 入り混じった特別な感情の整理。その過程 で歌まが親離れをしようとしていることが 静かに伝わってきます。 それは事実というよりもようやく自分だけ の道を歩こうとする決意のようにも感じ られました。そして視線はやがて江戸町へ と移ります。 田沼を置き継ぐ沖友の親子を見つめる佐野 正子と松井博そして背後には松道 さらに1つ橋春田までもが登場。 春サ田の笑に漂う不穏な要因が田沼家の 育末に影を落とします。 政治の世界にも家族を巡る思惑と決断の波 が押し寄せているのです。 めでたいめでたいと書いて願いを込めても 歴史の流れは容赦なく人々を試してくる。 そんな予感に満ちた会でした。 次回何が壊れ、何が残るのか。 その問が見るものの心をざずつかせたまま 物語は事象へと進んでいきます。 最後までご視聴いただきありがとうござい ました。コメントを残してくれると嬉しい です。チャンネル登録、高評価もお願いし ます。 またよければチャンネルメンバーになって いただけると大変公栄です。是非とも応援 をお願いいたします。

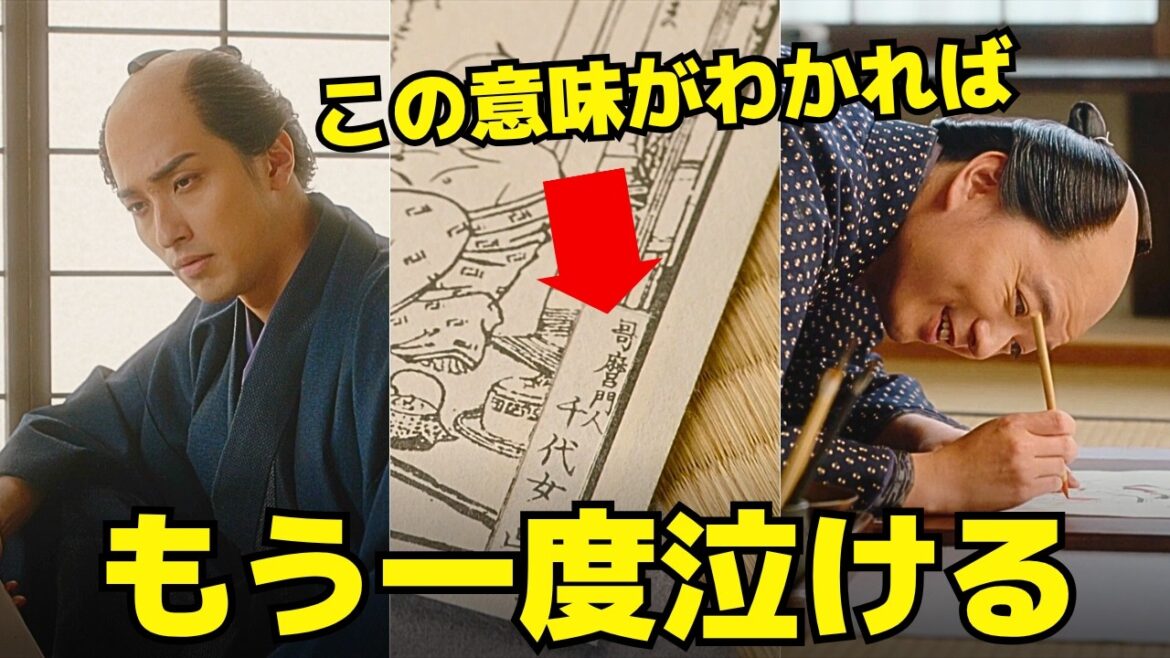
6 Comments
お疲れ様です
誰のセリフなのか
キャストの写真が表示されるのは
とても分かりやすく
ありがたいです。
ただ今回から朗読の声と
背景の映像が変わってしまいましたね。
背景映像が絵と風景だけで
私はとても聞きやすく見やすく
お気に入りだったのですが
今回から朗読部分に全く関係ない
まして外国の映像が出てくるのは
申し訳ないですが
ちょっと残念です。
すみません。
三人目の女…誰だったんだ?
瀬川か? でも出番なかったし
と思ってたけど 千代女だったのか!
あざっす🙏
このイケメンウザイ
チャンネル登録させて頂きました😊
歌麿の気持ちをっじっくり解説していただき、ありがた山です。蔦重が瀬川に言った「俺がお前を幸せにしてえの」 もよかったけれど、「ていといっしょに歩いていきたい」はもっとよかった。若い時の勢いから出た言葉ではなく、人生経験を積み、人間的に成長した蔦重の言葉ですね。二人が結ばれて喜んだ直後の歌麿の涙で一挙に頭が冷えてしまいました。二人と歌麿の間にふすま1枚、日本家屋の構造は残酷ですね。
そういえば歌麿はかつて蔦重から、自分のために生きてくれといわれていました。 これからは、蔦重のためだけではなく、自分のために描く絵を開拓していくのでしょう。