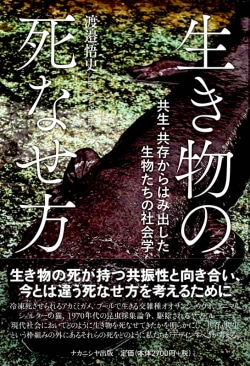社会と死の関係性問う
食卓に供された「刺身」を前に「死体を切り刻んだもの」と、静かに口にしてみる。すると、私たちが生き物の「死なせ方」に関与しているという問題が俎(そ)上(じょう)に載ってくるだろう。料理人は、魚の死体を一時的に「刺身」へと変容させ、美的・感覚的に整えることでデザインしている。本書は、死および死体と社会の関係性を問う「死体社会学」の独創的な試みである。
死や死体は、単なる静的な事実や存在ではなく、感情を誘発し、行為を引き起こす「共振性」を有する。ゆえに、それらは演出され、戦略化され、可視化され、消費の対象となる。著者はこの過程を「死政治」と規定し、特定の生き物を「死なせる」過程では、戦略や手管に情念が絡み合い、複雑に操作されていると喝破する。
一九七〇年代、昆虫採集が自然破壊だと批判されると、擁護派は動揺し、批判感情の広がりを抑えようとした。保全政策により廃校のプールに隔離された交雑オオサンショウウオの死体は、非難を回避すべく人目を避けて埋められる。アニマルシェルターへの共感と寄付を喚起する目的で、高齢の野良猫の死と供養がSNS上で可視化される。「害虫」のヤマビル採りでは薬剤を用いず、瓶に塩漬けして殺すという手応えが重視され、加害と被害の境界は曖昧になる。
本書の核心には、死や死体が能動性をもって「行為する」という逆説的で不穏な命題がある。死体が感情や実践と結びついて、共振を引き起こすきっかけになるという視点は、私たちがいろんな意味を込めて生き物を「死なせて」いることに無自覚であることを浮かび上がらせる。著者は、死が折り重なっていく過程を「歴史」と見なすダナ・ハラウェイに拠(よ)りつつ、現代における生き物と死の錯(さく)綜(そう)した関係を読み解く。
他の生き物といかに共生すべきかを問う前に、いかにしてそれらを「死なせて」きたのかを検討する必要がある。著者は、その重く深遠な入口を、静かに、しかし力強く開いてみせる。(ナカニシヤ出版、2970円)