今回、徳力氏が対談したのは、GoogleにてYouTubeの音楽部門を牽引する佐々木舞氏と鬼頭武也氏。世界最大の動画共有プラットフォームであるYouTubeにおいて、音楽コンテンツがどのように視聴され、アーティストとファンはどうつながっているのか。
後編は、YouTubeが企画運営に深く関わる音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」に注目。今年初開催で、幅広い分野の音楽関係者で構成される5,000名以上のメンバーの投票により、受賞作品/アーティストが決定する。5月16日から22日の7日間にわたってオンライン・オフラインで様々なイベントを開催し、最終日に行われる授賞式はYouTubeでライブ配信される。YouTube Musicチームが本アワードに込めた、日本の音楽業界への思いとは。
インタビューを受けてくださった佐々木舞さんは、本インタビューの後に急逝されました。本稿は佐々木さんが生前に語られた内容に基づくものです。謹んでご冥福をお祈りします。
初開催の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」とは
徳力 僕が個人的にも注目している、今年初開催の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。企画運営にはYouTubeが深く関わっていると伺いました。授賞式の模様は、NHKで中継すると同時にYouTubeでも全編配信されると聞いて驚きました。YouTubeさんが参画するに至るまでに、どのような経緯があったのでしょうか。
鬼頭 MUSIC AWARDS JAPANをご支援いただいている文化庁長官・都倉俊一さんと私たちYouTubeは、このアワードの話が持ち上がる前から長くお話しをさせていただいてきました。都倉さんは過去に、YouTubeが強いパートナーシップを築いている日本音楽著作権協会(JASRAC)の理事長もされていました。JASRAC前理事長の方から紹介いただき、今から5年ほど前、文化庁長官に就任される前に初めてお目にかかりました。
作曲家でもいらっしゃる都倉さんは「日本の音楽を海外に出していきたい。そのために、一人の作家として、YouTubeの活用法を教えて欲しい」と相談いただく中で、徐々にアワードの話を伺う機会が増え、Global Streaming Partnerとして参画するに至りました。「YouTubeを活用して日本の音楽を海外に出していく」というコンセプトがあっての、MUSIC AWARDS JAPANの立ち上げだったと思います。
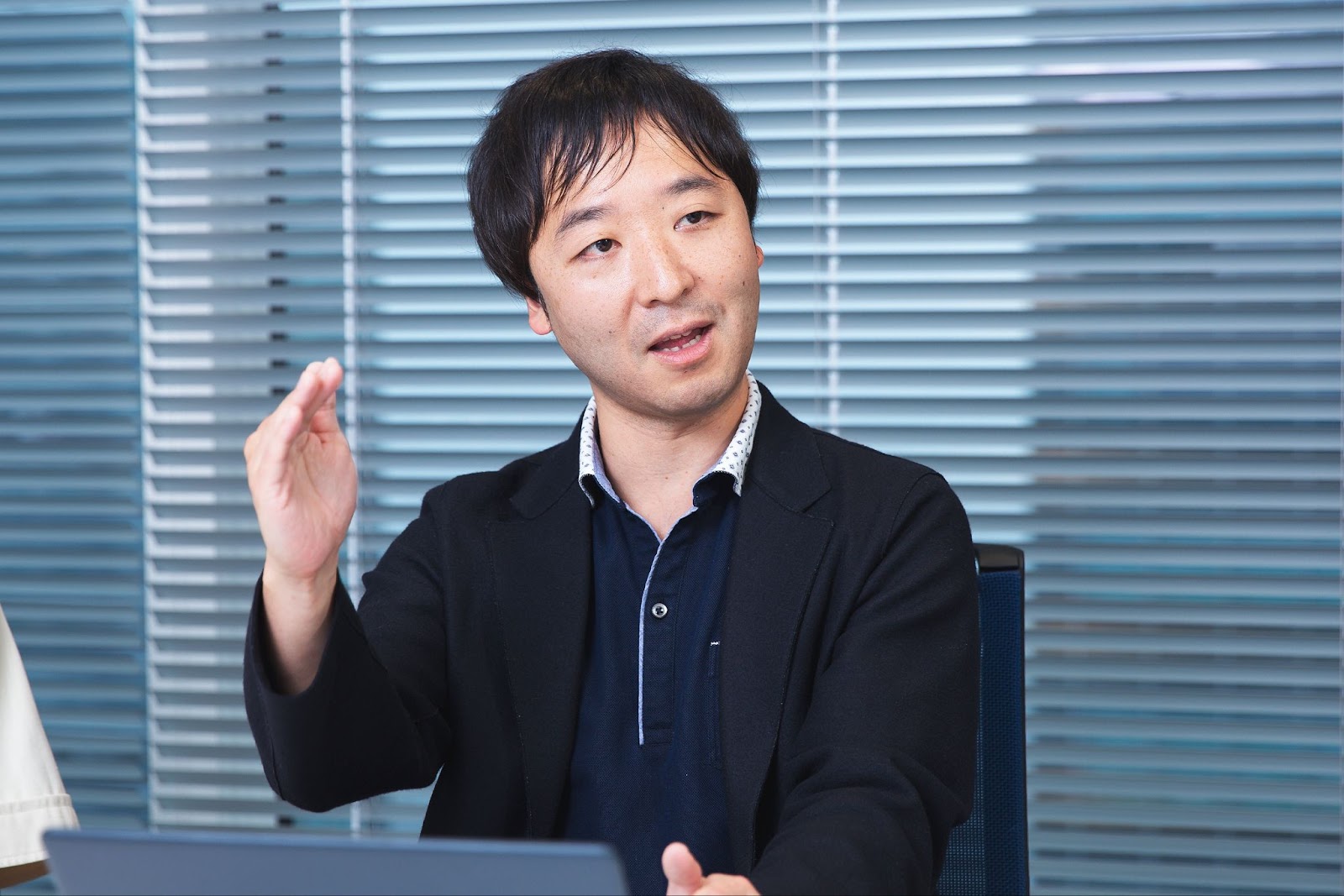
YouTube Music Content Partnership, Director 鬼頭武也氏
NTTコミュニケーションズ、ユニバーサル ミュージック、レコチョクにてデジタル音楽配信の事業・サービス開発経験を経て2015年、Google入社。現在はYouTubeの日本、東南アジア、豪州、ニュージーランドにおける音楽レーベル・アーティストとのリレーションシップの責任者を務める。
佐々木 MUSIC AWARDS JAPANを主催するCEIPA(一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)理事長の村松俊亮さんとも、早い段階からお話しさせていただく機会がありました。YOASOBIやCreepy Nutsが海外で大きな注目を集めたことはYouTubeの存在が大きかったと認識してくださっていて、コロナ禍を経て「日本の音楽を世界に届けていきたい」という思いがより高まったタイミングで、YouTubeと連携していきたいと声をかけていただきました。
日本を海外へ発信するのではなく、日本と海外を交わらせる仕掛け
徳力 YouTubeは「コーチェラ・フェスティバル(以下、コーチェラ)」のような音楽フェスのライブ配信であったり、さまざまなグローバルのアワードの中継でも存在感を増していて、YouTubeライブでの中継自体は当たり前になっています。なかでもMUSIC AWARDS JAPANに関しては特に、世界からの視聴者数を増やすため、御社も企画運営に入り込んでいるということですよね。
鬼頭 はい。佐々木と私が実行委員会のメンバーとして参加させていただいてます。

YouTube Music Artist Relations 佐々木舞氏
東芝EMIでのプロモーター、米国音楽アグリゲーターIODAでのビジネスデベロップメントの経験を経て、2011年からGoogle のYouTube チームに参加。現在日本のYouTube のアーティストリレーションズ担当として、アーティストのチャンネル活用による国内外でのヒット創出のサポートを行う。
徳力 僕が勝手に心配しているのは、「日本の音楽を世界へ」と言って開催するんだけれども、結局見ているのは日本人ばかりだった…というパターンにならないかということなんです。そこはYouTubeさんが頑張っていただけるということで良いのでしょうか?
佐々木 もちろん頑張ります(笑)。MUSIC AWARDS JAPANには、授賞式の配信以外にも様々な関わり方をさせていただいています。アワードの前の週末に「YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN」と題して、ノミネートされた日本やアジアのアーティストのパフォーマンスをプレミア公開したり、そのアーティストのプレイリストをニューヨークやロサンゼルスの屋外広告で配信したり、YouTubeのグローバルのソーシャルアカウントで発信したり。前段階からしっかり盛り上げて、授賞式の配信に持っていこうと考えています。
徳力 YouTubeライブで配信するだけではないのですよね。単に日本の音楽賞が「海外向けです!」と言ってYouTubeライブを使ったところで、誰にも届かないんじゃないかと心配していたんです。SNSアカウントで発信したり、グローバルのユーザーが興味を持ちそうなコンテンツを用意したり。そういう細かい動線づくりも大事になってきますね。
鬼頭 そうですね。やはり気付いていただかないとなかなか見ていただけないので、しっかり面を押さえていきます。「日本の音楽を世界へ」というと、エクスポートすることばかりを狙いがちになるのですが、今回はそうではなく、MUSIC AWARDS JAPANを通じて、日本の音楽業界が海外の音楽業界やアワードと連携・交流することを重視したいと考えています。
徳力 確かに、MUSIC AWARDS JAPANは、「BEST SONG ASIA」(アジアでヒットしたアジア楽曲を讃える部門)の設置など、グローバルアワードを意識したつくりになっていますよね。単純な日本の音楽の“宣伝”に終始しない工夫がなされていると感じます。
鬼頭 佐々木が申し上げたYouTube Music Weekendにしても、MUSIC AWARDS JAPANにしても、日本とグローバルのつながり・交わりを演出できるのは、YouTubeならではのサポートなのではないかと自負しています。
徳力 YouTubeやSpotifyによる告知の効果もあり、USENの音楽リクエスト投票サービス「推し活リクエスト(推しリク)」がアジアで話題になっているようです。フィリピンのファンダムがかなりの数を投票して、SB19(エスビーナインティーン)というフィリピン出身のアーティストがランクインしていて、そのことに僕がnoteで言及したら「紹介してくれてありがとう!」とSNSでnoteをシェアしてくれたんです。音楽を通じた日本と海外の双方向コミュニケーションってこういうことか!と実感しました。
日本のアーティストがグローバルに知ってほしいと思うのと同様、アジアのアーティストも日本や世界に知ってもらいたいと思っているはず。YouTube Musicのチームは、初めから双方向コミュニケーションの意識を持たれていたんですね。
鬼頭 日本だけでなくアジア全域のメンバーでチームを構成できるのも、YouTubeならではではないかと感じています。
徳力 過去に宇多田ヒカルさんや安室奈美恵さんがアメリカに挑戦したものの苦戦していた様子をみて、「彼女たちでダメなら、日本の音楽はもう世界で通用しないだろう…」と諦めてしまっていたところがありました。でも気がついてみたら、アニメソングをはじめ日本の音楽は世界できちんと聴かれるようになっている。昨年、コーチェラの中継で、新しい学校のリーダーズさんやYOASOBIさんが世界の舞台で日本語で歌唱している観客を熱狂させている映像に、大きな衝撃を受けました。
YouTubeをはじめとするグローバルプラットフォームによってそれが可視化されるようになって、「音楽って、本当に国境や言語を超えるんだな」と実感できるようになりました。


WACOCA: People, Life, Style.