井上ひさしさんは生涯をかけて日本と日本語のことを考え続けた作家です。2001年、井上さんは母校の上智大学で日本語をテーマにした講演を4回行いました。やさしくて、おもしろくて、ふかい……そんな伝説の講義を完全再現した1冊、『日本語教室』の一部をご紹介します。
「カタカナ倒れ」でも「漢字倒れ」でもなく
今、日本語は「カタカナ倒れ」になりかかっています。グローバリゼーション、グローバリズムが、世界化とか地球化というふうに、すべて漢字になっていれば、まだ意味がわかるのですが、わかったつもりでグローバリズムとか、グローバリゼーションとか、そういう外来語を使ってものを考えていく。先ほどのメンテナンスとか、リフォームがいい例です。プロジェクトだって「計画」にすればいいと思うのです。つまり、日本語で考えないで、外来語で考えているうちに、再生、改良、仕立て直し、改築、増築、改装というような違いが消えてしまうわけです。そのうちに、大きな誤差が生まれてくるでしょう。いかに私たちが英語を勉強しても、アメリカ人、イギリス人のように英語で考えることはできません。ものをしっかり考えるためには、われわれが自覚しないうちに、脳の発達と同時に、脳の一部として繰り込んできた母語を土台に考えるしかないのです。ところが、そういう脳の発達する一番大事な小学校の頃から、第二言語を入れようとする動きがあります。それができる子どももいると思いますけど、そこまで日本はアメリカの属国化していいのか、という気がしないでもありません。
外来語、カタカナ言葉の氾濫は目に余りますが、一方に「漢字倒れ」というのもあります。たとえば、カンキ、という音。カンキと聞いて、みなさん何を思い浮かべますか。僕は、神吉拓郎といういい作家がいたな、亡くなってから何年になるかな、などと考えます。その場合、カンキという音を漢字が補完していくわけです。カンキと言う音の中に、「勘気」が解ける、今日は「寒気」が強い、「換気」装置、何かを呼び起こす意味の「喚起」もあれば、喜びの「歓喜」もあります。
それからショウカイ。「哨戒」艇、何とか「商会」、あの人を私に「紹介」してください、い、身元の「照会」、詳しく解釈するという意味の「詳解」もあります。
つまり、漢字があまりにも便利で、造語力がありますので、インテリたちが漢字をたくさん使って、どんどん言葉をつくっていった時代がありました。外来語でどんどん変な言葉をつくっていくJRみたいな人が、過去にもいたのです。そういう「漢字倒れ」にも気をつけなければなりません。特にワープロが使えるようになって、書けない字でも漢字に変換しますから、今、若い人の文章というのは、漢字の使い過ぎ、「漢字倒れ」になりかかっていますね。
キーワードは「カタカナ倒れ」と「漢字倒れ」です。程のいい漢字の量で、ひらがなとカタカナをきっちり使って、正確で奥行きの深い、そういう文章を書いたり読んだりするためには、どういうふうに考えればよいのか。私たちは、まさに今、そのことを問われているのです。
そこで、この講座の正体を明らかにしますと、考えられる限りの、一番読みやすく、書きやすく、正確で、しかも潤いがある、そういう日本語を見つけようというのが、われわれの―――急にわれわれになってごめんなさい、押しつけみたいで―――私の野望なのです。漢字が多すぎるのも不便です。だからといって漢字制限をするとか、そういうことではありません。
大江さんはすごい
では、現存の作家の中で、その理想に一番近い文章を書く人は誰だろう、という方向から考えることも可能だと思います。僕なら、やはり丸谷才一さんかなとか、大江健三郎さんはちょっと漢字の使いすぎかなとか、まあいろいろ……。僕が学生の頃に大江さんがデビューして、あまりに素晴らしいので、もう小説はこの人におまかせ、自分は他のことをやろうという、大江ショックというものがありました。大江さんはたとえば「書物たち」という具合に、初めて無機物にも「たち」をつけたりしました。それから、比喩がすごい。有名な例で言いますと、オチンチンが縮こんでる様子を、「性器はどこもかも縮みこんで脹(ふく)ら雀(すずめ)のように股座(またぐら)の屋根にちょこんととまっていた」という。「脹ら雀」って、なんだろうと思ったら、それがオチンチンのことなのです。それからセックスのことを「セクス」と、きれいに書いた人も大江さんですし、「灼熱(しゃくねつ)した鉄串(てつぐし)のような男根」とか、そういう比喩はそれまでなかったのです。
何からそういう話になったのかと言うと(笑)、つまり私たちは、いろいろなことをいっしょに考えながら、「漢字倒れ」にもならない、「カタカナ倒れ」にもならない、そして昔のものもちゃんと読める、子どもたちにも渡していける、きちんとした日本語の姿の見当をつけたい。それがわれわれの講座の目的です、ということを申し上げようとしていたのでした。

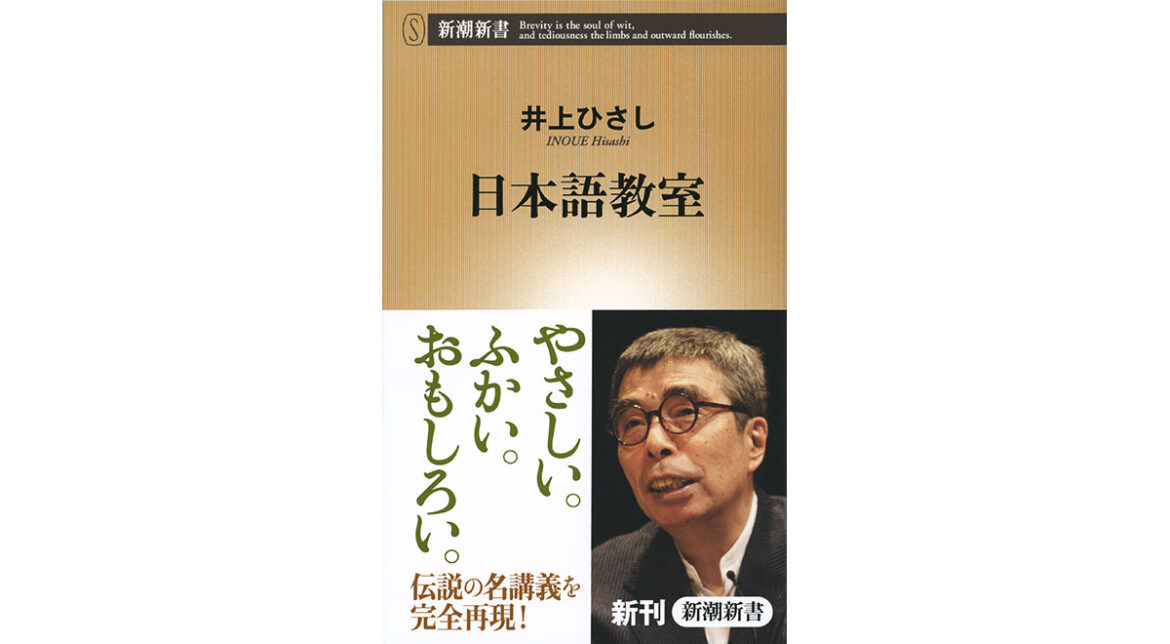
WACOCA: People, Life, Style.