1600年の関ヶ原の戦いの時に、
徳川家臣団はどこにいたのかという配置・所属について紹介していきたいと思います!
関ヶ原の戦いと言うからにはこの関ヶ原の地、
そして中山道を行く秀忠軍、
関東や東海各地に留守居役や守備隊として配置された家臣たちも多くおり、
今回は守備勢にも触れて徳川家臣団をできるだけ多く登場させたいと思います!
今回は相当数の家臣たちが出てきます!
最後までお付き合いいただけますと幸いです!
あなたはここにいたのですか!
と思うような配置もあったりします!
家康を三河時代から支える家臣たちにとっては、
最後の華々しい集大成!
そして秀忠、家光時代に幕閣において重きを成していく、
江戸時代の初期の歴史に名を残す人物たちの初陣であったりもします!
そんな時代の転換点となる戦いでの徳川家臣団の配置・所属を解説します!
#どうする家康
#徳川家康
#関ヶ原の戦い
#歴史
●画像引用
どうする家康公式HPより引用

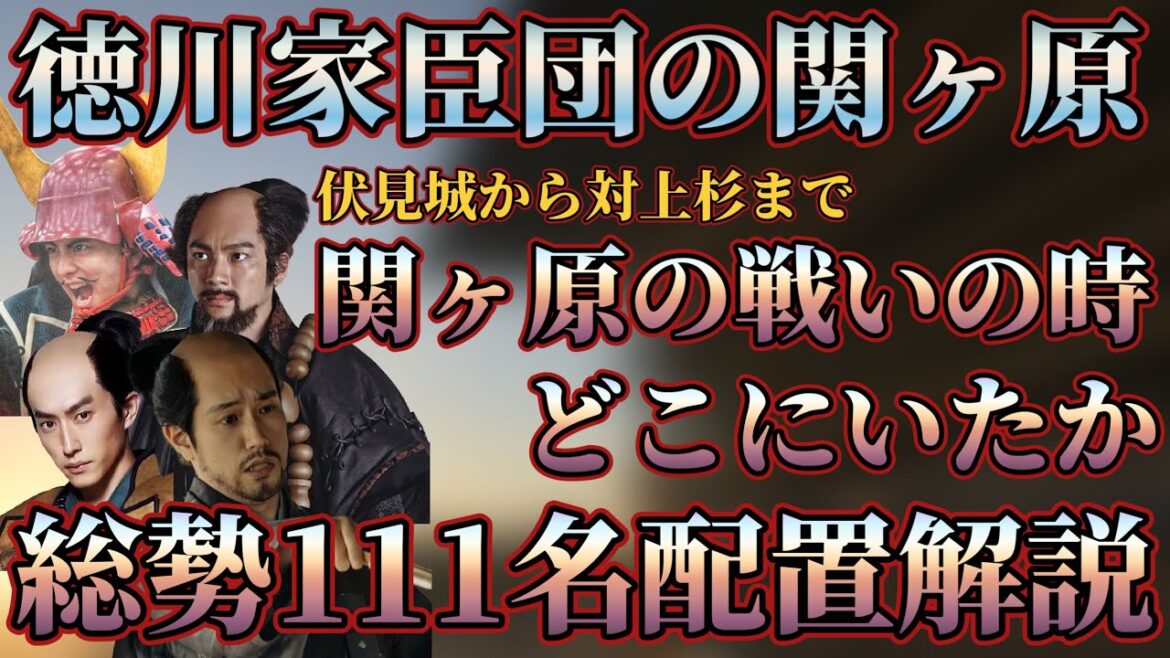
9 Comments
やすやすは何回聞いても笑う
毎回家系図書いてくれるのラスカル🦥
簡単にまとめた→知る限りこんなに人数まとめてる動画はないwww。充分詳しいですw
いやー、見応えありました!城を守るためにかなり多くの将たちを割いているのに驚きました。そんなこと考えたことなかったです!
今1番ハマってる小説「三河雑兵心得」(現在11巻)は渥美の架空の百姓が三河一向一揆の足軽として従軍して出世していく物語ですが、主人公の茂兵衛は松平康安の姉を嫁としてもらっており、今回名前が出てきて嬉しかったです。
茂兵衛は関東移封の際に3000石まで加増される大出世ぶりです^_^
早くて聞き漏らしがあったとは言え、今までになかった切り口で大変面白かったです
目の付け所がズレてますね。
旗本の先手は『せんて』ではなく『さきて』です
弓足軽、鉄砲足軽部隊で江戸時代は江戸城内、江戸市内の警備を担当しています
時代劇で有名な火付盗賊改は先手の隊長である先手頭(20人から30人いました)が兼務した役職です
江戸時代中期以降は本多や榊原家は名誉職的な地位にしか就けず酒井雅楽頭家、左衛門尉家と井伊家が老中、大老を輩出する徳川将軍家屈指の家柄になります
上屋敷が大手町にあった酒井両家の方が外桜田にあった井伊家より格上となります
上屋敷の場所は非常に意味があり大名小路(神田橋門から数寄屋橋門)にある家が最高ランク、日比谷門や数寄屋橋門外が次、神田橋門北、鍛冶橋や呉服橋門東はかなり格が下がります
いつも楽しく見させて頂いてます。相変わらず途中で訳がわからなくなるほどの資料をまとめてるのは凄いですね。しかし本当に家康は家臣に恵まれてますね。江戸幕府が出来たのもひとえにこの家臣達のおかげだと思います。最後の方で志村けんさんの名前が出て来るとは思いませんでした。今回もご苦労様でした。
とてもおもしろかった。四天王などの人物の配置は知られていますが、あちらこちらに家臣が配されていたのだと、また有名武将の親子、兄弟など総がかりで対戦に備えていたのだなぁと違う視点で見ることができます。それにしても本当にお疲れ様でした!時間かかったことでしょう。楽しかった♪