スウェーデンと日本の大きな違い、驚いたこと、学べると思ったこと、貴重な具体例もりだくさんのインタビュー。視察で来瑞中の子ども支援団体で活躍する西崎さんに聞きました。日々の家庭の子育てのヒントがつまってます。
これから日本もどんどん変わる!日本とスウェーデンの異なる「子供の権利」。11/20「世界こどもの日」にこそ考えたい、子供の権利の守り方。
【参考出典】
ユニセフ「子供の権利条約」
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
セーブザチルドレン
https://www.savechildren.or.jp/oyakonomikata/kodomo-no-kenri/
西崎さんの子育てインタビュー記事
東洋経済「教員の3割が子どもの権利の内容知らず~」
https://toyokeizai.net/articles/-/603587
東洋経済「日本の子供、幸福度調査世界ワースト2位~」
https://toyokeizai.net/articles/-/605674
【おすすめ動画】
スウェーデン保育#1:https://youtu.be/WDmSdtsD9yY
スウェーデン保育#2:https://youtu.be/ko_bfgJiy3E
日本が低い「世界幸福度ランキング」:https://youtu.be/R686TtCg1-8
北欧子育て:https://youtu.be/pBJe5hah_Rk
スウェーデンの学校びっくり:https://youtu.be/6RdzYi8A0t8
―――――――――――――――――――――――
※これからもどんどん更新していきます。チャンネル登録いただけたら励みになります。
【Who are you? 私たちはだれ?】
ノードラボ「北欧研究室」は北欧現地から直接お届けする、情報深掘りチャンネルです。さまざまなトピックをとりあげ、在住者の視点で深掘りしていきます。
●室長ヨウコ:スウェーデン在住歴16年。スウェーデン人の夫と二人の子供を持ち「ゆりかごから墓場まで」をリアルに体験中。2007年に北欧雑貨の雑貨輸出会社を起業。2018から北欧雑貨ショップ「ソピバ北欧」店長もやってます。
Clubhouseは @yoko.dah です。こちらもよろしく!
●研究員マホ:北欧在住歴3年。スウェーデン人との結婚を機に移住。スウェーデン企業でITコンサルタントとして働き、スウェーデンらしい社会でたくさんの発見をする日々。
―――――――――――――――――――――――
★室長ヨウコが運営する北欧雑貨ショップ★
ほんものの北欧が感じられる北欧雑貨をお買い物いただけます。
https://bit.ly/3bigijn
★Bon Aibonさんと作った北欧Fikaキットシリーズ↓
https://bit.ly/3xWIWQG
★YKRさんと作った、北欧白樺樹皮細工/ネーベルスロイド、手作りキットシリーズ↓
https://bit.ly/3bigxuN
★北欧雑貨卸専用の会員サイト(雑貨バイヤー様専用です):
https://ditt-datt.bcart.jp
___________________________________________________________________________
ソーシャルネットワークでも、北欧現地の生活の様子がわかる情報を発信中。
是非チェックしてみてくださいね。
Instagram : https://www.instagram.com/nord_labo/ (@nord_labo)
Facebook : https://www.facebook.com/nord.labo/ (@nord.labo)
Twitter:https://twitter.com/nord_labo (@nord_labo)
HP: https://nord-labo.com
お問合せ:info@nord-labo.com
___________________________________________________________________________

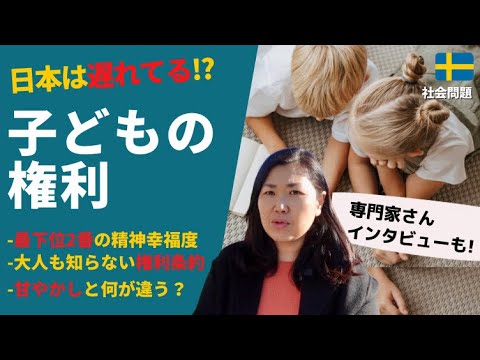
34 Comments
例えば幼い時に親が栄養がある「おやつ」を二つ出して子どもが選択する。図工のときに色紙を三色出して各自に選ばせるというような「選択肢」がある日常や、作られたおもちゃでない物で遊んで工夫する日常が必要だなと感じました。いつもの動画も楽しいけれど、今回も色々と考えさせられる内容をありがとうございました。
子供の権利以前の問題、夫婦が別の愛人問題で子供の面倒を見ない。ちょっとの隙に子供が思いも付かない行動をする。これは正規雇用者ならば危険予知訓練を身に付けているが、非正規雇用者はそのような訓練を受けていないと思われる。もう一つは画一性から外れたら虐めの問題が有リ同調圧力が強い。
これらを除けば世界は日本の人間形成教育システムを羨ましいと感じている。それには安全・安心・平和・秩序の社会が影響している。そしてアニメは世界の子供に魅了や共感を与えている。
欧州で子供に関わる仕事をしており、自身も小学生の子供がいるので今回の動画、大変興味がありました。日本では欧州一色多だと思いますが全然違うなと改めてかんじました。スウェーデン式子育て、子供との向き合い方などまたupして頂けると嬉しいです。
別の動画でフィンランド訪問後に戦争を経験した国は違うなとおっしゃっていましたがすごく気になってます。機会があればそのお話も聞きたいです。
お二人の動画、毎週とっても楽しみにしています✨
給食の話。私は、スウェーデンの市の学校給食で働いていますが、学校や幼稚園の給食職員からの提案で、時々、子供たちに食べたいものアンケートをとり、今週は子供の食べたいもの週間という感じで、上位の希望のメニューを出す週とかを時々設けています。
うちが中学生の頃は学食がa定食b定食どちらか選べました!ラーメンやデミオムライスも出ました!
とても美味しかったから食に関してはこだわっていたみたいだけれど、
家庭科は女子だけだったし、柔道は男子のみだった。
『子ども家庭庁』の存在自体が日本では大きな社会問題になっている旧統一教会が生み出したものです。
結果的に安倍元首相も旧統一教会の活動に加担したことによって命まで失ってしまいました。
この組織を日本人の民意とは考えにくいにせよ、次世代の納税者は守らねばなりません。
どうしたらいいのか、子ども食堂をはじめ、日本人はいま考えあぐねているのです。
旧統一教会が目指したものは旧来の家庭環境の遵守、LGBTや夫婦別姓や多様性の否定なのです。
また煽ってるし。もうスウェーデンが世界一嫌いな国になりました。
りんごとバナナの話で思い出したのは
ウチの二人の子供が小さい時に
朝ごはんを選ばせていた事。
ごはん?パン?おもち?と聞いていた。
将来、自分で色々選択していくであろう人生
人に任せず自分で決める練習をさせたかった。
義母には「甘やかしている」と言われたが
そんなこと知るか 笑
議論が出来て対応することが出来る。先生だけではくほぼ全ての教育者はファシリテーション出来ない。言動で影響を与えられるという希望は空気が消滅させている。空気は既得権益にある程度従うのでそれが変更されるまで継続的に続くのみ。既得権益に従うのは大人のわがままといつ気付くのだろうか。儒教文化が根強いのでそれを変えることが出来るように思えない。変えて頂けたら嬉しく思います。
ヨウコさんおすすめの羽毛布団の紹介して下さい😊
11月は、日本でも人権週間というものがありますよ。
わたしのかつての勤務地の小中学校では、人権について作文を書かせ、優秀者は市のホールで発表させていました。来場者は発表者の家族、市議会議員たちと、議員の関係する障害者団体の障害者さんたち(みなさんじっとしていられず、障害者の権利に反するような気がして毎年もやもやしていました)。来場者には、ボールペンやファイルなどを配っていました。
子どもたちが「こどもの権利条約」まで学んでいたら、こんな無意味な作文コンクールなんて話し合って撤廃させるはず。わたしは10年以上前に退職したのですが、今でも行われていてびっくりです。
権利が全然ない国が21世紀の今 現在ある。国民の当たり前の権利が保障されてるのは素晴らしい!
子育てだの住みやすさだの、与太話連中は治安をガン無視してて、「あー受けてる恩恵に気付けない可哀想な人たち」て感想。治安の良さは住みやすさや子育てしやすさに、なによりも重要なんだがね。
こども庁は作る前から失敗すると言われています。喫緊の課題は親による幼児虐待や無国籍児の問題です。小学校に行く年齢でも未就学児童がかなりいるとのことです。児童相談所が機能していなく虐待死が問題になっています。警察による救出と保護が効果的だと思います。日本の議員は自分の利益にならない事に積極的ではありません。
国が違えば子供の育て方も違うスウェーデンは本当に権利意識が強い国50年後スウェーデンの文化は ぼろぼろになっているね‼️それどころか国が有るか❓️。
スウェーデンの価値観を日本持ち込まないでください。スウェーデンの国は崩壊するよ‼️日本も社会崩壊しそうだけど どっちが早いか❓️。
なるほどーと思い見ていました☺️育ってきた過程がまず違い、社会環境も違いなかなか同じようには難しいですが、そういう考えもあるんだなぁと知ることができました😊北欧の教育方法は魅力的ですが、日本でも自発的に行動を起こしたり、自分で考える力や発言していく力もも持っていたりできる範囲で子供の力を伸ばせていけたらなぁと思いました🥰
子供に限らず他責にするやつが増えすぎて子供どころか大人も身動きできなやつが多すぎるだけやん
とても大切で示唆に飛んだ内容でした。
子供達の意思を尊重してあげられる教育の機会を増やしてあげたいですね。(*^^*)
子どもの権利に対しては,文科省も含めて日本の教育は消極的ですね。
道徳の教科書を見ても,子どもの権利を扱うときは必ず義務とセットです。
わたしから言わせたら,よほど子どもを信用していないんだと思います。
ちょっと飛躍しますが…
日本国民に浸透している家父長制の倫理観が,子どもの権利のみならず女性の権利,そしてジェンダーの問題まで影響を及ぼしていると思います。
こども家庭庁が話題になりましたが,子ども庁でなく子ども家庭庁になったことにも注視しなればならないと思います。
今,政権与党と世界平和統一家庭連合との関係が問題になっていますが,こども家庭庁になった経緯に家庭連合の働きかけがあったことが指摘されています。
選択的夫婦別姓制度を認めない政権与党と世界平和統一家庭連合との一致点が見え隠れします。
こども家庭庁が,子どもと家庭の在り方についてどんな政策を打ってくるのか。
逆に心配になってしまいます。
西崎さんのような方が影響力を持っていけるといいのですが…。
面白かったし早く日本の政治家が取り入れていってくれないかと思います。
以前、自治体のこどもの権利条例づくりに参加したことがありますが、教育現場の方々から、子どもの意見を聞いていたら、子どもが、わがままになる、といった意見が多く聞かれました。子どもの権利条約の理解と、動画でも言われていた枠組みづくりが大切だと思います。
日本の教育現場は忙しすぎて、子どもと対話する時間を作りにくいとも聞きます。
家庭の中で、できることからやっていきたいと思いました。
子どもの権利を尊重する大人になるために何ができるだろうか…と考えていたら、不意に個人的な経験が思い出されました。
もうン十年前、私が(日本の)公立中学で図書委員をやっていた時、顧問の先生が自分の趣味が偏ってることを理解されている方で、図書室に新しく納入する本を図書委員の生徒に7割くらい選ばせてくれてました。選び方も考えて良いと言われ、半分は自分たち図書委員が個人的に読みたい本、半分は3年生までの授業範囲から図書室に不足してると思う本を選んだ記憶があります。当然予算があるので、なぜこっちの本ではなくこっちの本を今回入れた方が良いのかなどを話し合って取捨選択していきました。今考えると、子どもにとって選択する自由は考える自由でもあるので、子どもの考えを尊重し良い機会を作ってくれた先生(大人)だったな、と思います。ただ、ある程度の個々の経験値があり、考えて意見を言える年齢での話なので、幼い子どもの場合では、大人側にある程度スキルが必要そうですね。
家庭庁ができることは今後に向けて必要だと思うのですが、日本では先ず公立学校を解体して、統率された中でもリベラルな学校を作ることから始めないと、さらにそれを指導できる教員を育てることから始めてベースを作らないと、学級崩壊しちゃう😅
日本は、リンゴとバナナを選ぶことをさせてあげられる保育園(保育士)からかなぁ。
大人も正直なところ、自分の1票や意見が政治参加しているって思っている人は少ないと思うし、なんでこの政策が今必要なのかとかがわからないことも多い……のは私だけでしょうか?😢
民法がやっと改正のはこびになって、体罰禁止になりましたね。最初は、こども庁だったのに、子供家庭庁になった経緯もちょっと不穏ですが😨日本の子供達も、もっと生まれてきて良かった!と思えるようになると良いですね。自分の子育てにも勉強になりました!難しい話題かもしれませんが、又スウェーデンの情報をお願いします😺
私40代ですが、自身が通学していた中学校は基本的に生徒の意見を聞いて、行事(体育祭や学園祭など)を決める。という方針でしたので、生徒と先生が協議しながら色々決めていました。
とても斬新だったのは、生徒から「制服は必要か?」と意見が出た際の先生たちとの協議です。制服があることのメリットやデメリットについて話し合い、結果として「私服登校週間」を取り入れるに至りました。
基本的に「先生たちと協議して決める」という方針だったので、自身の考えをきちんと相手に伝える、相手の意見をきちんと聞くという協議の基本姿勢は、中学時代に学んだのかもしれません。
おそらく、自分の考えが受け入れられる、どんな意見でも発言が許されるという安心感もあったのだと思います。
そう考えると、教育現場での取り組みって本当に大切ですね…
こんにちは。ストックホルムはしっかりした雪が降ったそうですね。
西崎さん: 東京でセカセカしないように頑張る
って結局、頑張らなきゃならないところが日本なんだよだなぁ、と思いました。
日本で博物館とかへ行くと子供向けっぽい展示が多い気がしています。そういうのって子供のためにそうしてるっていう大人の独りよがりで、大人の思考になることへの障害になると思っています。
西崎さんのお話、参考になりました。私も子育て真っ最中です(ハワイ島で)。子供の権利条約というと、堅苦しく思うかもしれないですが、子供が成長していく環境を整えて、子供個人を尊重するっていうことですよね。今いる場所は究極にのんびりしているのですが、東京に里帰りすると電車の駅で、スーパーで、ファミレスで、バスの中でなどなど、子供が大きな声出したりするたびにキーキー言ってしまう自分をなんでだろう?どうしてこうキーキーうるさく言ってしまうんだろう?って思ってたら、子供にもズバリと「ママは東京に行くと、僕をすぐに叱るから好きじゃない」と言われました。ヨウコ室長の東京は時間が過ぎるのが早すぎると感じる気持ちにも、激しく同感しました。いつも動画をありがとうございます。
子供はいずれ大人になる人間なんだってことですよね
20歳なり35歳になったからといっていきなりちゃんとした大人になるわけじゃない…
要は 自分の意見を主張できて なおかつ他人と折り合いをつけられる大人…になる準備を子供の時からする ということだと思います
小学生の時に学生会役員となり、学内でUNICEF募金活動をしたいと伝えとことがありました。募金活動の方法まで自分達で考え、実行できましたよー。ちょうど子どもの権利条約が採択された頃のことです。
子どもの権利、日本はこれからですね。参考になりました。就学前学校や小学校等の現場の報告期待しています。
「こども家庭庁」の名称を決める際にも、某カルト宗教団体が政治家と絡んでいたという問題もありますが、御存知でしょうか?日本は政治の根幹から総入れ換えしなければ、教育や、子どもに関わる実態は悪化すると私は思っています。国のトップが汚染されていますから。
私の働いていた保育園では、12年前ほどから、『子どもの権利』について、年に一回子どもたちが学ぶ機会がありました。外部の講師の方を呼んで行っていました。子どもたちが覚えやすい言葉や体の動きを使って子どもの権利条約とは何かを知って行く機会になっていました。私自身も学校では習った記憶はあっても、どう教えるかのスキルは身につけておらず、まずは大人が知っていかなくてはと思いました。自分も学びながら、子どもたちも知る機会を作っていくことは大事ですね!
子育てに税金つぎ込むのは構わないが「躾け」だけはしっかり義務付けてくれ。
日本人は常に不安を動機で動いてるからセカセカしてる。そしそれは社会の常識や制度によって作られる。神風の国だから、通俗道徳的な非論理的で勇ましい物言いが受ける。