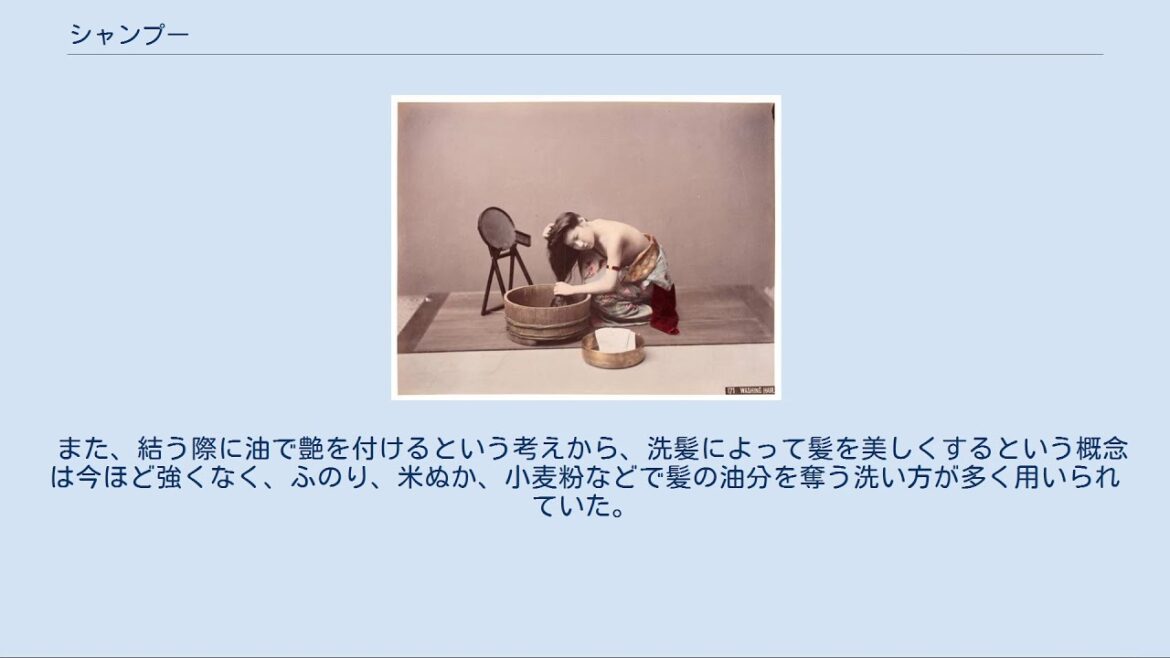シャンプー, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=163736 / CC BY SA 3.0
#シャンプー
#インドの発明
シャンプーによる洗髪 シャンプー(英: shampoo)は、頭髪および頭皮を洗浄するための洗剤である。
シャンプーの形状には粉末、固形、ペースト、液状などがあるが、現代ではほとんどが後者のものである。
原語はヒンディー語で「マッサージをして頭皮、毛髪を清潔に保つ」である。
洗髪剤(せんぱつざい)と訳されることもある。
また、洗髪自体を「シャンプー」「シャンプーする」と言う。
シャンプーで髪と頭皮を洗浄した後は、リンス、コンディショナー、トリートメントなどで髪の保護をするのが一般的である。
なお、洗髪の際にはシャンプーブラシが用いられることもある。
店頭で陳列販売されるシャンプー 数十年前のシャンプー 水を基材に、ラウリル硫酸ナトリウム・ラウレス硫酸ナトリウムといった洗浄剤、増泡剤、保湿剤、キレート剤、香料、防腐剤を成分とする。
シャンプーの洗浄剤には、アミノ酸系、高級アルコール系、石けん系がある。
アミノ酸系 アミノ酸系は毛髪や頭皮に対する刺激は小さいが他に比べると洗浄力も若干弱い。
現代の洗髪回数の状況も考えると皮脂の分泌の少ない人に適した製品である。
高級アルコール系 高級アルコール系は他に比べるとやや洗浄力が高く、皮脂の分泌の多い男性や脂性肌の女性向けの製品である。
シャンプーの改良により特性を活かした配合製品も多く販売されている。
石けん系 石けん系は化学的には高級脂肪酸のナトリウムまたはカリウム塩でアルカリ性が強いため、アルカリ性に弱い毛髪への使用には注意が必要である。
ただし、石けん系シャンプーは脱脂力が大きいため、強い脂性肌には適切なアフターケアをすれば有効である。
なお、石けんの解釈の拡大により、弱酸と弱アルカリ塩からなる形状が固形石けんの界面活性剤も「石けん」と呼ばれることがあるため性状による分類との区別が必要である。
界面活性剤(洗剤)は、肌の油分を落とすことで肌の硬さ、乾燥、バリア機能の低下、刺激や痒みを起こすことがあるが、ステアリン酸やパルミチン酸のような飽和長鎖脂肪酸を添加することで、脂肪酸が補充されバリア機能の改善に役立つ。
こうしたバリア機能の破壊はフケの発生につながることがある。
(対応シャンプーは「フケ」の項を参照) 一般的にはシャンプー、リンス、コンディショナー、トリートメントはそれぞれ別のパッケージで発売されるが、シャンプーとリンスが一緒になった機能を持つリンスインシャンプーも発売されている。
そのほか、キャンプ・介護・非常時等入浴ができない場合に水なしで洗髪できるドライシャンプーも販売されている。
なお、JIS規格ではシャンプーの容器に凹凸を付ける事が望ましいとされている。
この容器の凹凸は視覚障害者がリンスの容器と区別するためのもので『識別リブ』と呼ばれる。
英語の shampoo の語源はヒンドゥスターニー語の chāmpo (चाँपो [tʃãːpoː]) に因むもので、1762年には使われていた。
ヒンドゥスターニー語の chāmpoは、ムガル帝国のビハール州周辺において行なわれていた香油を使った頭部(髪)マッサージの事を示していた。
このchāmpoは、東南アジアから南アジアにかけて自生し香料としても使われているキンコウボク(Magnolia champaca)が起源とも考えられている。
この頭部マッサージの習慣は、18世紀には英領インドから英国に伝わった。
1814年にビハール州出身のシャイフ・ディーン・ムハンマドが、イギリス南部のリゾート地ブライトンの浴場ハンマームで頭部マッサージの提供を開始し、イギリス王室にも認められるところとなった。
20世紀初頭、ワシントンD.C.のC.L.ハミルトン社のシャンプーとローション その後1860年ごろには、シャンプーが頭部マッサージから洗髪を意味するようになった。
初期には石鹸が使われていたが、20世紀に入り頭髪用のシャンプーが販売され始めた。
1954年にはカーペット等の洗浄の意味でも使われるようになった。
初期には石鹸にハーブを混入したものを洗髪に使用していたが、やがて石鹸シャンプーとして一般に普及。
1930年代に至って界面活性剤が開発されると、高級アルコール系シャンプーが売り出される様になった。
20世紀以前[編集] 日本では、洗髪の習慣は過去に遡る程頻度が少なく、日本髪が結われていた時代は1ヶ月に一度程度というのが一般的であった。
明治時代の美容本「化粧のをしへ」によると、「女の髪の不潔になったのを嗅ぐと小便…