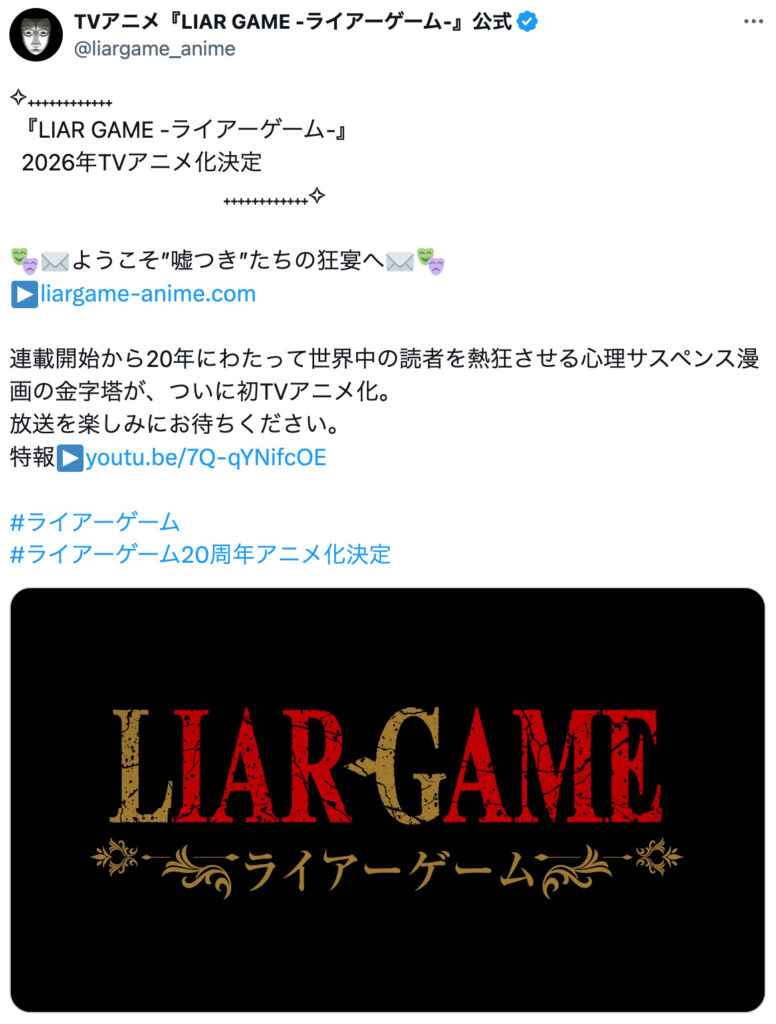甲斐谷忍の大ヒットコミック『LIAR GAME』(集英社)が、2026年、「連載20周年」を記念してTVアニメ化されることが発表された(マッドハウス制作/放送局は現時点では未発表)。
✧₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊
『LIAR GAME -ライアーゲーム-』
2026年TVアニメ化決定
⠀⠀ ₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊✧🎭✉️ようこそ”嘘つき”たちの狂宴へ✉️🎭
▶️https://t.co/WsiKLP876l… pic.twitter.com/Egy3BhU95q— TVアニメ『LIAR GAME -ライアーゲーム-』公式 (@liargame_anime) August 22, 2025
『LIAR GAME』は、2005年から2015年にかけて、「週刊ヤングジャンプ」にて連載された頭脳バトル漫画の金字塔である。
主人公は、神崎直という名の女子大生。「バカ正直のナオ」と呼ばれている彼女のもとに、ある時、怪しげな小包が届く。「ゲームに参加する場合のみ、箱をお開けください」という注意書きがあるにも関わらず、思わず箱を開けてしまうナオ。中には札束が1億円分入っていたのだが、この瞬間から彼女は、巨額の金が動く「LIAR GAME」に、半ば強制的に参加させられることになるのだった……。
当然、というべきだろう、「バカ正直」なナオは、一回戦のゲーム(五回戦まである)が始まるやいなや、対戦相手に金を騙し取られてしまう。ゲームのルールにより、期日内に金を取り戻せない場合は、巨額の負債を背負うことになるのだが、困り果てた彼女は、ある特異な人物にすがりつくことに。それは、出所したばかりの“天才詐欺師”――秋山深一という青年だった。
「そんなバカ正直だから騙されるんだ」という秋山に、ナオは答える。「バカ正直じゃいけませんか?」
極限状態の中、次々と参加者たちが醜い本性をむき出しにしていく“嘘つきのゲーム”で、果たして彼女は勝ち残ることができるのだろうか――。
“文字ばかり”の漫画は読む気がしない?
ところで私は、四半世紀ほど前、とある週刊青年漫画誌の編集部に勤めていたのだが、そこで先輩編集者たちからよくいわれていたのが、「文字(セリフ)ばかりの漫画」や、「キャラの顔のアップばかりの漫画」はダメだということだった。
要は、その手の漫画(=文字ばかりで、絵的にもあまり変化のない漫画)は読者から敬遠されがちなので、そうならないように気をつけねばならない、ということなのだが、なぜそんなことをいまさらここで書いているのかといえば、くだんの『LIAR GAME』がまさにそんな漫画だからだ。
むろん、同作が頭脳戦や心理戦を主軸においた漫画である以上、セリフやモノローグが多くなるのは必然ともいえるし、それ(会話劇や心の葛藤の様子)を漫画で表わす場合、どうしてもキャラクターの顔のアップが多くなってしまうということも、理解できなくはない。
それでもなお、結果的に『LIAR GAME』が多くの読者に恵まれたというのは、ひとえに同作のストーリー展開とセリフ回しがよくできていたからだろう。当たり前の話だが、漫画を読んでいて「長く」感じるのは、「文字が多い」からではなく、単に「つまらない」からなのだ。そういう意味では、『LIAR GAME』は、読んでいて「短く」感じる漫画だといっていい。つまり、単純に「おもしろい」から、長尺の会話劇が続いても全く苦にならないのである。
そしてもう1つ。実は『LIAR GAME』の連載が始まったゼロ年代半ばには、この手の会話劇中心の頭脳バトル漫画がヒットする流れができていた、という見方もできるだろう。
具体的なタイトルを挙げれば、『賭博黙示録カイジ』(福本伸行/1996年〜1999年)、『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博/1998年〜)、『DEATH NOTE』(大場つぐみ・小畑健/2003年〜2006年)といった作品のヒットが、この手の漫画(肉体を使ったバトルではなく、頭脳戦・心理戦を主軸にしたデスゲーム物)が読者に受け入れられやすい土壌を作っていたともいえるし、同じ“文字が多くなりがち”なジャンルに「ミステリ漫画」があるが――『金田一少年の事件簿(第1期)』(金成陽三郎・さとうふみや/1992年〜2001年)や、『名探偵コナン』(青山剛昌/1994年〜)などの成功も無視はできまい。
20年前の漫画作品がいまアニメ化されるワケは?
とはいえ、「ストーリーがよく練られている」、「セリフ回しが上手い」というだけではまだ不十分で、(これまたかつての職場でよくいわれていたことなのだが)漫画は“キャラが立って”いなければならない(上記の作品群も、結局は、主人公たちのキャラが立っているからおもしろいのだ)。
その点では、『LIAR GAME』は、「バカ正直なヒロイン」と「したたかな詐欺師」という、主人子ふたりのキアロスクーロ(明暗対比)が絶妙であった。ゲームが進むにつれ、ナオは、人を信じ続けることでしか得られない“強さ”を身につけ、そんな彼女に影響され、秋山もまた(彼は二回戦以降、プレイヤーの1人としてゲームに参加することになる)、「人は疑うべきだ」という考えを徐々に改めていくことになる。
何かと、フェイクニュースや、SNSでの誹謗中傷などが問題視されている現在、「他者を信じる力」がテーマの本作がTVアニメ化されることの意義は、ことのほか大きいといえるだろう。

島田一志
Follow on SNS
1969年生まれ。ライター、編集者。「週刊ヤングサンデー」編集部を経て、「九龍」元編集長。コミックを中心にサブカルチャー全般の批評活動を展開。著書に『ワルの漫画術』、『ロック・コミック』、編著に『漫画家、映画を語る。』、『マンガの現在地!』、『コロナと漫画』、共著に『進撃の巨人という神話』、『ベルセルク精読』などがある。
島田一志の記事一覧はこちら