弊誌では既に『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』のレビューを公開しているが、かくいう私も本作をプレイし心動かされたゆえ、感想を述べたいと思う。ゲームに関する感想は有れば有るほど良いものだ。本作の価格は税込7700円。『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は物語が氾濫する現代において、低価格帯のアドベンチャーゲームが流行する昨今だからこそ、唯一無二の魅力を放つ規格外のゲームである。
※本稿には物語の核心的なネタバレが含まれているため、閲覧には注意してほしい。
本作の特徴は、ゲームデザインそのものである

100のエンディングをセールスポイントの1つとしている『ハンドレッドライン』。同作の特徴は、エンディングの数というより、それを内包するゲームデザインにあると言っていいだろう。今日において、俗に言う「ルート分岐」を採用したアドベンチャーゲームの形態は、さまざまな方向性に枝分かれしていった。たとえば、入力という証拠を通じて、プレイヤー個々人に異なる物語を提供する作品がある。『Detroit Become Human』が有名だ。周回プレイを前提として、分岐により体験のバラエティを提供する作品もある。主に恋愛シミュレーションの要素を取り入れている作品群が有名である。
このほか、いわゆる「本編」を強調する「外伝」のために、分岐を採用する作品がある一方で、オムニバスの形式を取りながら、作品全体として一貫したテーマを描く作品もある。ただ「枝分かれ」とは表現したが、基本的にこれらの方向性は物語の構成要素として、どのタイトルにも大なり小なり、異なる割合で含まれている。要素のうち特化した部分が作品の個性としてプレイヤーの前に顕在化するというわけだ。

そして『ハンドレッドライン』の場合は、上記要素が山盛りになっている。本作はあくまで既存の方向性の詰め合わせである。「これまでになかった革新的な方向性による体験」、というものを提供する作品ではない。しかし、既存の全方面に尖っているため、遠目に見ると「丸」に見えるという規格外の作品である。
まず「プレイヤー個々人に異なる物語を提供する」については、マイルストーンに到達するゲームにも関わらず、プレイヤーが計画を立てられないという仕様を通じ生まれる緊張感と、突発的に発生する選択肢の存在。これが各ルート100日近く続くというボリュームによって成立している。先の見えないドキドキ・ワクワクを100日続けたという事実は、「愛着」という形でプレイヤーの印象に強く残る。「体験のバラエティ」についてはセールスポイントである100のエンディングが担う。また、本作は100のエンディングを通じ、作品全体として2つの方向性を描く、という独特な構成になっている。
ゆえに、本作は「好きなルート分岐」「好きなキャラクター」「全体的な物語構成」などさまざまな観点から作品を語ることが可能だ。筆者は「全体的な物語構成」に美しさ、心地よさを感じた人間であるため、本稿ではそれについて語っていこうと思う。
少年の視点と大人の視点

本作は選択肢を通じてさまざまなルートに物語が展開していくが、その方向性は大きく2種類に分けられる。「少年兵」として侵略戦争に対し主観的に取り組む分岐と、「大人によるサポート」を通じ、侵略戦争を俯瞰視点で捉え、馬鹿げたものとして責任を放棄する分岐である。前者はヒロインである少女を救うという少年漫画的な大義のもと進行し、侵略戦争という極限状態によって発生するグロテスクな認知の変化や、度重なる犠牲と心身の成長を伴いながら、結末としては「勝戦」から「敗戦」のグラデーションの中に収まっていく。振り上げた拳の行方が主題となる。
一方、後者はもう一人の大人びたヒロイン(と筆者が考えている)からサポートを得ることで視野を拡大し、造られた兵器ではなく1人の人間としてさまざまな人生体験を得つつ、戦争責任を放棄する道を模索する。ルート分岐の存在をプレイヤーに明示したり、分岐内容がホラーやデスゲーム、宝探し、青春物語、謎解きになっていたりと、本作の舞台となる侵略戦争は押し付けられたゲームでしかないという演出が続く。戦争が話題の中心とならないことで、キャラクターの多面的な掘り下げも行われる。広い視野を持って行動すれば現実を変えられるというメッセージも込められているかもしれない。
とはいえ、後者が俗に言う「良い分岐群」なのかと問われればそうではない。責任を放棄して主人公たちだけ助かろうとするため、戦争を仕掛けたことにより発生する諸問題は一切解決されないどころか、見向きもされない。憎しみの連鎖は断ち切られることはない。前者はそれに(犠牲は伴うが)一定の決着を見出し、当事者として責任を全うする内容であるため、一概に「悪い分岐群」とは言えないのだ。
この構成は筆者にとって魅力的に映った。大人の力で責任から逃れる物語が存在すること自体、風刺的で新鮮であったということもあるが、その逃亡劇がドラマチックに描かれていたからである。戦争記に匹敵するほどに。ぜひとも成功させたいと思えるような内容だったのだ。これによって、筆者は選択をするたびに疑念と後悔を抱き続けていた。画面に向かってさまざまな言い訳をし続けていたのだ。戦争に向き合わずに良いのかと。しかし戦争に熱中していて良いのかと。ルート分岐を採用する作品は入力経験という証拠をプレイヤーに突きつけることで、選択に対し納得感を与えるものではあるが、『ハンドレッドライン』はプレイヤーが結果に対し完全な納得を与えないよう物語体験が構成されているように感じられた。心に残ったしこりを取り除くべく、結果としてさまざまな100日間を経験することになった。小高和剛と打越鋼太郎の作風が手を取り合った、本作ならではの体験であった。
物語が氾濫する中で フルプライス・シナリオ主体なゲームの行方
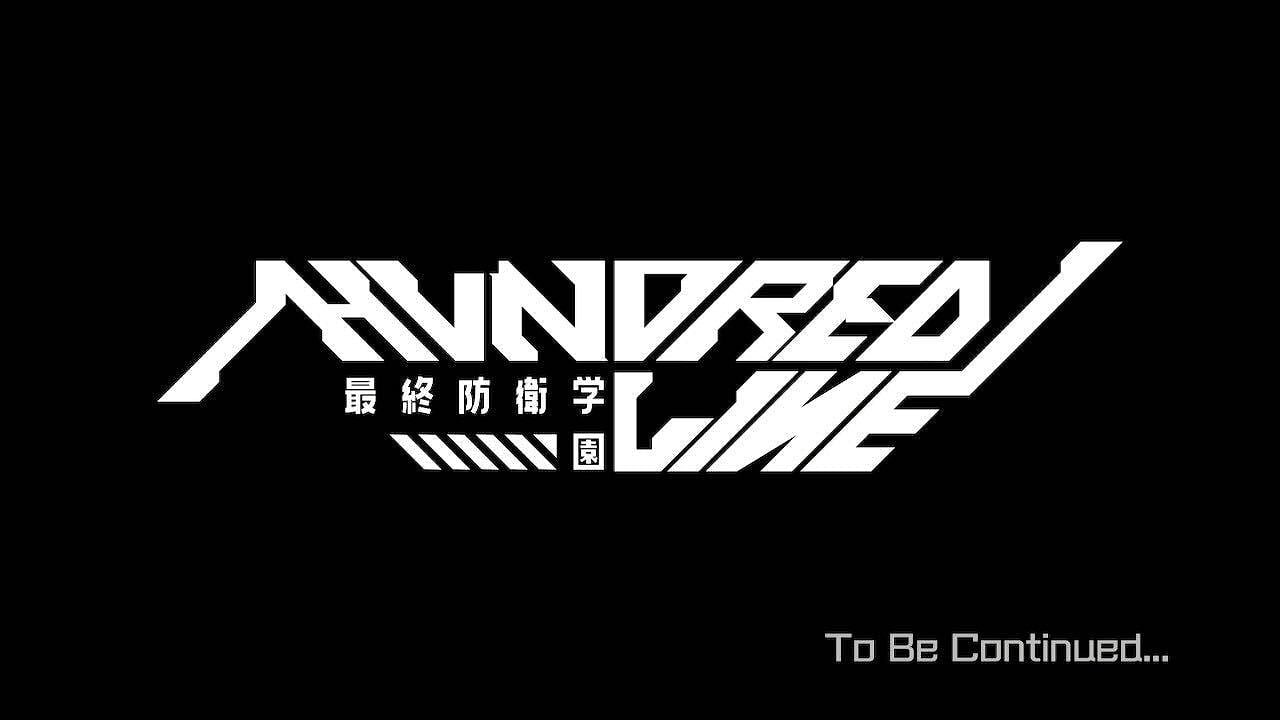
そしてゲームクリア後。本作のようなフルプライス・シナリオ主体なアドベンチャーゲームの今後について思いを馳せた。筆者の印象としては、現状、当該スタイルの主戦場はインディーを中心とした小規模開発作品であったり、基本プレイ無料のサービス型作品であるように思う。特に近年のサービス型作品はテキストだけでなく、インタラクティブな物語体験を提供するものが増え続けており、「シナリオだけ抽出して買い切りにして欲しい」といった意見も今は昔である。実際に買い切り形式になった作品もある。要するに、比較的低価格で楽しめる作品が氾濫する昨今において、消費者が高価格帯に踏み込む理由をこのスタイルは提供出来るのかということだ。言い換えれば、「高価格帯ならではの体験が含まれた作品」とは何かという疑問である。
リッチな映像効果にしても体験のボリュームにしても、画期的な入力ギミックについても、今では低価格で楽しめるため、それ自体がフルプライス作品への吸引力になることは無いだろう。何ならこのジャンルのゲームは、インタラクティブで先の読めない物語を提供するコンテンツとして、「人間」……オフラインイベントを開催できる「ストリーマー」や「アイドル」と競合していると筆者は感じている。であれば、残された道はフロンティアの開拓に他ならない。自ら望んで規格外になり、新たな規格を作らねばならない。
『Detroit Become Human』は無数の分岐を作った。『十三機兵防衛圏』『ファタモルガーナの館』は極めて緻密な物語を建立した。『ジャックジャンヌ』は女性向けシミュレーションゲームとして、恋愛を主役とせず素材の一つにした物語を作り上げた。そして『ハンドレッドライン』はさまざまな100日間を通じ、膨大な質量を持った心残りをプレイヤーにもたらす作品である。この他、近年の著名作はいずれも無茶苦茶なことをやっている。平たく言えば「真似できないことをやる」。「真似されないことをやる」。フルプライス・シナリオ主体のアドベンチャーゲームは他ジャンルの大作と比較すると、開発規模の差ゆえにスタッフの属人性が反映されやすいという性質もあるが、結果的にそうした状況に追い込まれているのだろう。
だが、いち消費者としてはこんなにも贅沢なことはない。サービス型や小規模開発の作品がテクニカルなシステムや社会思想の反映という手法で存在感を示し、『VA-11 Hall-A』のような形で規格を作り後続に継承していく傍ら、名のある開発スタジオが、堂々と規格外の作品に挑戦していく。メジャー/インディーズの隔たりなく、同じショーケースの上で作品が販売されるからこそ、こういった状況が成立している。百花繚乱とはこのことだ。物語が氾濫する現代において、フルプライス・シナリオ主体なゲームは今後も生まれ続けるだろう。『ハンドレッドライン』がその証拠である。

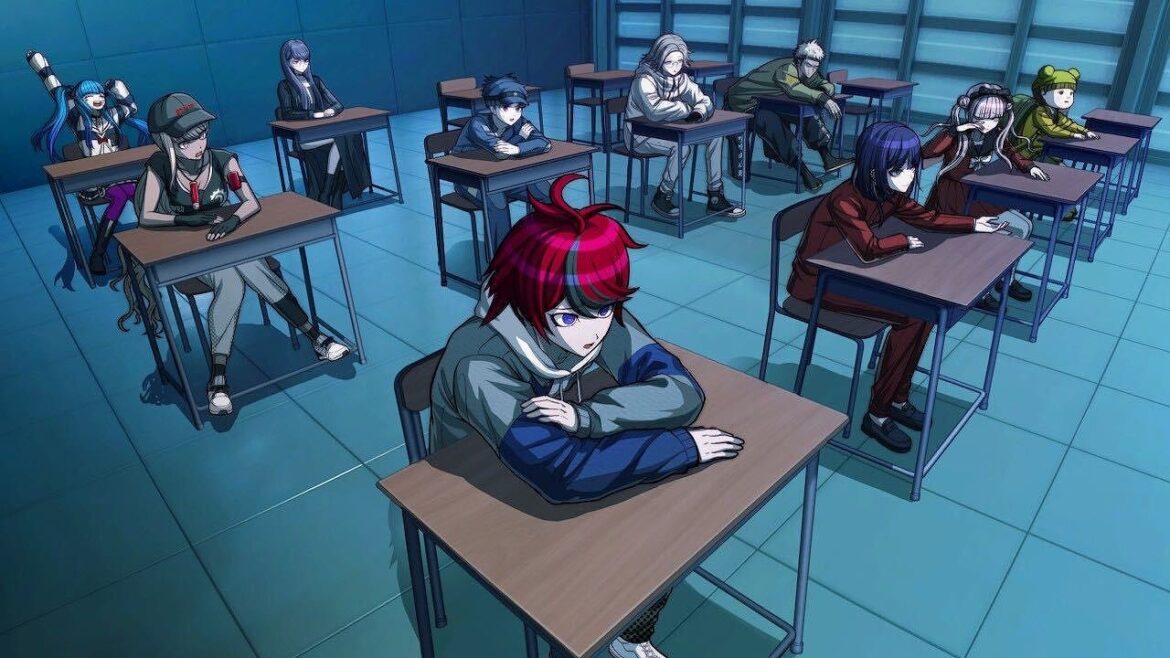
WACOCA: People, Life, Style.