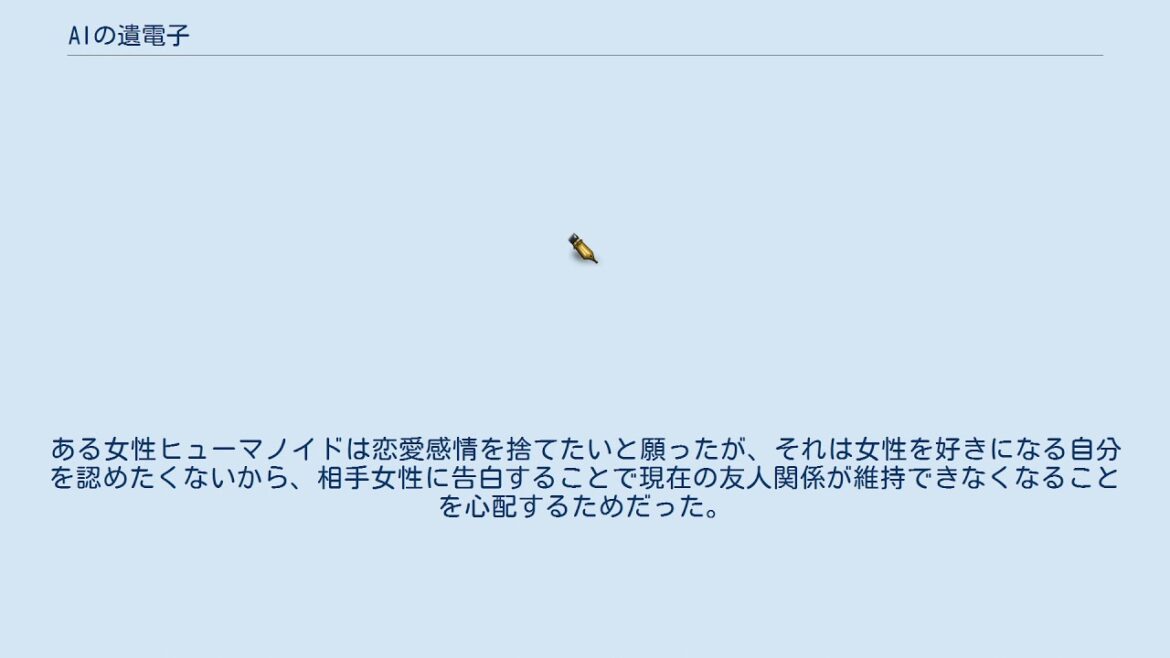AIの遺電子, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=3644775 / CC BY SA 3.0
#漫画作品_あ
#2015年の漫画
#週刊少年チャンピオンの漫画作品
#自律ロボットを題材とした漫画作品
#人工知能を題材としたフィクション作品
#継続中の作品
『AIの遺電子』(アイのいでんし)は、山田胡瓜による日本のSF漫画作品。
『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)で、2015年49号(同年11月5日発売)から2017年39号(同年8月24日発売)まで連載された。
続編の『AIの遺電子 RED QUEEN』が、『別冊少年チャンピオン』(同社刊)にて、2017年11月号(同年10月12日発売)から2019年7月号(同年6月12日)まで連載。
『AIの遺電子 Blue Age』が、同誌にて、2020年8月号(同年7月10日発売)から連載中。
人間、ヒューマノイド、ロボットが当たり前のように存在する近未来を舞台に、ヒューマノイドを治療する人間の医者を主人公として、人間とヒューマノイド双方の考え方の違いによって起きる問題を戦争、テロ、殺人事件、陰謀、暴力、憎悪ではなく、「愛」、「友情」をベースに描くオムニバスストーリーである。
大西赤人は、「AI」を「アイ」と読ませ「愛」や「I」(英語の一人称であり、自我としての“私”)の意味を含ませることで人間的にし、逆に遺伝子ではなく「遺電子」とすることで“機械”としての意味を打ち出しているのではないかと推測している。
また、大西は本作について、ヒューマノイドのAIがなぜ感情を持つのか、感情を持たねばならないのか、人間の感情とは何なのか、人間の感情も人間の成長過程において「プログラム」されているのではないのか、人間の感情の基盤となる記憶そのものも不正確な後天的プログラムなのではないかと、ヒューマノイドという空想的な題材を描きつつ、人間自体のありようを考えさせる作品であると評している。
山田自身は、将来、人間と同等の人工知能 (AI) が登場したときには、AIと人間とは対等のものとして扱われるべきではないのか、人間と同等のAIは、人間同様に間違いも起こすはずであり、AIの間違いをどこまで許容できるのか、といったような問題を考える際の参考になれば良いと語っている。
コミックス1巻発売時の帯には「これぞ近未来版ブラック・ジャック! 人工知能を治療する新医者!」と書かれていた。
また、ブラック・ジャックのイニシャルである「BJ」を1文字シフトすると「AI」になることも指摘されている。
第21回(2017年)文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した。
ヒューマノイドを治療する専門医の須堂光は人間である。
須堂の病院をさまざまな悩みを抱えたヒューマノイドが治療に訪れる。
あるヒューマノイドの落語家は、蕎麦を美味そうに食べているように見せられないのは、人間とは感覚が違うからだと悩むが、人間の師匠は蕎麦アレルギーで蕎麦を食べられないことを知ると、自身の芸の拙さに問題があったのだと気づく。
ある女性ヒューマノイドは恋愛感情を捨てたいと願ったが、それは女性を好きになる自分を認めたくないから、相手女性に告白することで現在の友人関係が維持できなくなることを心配するためだった。
絵を描き続ける画家のヒューマノイド、小説を書くヒューマノイド、歌を生業とするヒューマノイドなど、自らの才能の限界に悩んだり、ヒューマノイド故に可能なボディの交換による歌声の微々たる変化といったヒューマノイド独自の悩みに苦しむ。
基本的に一話完結だが、徐々に明かされていく須堂自身の事情が物語の縦糸として機能している。
須藤はヒューマノイドの母親に育てられ、その母親が違法行為であるコピー人格の販売を行って収監されており、母親のコピーを探すことを目的としていた。
前作からの続編だが、連続したストーリーとなっている。
母親のコピー人格を追って、須堂は記者の身分で内戦中のロビジアへ。
人間至上主義の北ロビジアがヒューマノイドの電脳を集めていることを知り、北ロビジアへ潜入する。
第1作の前日譚。
国立医療機構の大病院のヒューマノイド科に研修医として勤務していた頃の須堂を描く。
AIの遺電子 RED QUEENに関するカテゴリ: AIの遺電子 Blue Ageに関するカテゴリ: