Serial experiments lain, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=123063 / CC BY SA 3.0
#メディアミックス作品
#アニメ作品_し
#1998年のテレビアニメ
#日本のオリジナルテレビアニメ
#テレビ東京の深夜アニメ
#トライアングルスタッフ
#ジェンコのアニメ作品
#NBCユニバーサル・ジャパンのアニメ作品
#仮想世界を舞台としたアニメ作品
#SFアニメ
『serial experiments lain』(シリアルエクスペリメンツレイン)は、グラフィック+テキスト形式の雑誌連載企画・アニメ作品・ゲーム作品が同時進行・相互関連して制作されたメディアミックス作品である。
1996年頃に企画が開始され、1998年に作品が発表された。
サイバーパンク的な作品であるが、オンライン時代の集合的無意識が主なテーマであり、サイコホラー的な側面も併せ持っている。
雑誌ではAXで1998年3月10日から11月10日まで連載、テレビアニメはテレビ東京で同年7月6日から9月28日まで放送(半年遅れでテレビ大阪・テレビ愛知でも放送)され、第2回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞した。
ゲームはプレイステーション(PS)用ソフトとして同年11月26日に発売された。
『存在は認識=意識の接続によって定義され、人はみな繋がれている。
記憶はただの記録にすぎない。
』という世界観のもとで繰り広げられる、14歳の少女・玲音(lain)をめぐる物語。
リアルワールドとコンピュータネットワーク・ワイヤード(Wired = 繋がれたもの)に遍在する「lain」という存在について。
分析心理学の創始者、カール・グスタフ・ユングが提唱した集合的無意識の化身”lain”がワイヤードを介して現実世界を侵食するというサイコホラー的な作品である。
1990年代のアンダーグラウンドなオタクカルチャーを未来的に描き直したような作風で、全作品で一貫して陰鬱とした雰囲気がある。
メディアミックスの実験でもあり、媒体間の相互参照により世界観への理解が深まるような仕組みが作られている。
ゲーム版とアニメ版では、登場人物もストーリーも”lain”という存在や破滅的な傾向を除いて大きく異なる。
雑誌連載されたグラフィック+テキストは、キャラクター原案の安倍吉俊による画集『an omnipresence in wired』(オムニプレゼンス=遍在)に未掲載分を含めた完全版が収録されている。
長らく絶版だったが、ワニマガジン社より『yoshitoshi ABe lain illustrations』として描き下ろし分を追加して再版された。
脚本の小中千昭によるアニメ版シナリオ集『scenario experiments lain the series』(シナリオエクスペリメンツ・レイン)なども出版されており、パイオニアLDCからは、『serial experiments lain BOOTLEG』と題したデスクトップアクセサリー集も発売された。
当初、主人公の名前であるレインの英語表記は未決定で「lain」と「rain」が検討された。
安倍吉俊によるスケッチなどは試験的に2種類描かれたが、結局1997年3月頃に「lain」に決定された。
日本のみならず海外でもカルト的な人気を誇り、ファンコミュニティが活動を続けている。
高度に発展したネットワーク社会から連想される、現実と区別のつかない仮想空間というよくある物語とは逆に、本作は仮想世界(wired)と区別のつかない曖昧な現実(real world)に注目する。
各登場人物が語る真実も事実だという保証はない。
主人公・玲音の世界は身近な人間や友人に関する内容で占められ、作品は玲音の主観の影響下にある。
客観のこのような不在はネットワークやコミュニケーションの性質をリアルに描いており、視聴者もlainという作品、岩倉玲音と繋がった『ネットワーク』に接続するよう仕向けられる。
番組のエンドカードには、直後に放送されていた「ウェザーブレイク」を意識した、安倍吉俊によるイラストが挿入されていた(このイラストはDVDに一部、BD-BOXでは全て収録されている)。
また、最終話放送後、CMの時間帯にワイヤード上の存在となった玲音が視聴者に向けて呼び掛ける映像が挿入されるなど、現実との融合を強く意識した演出が行われた。
根底には集合的無意識という考え方が導入されており、作中で遍在という言葉が頻繁に登場する。
岩倉玲音自身は人の姿をした集合的無意識そのものであり、英利政美が改変を加えたワイヤードのプロトコルにより集合的無意識が意識化される事で、玲音…

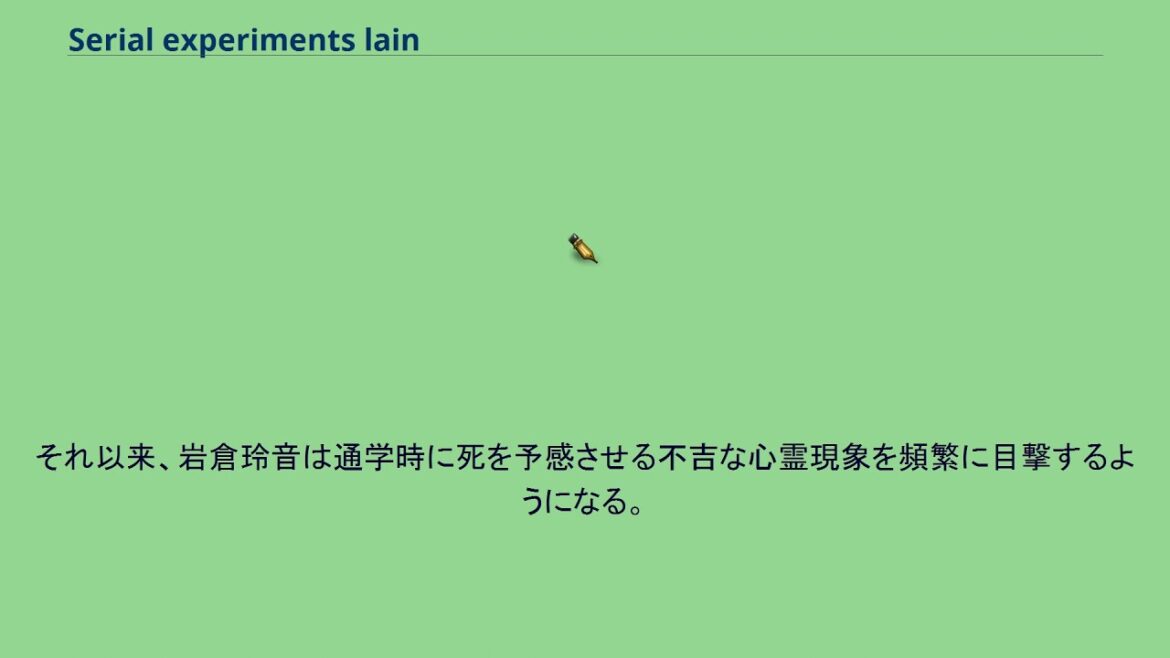
WACOCA: People, Life, Style.