✴️「自分が何をできるかを考える」ことの意味 #名言 #心の哲学 #歴史 #大事なこと #うれしい #audiobook #いい言葉 #なぜ生きる #雑学
自分が何をできるかを考えることの意味。 人は生まれた時から周囲に支えられて生き ています。両親や家族に育てられ、社会に 守られ、教育を受け、食べ物や住まを与え られて成長してきました。そのため私たち は気づかないうちにしてもらうことになれ ています。しかし、ある段階に差しかかる と人生は何をしてもらえるかではなく、 自分が何をするかによって開けていくのだ ということを知る必要があります。上皇明 さんの言葉はその転換点を示しています。 人は誰しもっと助けて欲しい、理解して 欲しい、与えて欲しいと願うものです。 しかしその思いが強すぎるといつしか他人 に依存し受け身の姿勢に陥ります。結果と して状況が変わらないことを他人のせいに し自らの可能性を閉ざしてしまいます。 一方自分が何をできるかを考える人は どんな環境にあっても主体的に道を 切り開きます。与えられた条件が不十分で も工夫や努力によって力を発揮し、人の ために働くことによって周囲から信頼を得 ます。その信頼はやがて大きな縁となり、 さらに自らの可能性を広げてくれるのです 。依存から主体へ私たちは成長の家庭で あの人がもっとこうしてくれたらいいのに 社会がもっと便利になればいいのにと望む ことがあります。確かに他人や社会が与え てくれるものは大切ですけれども、それを 求めすぎると自分の成長は止まってしまい ます。例えば学校で先生の教え方が分かり にくいと感じることがあるかもしれません 。その時先生がもっと分かりやすく教えて くれればいいのにと不満を抱く人もいれば 分かりにくいなら自分で調べてみよう。 友人に聞いてみようと動く人もいます。 校舎の姿勢を持つ人は自らの努力を通じて 理解力や行動力を養い結果的に成長して いきます。社会に出ればさらにその差は 大きくなります。上司が理解してくれない 。会社が十分に環境を整えてくれない。 政府が支援してくれないと嘆く人は少なく ありません。しかし、そこで立ち止まるか 、それとも自分に何ができるかを問い 続けるかで未来は大きく変わります。主体 的に動く人は小さな一歩を積み重ね、 やがて大きな成果を生み出していきます。 与えることが人を育てる。
「自分が何をできるかを考える」ことの意味
人は生まれたときから、周囲に支えられて生きています。両親や家族に育てられ、社会に守られ、教育を受け、食べ物や住まいを与えられて成長してきました。そのため、私たちは気づかないうちに「してもらう」ことに慣れています。しかし、ある段階に差しかかると、人生は「何をしてもらえるか」ではなく「自分が何をするか」によって拓けていくのだということを知る必要があります。
上甲晃さんの言葉は、その転換点を示しています。人は誰しも「もっと助けてほしい」「理解してほしい」「与えてほしい」と願うものです。しかし、その思いが強すぎると、いつしか他人に依存し、受け身の姿勢に陥ります。結果として、状況が変わらないことを他人のせいにし、自らの可能性を閉ざしてしまいます。
一方、「自分が何をできるか」を考える人は、どんな環境にあっても主体的に道を切り拓きます。与えられた条件が不十分でも、工夫や努力によって力を発揮し、人のために働くことによって周囲から信頼を得ます。その信頼はやがて大きな縁となり、さらに自らの可能性を広げてくれるのです。
依存から主体へ
私たちは成長の過程で、「あの人がもっとこうしてくれたらいいのに」「社会がもっと便利になればいいのに」と望むことがあります。確かに他人や社会が与えてくれるものは大切です。けれども、それを求めすぎると、自分の成長は止まってしまいます。
例えば、学校で先生の教え方が分かりにくいと感じることがあるかもしれません。そのとき「先生がもっと分かりやすく教えてくれればいいのに」と不満を抱く人もいれば、「分かりにくいなら自分で調べてみよう」「友人に聞いてみよう」と動く人もいます。後者の姿勢を持つ人は、自らの努力を通じて理解力や行動力を養い、結果的に成長していきます。
社会に出れば、さらにその差は大きくなります。上司が理解してくれない、会社が十分に環境を整えてくれない、政府が支援してくれないと嘆く人は少なくありません。しかし、そこで立ち止まるか、それとも「自分に何ができるか」を問い続けるかで、未来は大きく変わります。主体的に動く人は、小さな一歩を積み重ね、やがて大きな成果を生み出していきます。
「与える」ことが人を育てる
自分にできることを考えるという姿勢は、単なる自己成長にとどまりません。それは周囲の人々をも励まし、社会を変えていく力を持っています。
例えば、友人が悩んでいるときに「誰かが慰めてくれるだろう」と傍観するのではなく、自分から声をかけて寄り添う。その一言が友人の心を救うこともあります。職場で同僚が困っているときに「自分には関係ない」と突き放すのではなく、助け舟を出す。その行動が職場の雰囲気を和らげ、信頼を築きます。
人は「してもらう」より「してあげる」ことで、本当の意味で強く、豊かになります。なぜなら、人に与える行為そのものが、自らの誇りや喜びとなり、自信へとつながるからです。相手が感謝してくれるかどうかは問題ではありません。自分が「できることをした」という事実が、人を内側から成長させてくれるのです。
不安や困難に立ち向かうために
若い時期は、まだ経験も浅く、不安や困難に直面することが多いものです。将来が見えず、自分の力に自信を持てないとき、「もっと助けてほしい」「もっと導いてほしい」と願いたくなるのは自然です。しかし、そのときこそ「自分に何ができるか」を考えることが大切です。
例えば、社会に不安が広がる時代にあっても、自分が小さな光を灯せば周囲も照らされます。困難な状況でも、自分が一歩を踏み出せば仲間が続いてきます。どんなに大きな問題も、誰かが「私がやる」と決意した瞬間から動き出すのです。
困難を嘆くより、自分にできることを探す。未来を心配するより、今できる行動を重ねる。そうした積み重ねが、必ず自分と周囲の未来を明るくしていきます。
自己中心から利他へ
「何をしてもらえるか」を基準に考えると、どうしても自己中心的になってしまいます。「自分に利益があるか」「自分に都合がいいか」という視点が強くなり、人との関わりも取引的なものになってしまうのです。
しかし、「自分が何をできるか」を考えるとき、人は自然と利他的になります。相手のために何ができるか、社会のためにどう貢献できるかという発想が生まれます。その利他的な行動は不思議と自分自身を豊かにし、周囲からも信頼と尊敬を集めます。
本当の幸せは「してもらう」ことでは得られません。「してあげる」ことの中にこそ、人間の喜びや誇りがあります。だからこそ、若いうちから「自分ができること」を探し、実行する習慣を身につけることが大切なのです。
主体的に生きる勇気
主体的に生きるとは、決して簡単なことではありません。自分にできることを考えると、時には失敗することもあります。周囲から理解されないこともあります。それでもなお、自分の足で立ち、自分の意志で行動する人は、確実に成長していきます。
他人に依存する人生は、安易に見えて不安定です。状況や相手の都合によって左右されるからです。しかし、自分にできることを考えて行動する人生は、たとえ困難があっても揺らぐことがありません。なぜなら、自らの意志に根差しているからです。
勇気を持って「自分は何ができるか」を問い続けること。それが、自立した人生を築く第一歩です。
若者へのメッセージ
これからの時代を生きる若い人たちにとって、この言葉は大きな指針となります。社会は急速に変化し、未来の予測が難しい中で、多くの人が不安を抱えています。そのような時代に求められるのは、「してもらう」ことを待つ人ではなく、「自分にできることを探し、行動する」人です。
自ら動く人は、人の信頼を集め、仲間を得て、大きな道を切り拓いていきます。与える人は、やがて与えられる人にもなります。逆に、してもらうことばかりを望む人は、最後には孤立し、自らの可能性を閉ざしてしまうでしょう。
若いときにこそ、この言葉を胸に刻んでください。「人に何をしてもらえるかより、自分が何をできるかを考えよ」。この姿勢を持ち続ければ、どんな困難な時代でも、自分らしい生き方を貫き、周囲に光を与える存在になれるはずです。
感謝を込めて
上甲晃先生が残してくださったこの言葉は、単なる人生訓ではなく、人として生きる根本的な姿勢を示す道しるべです。私たちはこの言葉を胸に、受け身ではなく主体的に、依存ではなく自立を目指し、利己ではなく利他の心で歩んでいきたいと思います。
先生が人生をかけて語り続けてくださった熱意と真心に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
#いい言葉 #うれしい #名言 #歴史 #大事なこと #開運 #すごい #幸せ #潜在意識

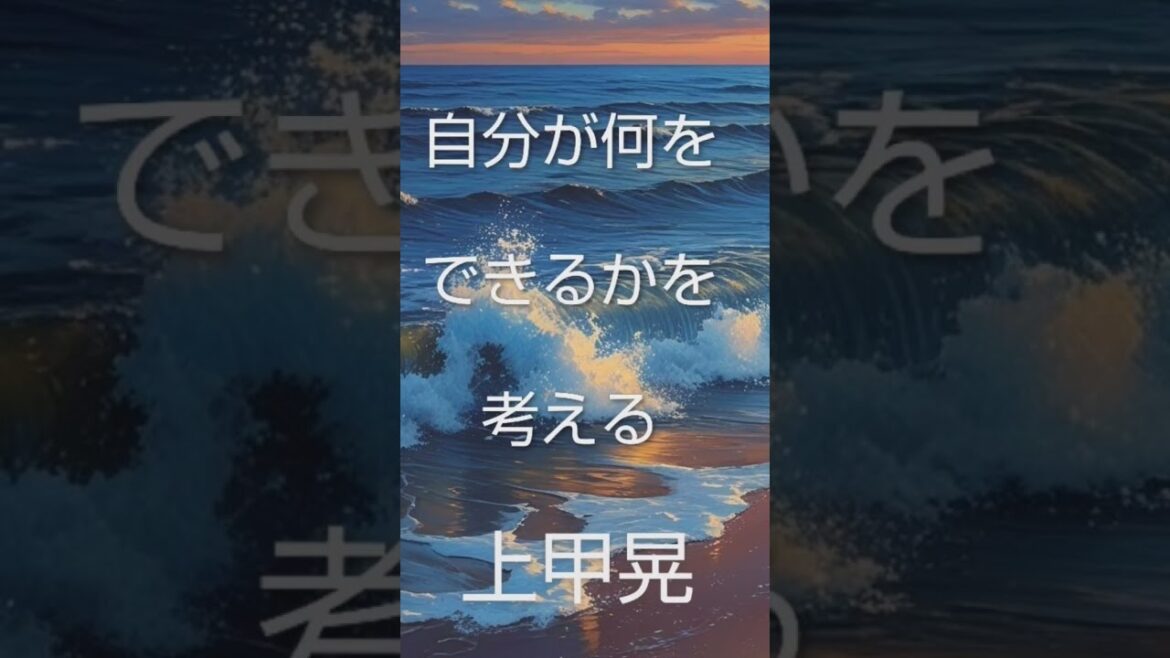
1 Comment
自分の一番の理解者は自分自身です