【学校では教えてくれない】武将や足軽は合戦中に何を食べていた?陣中飯の真実!歴史解説
元世は法色の時代と呼ばれて親しいのじゃ が、最近は何やらあ、米が高騰しておって 、ちょっとした米騒動になっておるよう ですな。それは戦国時代も同じこと。限り ある食材をどうにか工夫して食べるしか ありませぬ。とりわけイサでは武将様から 足柄に至るまで厳しい食生活を強いられて おったのじゃ。 ここで小度は人飯、活を取り上げつつ、どんな料理や食材が存在しておったのか詳しくご紹介してまいりましょう。 食感と味は最悪。洗浄の保存とは?天井へ出る際長期保存が効く食材は欠かすことができません。冷蔵庫もない時代ですから保干して水分を抜くことで腐敗を防いでたわけですね。 そんな保存色の代表格が星です。まず星は 一旦炊いた米を天秘にさらしカラカラに 乾かしたもの。作り方は単純ですが保存が 効いて持ち運びしやすく洗浄赴く兵たちの 蛍光色として重宝されました。また一般 家庭でも作られていて万が一の非常となっ ていたようです。さらにあらかじめ熱が 加わることでアルファ化しており、栄養を 吸収しやすい利点がありました。ところが 、本来なら水に浸たして戻すのですが、 これが数時間もかかってしまうのです。 あの、徳川イアスですら、4時間ほど水に つける方が望ましいと述べたほど。もし 兵士なら悠長に時間をかければ済む話です が、緊迫する戦場ではそうもいきません。 中にポリポリ食べたり、河戦中でも口の中 へ放り込んでいたはずです。また飲み水が 手に入りにくい洗浄では基本的にそのまま 食べることが前提でした。もちろん食感は いまいだったことでしょう。奥場に挟まっ て不快な思いをしたり、ましや米本来の 風味など感じられません。きっと味けない ものだったに違いありません。ただし最悪 だったのが雨の場合です。星は乾燥させて あるから保存が効くのであって、もし濡れ てしまえば腐敗したりカが生えてしまい ます。こんなものを口にすればお腹を壊し ますから、なくなく捨てるしかなかったと か。そうならないよう で包むなどしっかり保存していたそうです 。同じ保存色の中でも特に人気だったのが カオブでござる。これは勝武士に通じる ため 勝ち喜ぶと共に戦の演技となり申した。 また長期間の保存が聞きまするし、栄養化 も高く汁に入れれば出汁がよく出るため 大変だったのじゃ。そんなカツオ節を生さ へ持ち込むものの歩もたくさん折り申した 。どじゃこれは大きくて立派なカツオブ じゃろ。我が妻が作ってくれたのじゃ。 おほほ。これはうまそうだ。お主もカお節 を自散したのではないか。これ見せてくれ ぬか?持ってくるには持ってきたが ちょっとばかり時間が足らなくてのまだ はまじゃ それはカツオ節ではなくなりというのだ。 言うならば生クってことよ。の模範という のはカオ節のように削り硬い中義を持つ ことが最も大切だとされてきました。 とある江戸時代初めの文献にはこう記され ておりまする。良き侍というのは9馬の道 を極め義を磨き真をしての心を削る人に カオ節とも言わること。 が重宝された理由が分かりますよな。 味けなく口の水分を全部持っていかれる戦国のカロリーメイトとはもう 1 つ戦国時代の保存として注目を集めているのが老癌です。 地方によって材料や製方は異なるものの 一般的には小麦粉やすりごま、そばコ、酒 といった材料を水で練り、団子上に丸めた 後で乾燥させます。食感を良くするために 無視焼くこともあったとか、欲しいと 同じく乾燥させることで保存が効きますし 、その分軽くなるので携帯しやすい利点が ありました。 についてはあの紅葉軍官にも記されていて 山に入り民家を離れて7日食事を立つとも これを用いれば元気を増し力衰えずとあり ますから兵たちの行動職として万能だった に違いありません。ちなみに表老癌1つ 食べるだけで1日の必要カロリーを摂取 できたと言いますから、まさに戦国の カロリーメイトと呼んでもいいでしょう。 ただし大きな問題だったのがその味と食感 です。現代でも表老癌を再現したレシピや 実際に食べさせるお店もありますが、それ は砂糖を加えたり旨味調味料を混ぜて食べ やすくしただけに過ぎません。当時の表老 癌は乾燥しているだけに口の中の水分が 持っていかれる食感だったようです。また 味がほとんどしないためとても美味しいと は言えない白物でした。 中には事業のために挑戦ニンジンを混ぜ込んだ表癌もあったらしく、とてつもなく苦かったと言います。 戦国時代保存というのはサ場での食事だけでなく日々の暮らしにも欠かせないものでござった。 [拍手] とりわけ独願と伊達伊達伊宗様は保存職の 研究に熱心だったようで仙台浄化に わざわざおそぐという日本初の味噌工場を 作らせたほど日や食のことを考えておられ たのじゃろう。つい先日殿が考案された シミ豆腐あれがスコプル評判でござい まする。 かうまかったと思うすか?考えた会があったというものじゃ。 [音楽] それでとのそれがしがなのをご存知でございましょう。できれば今度は甘いものが食べございまする。 全くそ置は台の大人のくせにオ子みたいなことを申すのじゃな。曲がった。待っておれ。いつものように屋で考えるな。 しばらくしてロついに完成したぞ。これは枝豆をりつぶして砂糖を加え餅の上に乗せたじゃ。これをずんだ餅と申す。 [音楽] あら、これは素敵でございますなあ。 ちなみに宗様は食への探求心がすごすぎて自らを作ることもござり申した。 将軍徳川イ光様には豪華な表な自然を 振る舞れ、その包丁さきを絶賛されたそう 。その際料理の内容や調理法を味みや配善 に至るまで全て正宗様が監修されたと言い ますから一流の料理にもびっくりの腕前 だったんですな。飲み込めないほど まずかったお米とはご飯といえば誰もが 白いお米を想像するでしょう。しかし戦国 時代の日本では白米と赤米が共存していた ようです。古代の日本人が赤米を食べてい たことはよく知られていますよね。さて、 平安時代から鎌倉時代にかけて日本へ 伝わってきたのが大東という品種です。 いわゆるジャポニカと違って水電が不要と いうメリットがありました。単外技術が 未発達だった当時水電が作られるのは平置 に限られていたためなかなか農業生産量を 増やすことができません。その点等は野生 に近い品種ですから痩せた土地であろうが 3地であろうが湿地であろうがどんな環境 でも栽培が可能でした。ただし水分を吸い にくい性質があるため炊いても全然 美味しくありません。時間をかけて蒸す ことで柔らかくしていました。ただし問題 だったのがその味です。普通の白米と違っ てアミロースやタンパク質が多く含まれて いるので粘りがなくさらに単人の影響で 極度の渋みが出ることでした。つまり白米 とは全く別の食材と考えた方がいいのかも しれません。食感がボソボソしてしかも 渋いというのは一体どんな味だったの でしょう?朝鮮の通信士として日本を訪れ た王神はこのように述べています。上級 以外のものはみんな赤米を口にしている ようだ。実際に食べてみたが、渋すぎて喉 を通らず飲み込むことができない。およそ いの品種の中で最悪の部類に入る。 おそらく火球士や足軽たちはこの大当を 日常的に食べていたのでしょう。しかも 白米より1割安かったそうですからいくら まずくても我慢しながら食べていたと考え られます。 やがて江戸時代に神殿開発が進んで白米がたくさん取れるようになると大米は次第に姿を消していったのです。 美味しくない藤も去ることながら過酷なサではどんなにまずいものでも食べねばなりませぬ。とりわけまずいと形用されたのが次なという野草でござった。 [音楽] ちなみに奉の部分は尽しと呼ばれておりの じゃが問題となるのは歯の部分でござった 。さて武田市滅亡の際田信之様は弟信茂様 と共に故郷のさ田の賞へ逃れようとされて おりた。しかし背後からお手が迫っており 仕方なく3に分けるしかありませぬ。あ、 兄上、もう何日も食べておりませぬ。もう 倒れそうでございます。け次郎しっかり気 を持つのじゃ。おお、あそこに杉が生えて おるぞ。確か食べられると聞いておる。 [音楽] 兄上、1刻ほど似ておりますが、一向に 柔らかくなりませぬ。うむ。仕方がない。 あ、ここにとまっても折れるし。ここらで 触してみよう。う、なんじゃこの味は。 おへえ。これはアークが強いの。しかも硬 すぎて木の枝を噛んでおるようじゃ。これ は飲み込めよ。こ年松代となった信は当時 のことを思い出され、杉名は花肌食べ づらきものと述べられたそうじゃ。 確かに杉は煮るとまずいのじゃが、実はつくだにしたり天ぷらにするとおしくいただけると言いまする。 あのいいおマさも泣いた。究極の激末まず味噌汁は古くは中国大陸から伝わった味噌ですが調味料として広く認知されたのが室町時代のこと。 ただし効果で流通量も少なく大名や一部の 上級部資のみが味わえるものでした。庶民 は元一般の武士ですら味噌汁にあり付け なかったと言います。一方社会全般に普及 したのがぬかみそです。ただし大豆や麦が 原料ではなく生まのぬかを用いた味噌でし た。パッと見た感じは普通の味噌汁と 変わらないためみんなぬかの汁を飲んでい たんですね。さて、肝心の味ですが一口 飲むと全然違うことがわかります。 そもそも一般の味噌と違って味も風味も 感じられずとても口にできるものではあり ませんでした。さらにぬか湯油が多いため 嫌な雑みや後味が残ってしまうのです。 ちなみに徳川四天皇として知られるいい 直正についてこんな逸話があります。ある 時主徳川家康に従ってカへ出人した直正は 祝ろ大久保たよからうまいものを食わせて やろうと誘われたそうです。早速ただの陣 を尋ねたところすに鳥たや本田安げ若い 家臣たちがいて今か今かと料理を待ってい ました。直もそこで待っているとしばらく 立って出てきたのは芋汁だったそうです。 他の者たちが美味しそうに食べる中にも ワンが振る舞われました。そして口にして みるのです。すると直はすぐに顔を歪め ました。これはぬかみそか。彼の出身地で あるは裕福な国で、しかも実家は今川市の 過震筋という家柄。これまで直正が ぬかみそを口にすることはなかったのです 。一方、咀嚼に慣れている三川武節にとっ てぬかみそは当たり前の味でした。周りの ものが食べる中、直マだけはどうにも箸が 進みません。するとただよがマンチをなぜ 食べないと声をかけてきました。さすがに 美味しくないとは言えないは醤油があれば 食べやすくなるのですがと答えてしまい ます。立ちまち周囲のものが戦場にそんな 贅沢なものがあるかと色めき立ちますが、 ただよはこのように確めました。我らは 芋汁を食べられるから恵まれている。身分 の低い者たちはそれすら口にできぬ。その 言葉を聞いた直正ははっとなり、この芋汁 の味を決して忘れはしない。 これからは部下を愛し、民を慈しむようにしようと誓ったそうです。 さて、料理の味付けは出身地によって異なるもの。織田信長様についてこんな逸話がありまするる。信長様が上落された直後のこと美助の料理人をしておったという壺内という男を捉え申した。 [音楽] 兼ねてから恐風の味付けに興味がござった信長さも早速料理を作るように命じられまするじゃが。おお、これが強料理というやつか。どれどれ。ん?なんじゃこの味付けは?こんなものが食えるか? [音楽] いや、そんなはずは。あ、これは立派な今料理でございます。 おい、料理にわしをなめるなよ。もう1度 機械を与える上、ちゃんとしたものを作れ 。さなく首じゃ。しかし調理場へ戻られた ツ様は困り果てられた。そこで何をしても 打ち首になるのこと焼けっぱじゃ。えい。 醤油に味噌。それから塩こ玉ぶち込んだっ たらよ。おろし。 [音楽] よし、食べてやろうではないか。 [音楽] おお、これはうまい。やればできるはない か。今後はわしの料理人に取り立てて 使わす。そう。日頃から鍛錬などで体を 動かされておる信長様にとって故郷終わり の味はスコプル濃い目の味付けだったの じゃ。まずい人中ばかりじゃない。魅惑の 戦国グルメとはとにかくまずい料理食材 ばかりをご紹介してきましたが、もちろん 洗場には美味しい料理も存在していました 。ここからは魅惑の戦国グルメと題し、 戦国部将たちのうますぎる活戦飯の数々を 登場させたいと思います。まずは文庫の 大友総林です。当時文庫の府内には多くの 選教士たちが不教に訪れていたのですが、 復活祭で総林に振る舞われたのが魚介を 炊き込んだ色のついたご飯でした。今で 言うパエリアのことですね。味の良さに 感激した総林は同じものを選しに作らせ ました。これが大田の強度料理王の元に なったとされています。ただしご飯に色を つけるのは本来ならサフランですが日本に あるはずもありません。そこで疾口 なしを代用したそうです。総林はこの料理 を陣中でも好んで食したようで度々家臣に 振る舞うこともあったとか。続いてご紹介 するのが島ず軍の食を支えた悪巻きという 料理です。これは大陸から伝わった血巻き が期源だとされ、妄想地区の川で包み、 独特の形に整えたもの。まず持ち米を悪に 浸たした後、竹の川で包み、そこから数 時間2個目は出来上がりとなります。悪の アルカリ製で米が柔らかくなり、さらに 雑菌の繁殖を抑えられますから長期保存に 向いた料理と言えるでしょう。悪魔は古く から人中として親しまれ、あの島ず義博も 大好物だったと言います。朝鮮出平では よその軍勢が木で苦しむ中、島ず軍だけは 食に困らなかったとされていますね。また 炭水化物や糖分、ビタミンやミネラルを 多く含むため体力維持や疲労回復に役立ち ます。 まさに活飯に売ってけのグルメだったに違いありません。 最後に飼の武田神玄様が特に好んだという料理をご紹介いたしましょう。ある戦でのこと新たに観した家臣が腹をかせてまいりました。するとかねた信玄様が自らを振る舞うと言い出されました。 [音楽] 親様慣れたて付きでございますな。 あ、これは何という料理でございましょうか? 私はタゴの出身へわからんでやろう。これは当してな。貝の強度料理じゃ。わしがよく作るから武田汁ともす。 見るかに美味しそうでございます。 そうであろう。彼は山ゆに米が取れぬ。 だから麦を育てて平打ち面にするのじゃ。そこに [音楽] 3 歳やらやらを超えればそれだけで立派の人中食になる。 それにしても麺が不ございます。あ、これは食べ応えがありそうな。 見た感じのように見えるであろう。 だから頭と頭をかけてみたんじゃ。どじゃろうはは。もう [音楽] 1 つ神玄様が愛した料理といえばアビの姿にでござろう。ただし海は海のない国でございまするから新鮮な魚介は手に入りませぬ。そこでまく運ぶために公案されたのが合わびでございます。 もちろん保存が聞きまするし、干すことで アミノさんなどの旨味成分が増していくの じゃ。まさに一隻日常の食材だったわけ ですな。活戦中の人飯のお話はいかがだっ たじゃろうか。今のお主たちのご飯がわし ら戦国時代と比べてどれだけ恵まれておる か感じていただけたじゃろうか。もし 人食べたことがござるものがおったらやみ コメントしてくだされ。さてさて、我ら 武将隊は名古屋城で毎日草働きをしており まする。しかし元世の活性の人色は恵まれ ておりますな。名古屋城では名古屋名物の 騎士麺も食べられますしの。 是非名古屋城に来て食べてみてち待っておりますぞ。 最後に10大発表でござる。この度公式 LINEが出来申しだ。公式 LINE では歴史を学べるクイズ初級中級上級とござるで挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城出人情報も分かりますのでこれから名古屋城に来る方は来る前に登録してくださいませ。 登録は無料でござる。概要欄からどしどし 登録お願いいたしまする。の陣のことも 知ることができるこの天国雑長チャンネル 登録援軍しておらんものはほれはい。援軍 チャンネル登録押して押して押した。ほん で良いね高評価も押して押してはい。ほん でやぶみコメントも書いて書いてれうん。 してくれたからはい。ありがとさんじゃ よし。はい。それではまた [音楽]
現世は「飽食の時代」と呼ばれて久しいのですが、最近は何やら米が高騰して、ちょっとした米騒動になっているようです。
それは戦国時代も同じこと、限りある食材をどうにか工夫して食べるしかありません。
とりわけ戦場では、武将から足軽に至るまで厳しい食生活を強いられたようです。
そこで今回は「陣中飯・合戦飯」を取り上げつつ、どんな料理や食材が存在していたのか?詳しくご紹介してみたいと思います。
◆公式LINEを開設!ぜひ、ご登録ください。
https://liff.line.me/1657596280-v27Xmxo3/landing?follow=%40631ylvss&lp=Uub7x6&liff_id=1657596280-v27Xmxo3
(名古屋おもてなし武将隊公式LINE)
■名古屋おもてなし武将隊は16周年!
https://busho-tai-shuunensai.jp/
■出演
語り:踊舞(名古屋おもてなし武将隊)
TikTok https://www.tiktok.com/@touma1560
X(twitter) https://twitter.com/touma_bushotai
ナレーション:なつ(名古屋おもてなし武将隊)
Instagram https://www.instagram.com/ngy_natsu/
■企画制作/ほまれWORK
work.homare@gmail.com
■BGM/若林タカツグ
https://x.com/cocoa2448
https://youtube.com/@Takatsugu
【出演団体紹介】
■名古屋おもてなし武将隊HP ぜひ、名古屋城に会いにきてください。
https://busho-tai.jp/
■BGM:若林タカツグ
https://x.com/cocoa2448
https://youtube.com/@Takatsugu
#歴史,#日本の歴史,#足軽

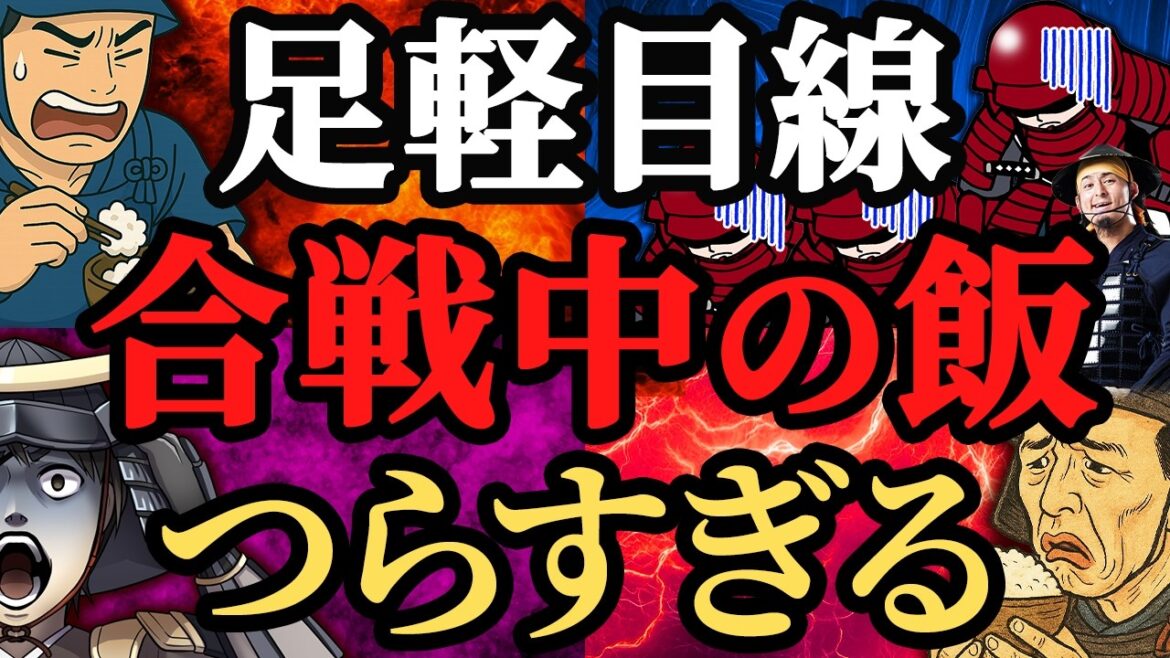
17 Comments
空腹の
一口飯の
宝物
美味い不味いも
勝てない空腹
初陣する時って、戦に慣れてないから、めちゃくちゃ飯が不味く感じるんだよなぁ。塩欲しくなっちゃう
ずんだ餅が出てきたところで「ずんだもん」が出てきたら面白かった
元陸自です、経験から思うに兵士の楽しみは食事です。
平時でも献立表を見ては好きなメニューの日を心待ちにしていました(私の場合はハムステーキ)。
演習メシは私の時代は缶飯が主流でしたがこれが結構美味しい、特に好きだったのが牛飯と鳥飯、これが今のパック飯より数段ボリュームがある。
副食では沢庵の缶詰(後に一人一つの大きさになりましたが二人で一つのやつ)、あの組み合わせは最高でした!
私は戦車兵でしたので歩兵の方達より多くの荷物を持てたと思うのですが、ソーセージの缶詰の汁を捨て代わりに醤油を入れ携帯コンロで煮たヤツ、あれも美味かったそれをつまみに皆と一杯やったのを思い出します。
今も昔も食事の内容は士気の上下に大きくかかわると思います。
陣中食グルメ漫画の登場も近いか!?
兵糧丸は武士も足軽も持って行ったのですね。当時、食料持参で戦いに臨むのは移動だけで体力を使うのに、散々歩いて戦をするとか目眩がしそうです。
「雑兵物語」も面白いですよ。
眞田信繁(幸村)の薩摩落ち(その3)
滋野氏から海野氏、望月氏、根津氏が分かれた。海野氏から眞田氏が分かれた。村上義清に侵略された眞田幸隆は武田信玄に仕えた。眞田幸隆には信綱、昌輝、昌幸、信伊などの子供がいた。眞田昌幸には信之、信繁(幸村)、信勝、昌親などの子供がいた。
眞田信繁(幸村)には阿菊、於市、阿梅、あぐり、幸昌(大助)、御田姫、阿昌蒲、おかね、女(石河備前守貞清室)、女(青木次郎衛門室)、大八(守信)、幸信、之親、瓢左衛門がいた。薩摩落ちし眞田信繁(幸村)の子が瓢左衛門である。
実は真田氏のルーツに関して「海野氏の末裔である」ということ以外、詳しいことは判明していません。しかも、その海野氏も、平安時代末期に木曾義仲に従った「海野幸親(うんのゆきちか)」以前のことはほとんど判明していません。
滋野氏は平安時代初期に編纂された『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』という系譜集によると、「紀直同祖(きのあたい)」で、「神魂命(かみむすびのみこと)五世孫天道根命(あめのみちねのみこと)」の末裔とされています。天道根命は天皇の末裔ではないので、平安時代には滋野氏は天皇家とは血縁の関係のない一族であると考えられていたことがわかります。
※紀直(きのあたい):紀伊国造(きいのくにのみやつこ、現在の和歌山県知事のようなもの)の一族で、紀貫之などの紀氏とは別の一族)と同じ一族という意味。
どのように信濃国に土着あるいは勢力を築いたのかについては、「地方官が任地に土着し、地方豪族となる例は少なくなかったので、滋野氏もそうであった」という説や、「滋野恒蔭や善根やその子供が直接信濃国に根付いたのではないが、寛弘6年(1089年)に信濃国から献上された馬の処置を司った、善根の子孫と考えられる『滋野朝臣善言(しげののあそんよしこと)』がいるように、早くから信濃国と滋野氏には深い関係があった」という説、「地方官が任地において荘園を経営したことは頻繁にあったので、滋野氏も荘園の管理者として信濃国に土着した」という説などがあります。
滋野家訳が滋野宿禰の姓を賜る前は伊蘇志臣を名乗っており、家訳の祖父が伊蘇志臣の姓を賜る前は「楢原造(ならはらのみやつこ)」を名乗っていたのですが、この「楢原」は、現在も東御市にある「奈良原」に由来するという説もあります。ただし、楢原という地名は大和国(現在の奈良県です)や播磨国(現在の兵庫県です)にもあったことが判明しているので、確実ではありません。
秀頼、幸村の大坂城脱出
大坂の陣が始まる前に、豊臣秀頼は、“島津の退け口”で勇名を馳せた島津義弘に丁重に出陣を要請したが、断わられている。というものの、過去のいきさつもあって、島津義弘は、秀頼を救出することにした。島津義弘は徳川家康に味方する約束をしていたのに、伏見城を守る鳥居元忠が島津義弘を信用せず、「そのようなことは聞いていない」と言って島津義弘隊を受け入れなかった。そのため、行きがかり上、島津義弘は西軍に属することになった。関ケ原合戦後に島津義弘が徳川幕府にその経緯を説明するとともに、島津義久が薩摩藩の国境警備を固めた。加えて、徳川幕府に改易されそうになり、いざ合戦となった場合は、合戦で有利になるように豊臣秀頼を隠し球として確保しておこうしたのかもしれない。
島津の軍勢は西軍のために兵糧米500石を大坂城中に運び込み、その帰りに眞田信繁(幸村)・大助幸昌親子、豊臣秀頼・国松親子、木村重成らを密かに救い出した。家康が河川の多い低湿地帯となっている大坂城の北西方面に手厚い陣を布けなかったことを幸いなことに、眞田信繁(幸村)や豊臣秀頼らは、島津家家臣・伊集院半兵衛が京橋口から忍び入れた小舟に乗り、急流に乗って一気に川口まで下って、本船に移った。夏の陣の頃は梅雨の季節で、大和川(寝屋川)、平野川や淀川はなみなみと水をたたえ、その合流した急な流れに乗ることができた。
この秀頼救出劇は、江戸中期の作家上田秋成が書いた『胆大小心録』の中で、大坂西町奉行所与力内山栗斎の女中から聞いた話として書かれている。その女中の母親は、18歳から木村重成に仕えていた女性である。また、『厭蝕太平記』『玉露証話』『備前老人物語』の中でも、これは述べられている。また、最近、「秀頼脱出~豊臣秀頼は九州で生存した」(前川和彦著、国書刊行会刊)」という本が発行された。
「島津外史(鹿児島外史)」などによると、眞田信繁(幸村)らは、京橋口より軽船に乗り河港に出て、そこから瀬戸内海を進み、兵庫経由で島津の大軍艦に乗って、鹿児島湾(錦江湾)に辿り着いた。眞江田家に伝わる伝承によると、眞田信繁(幸村)は、この時、親鸞上人が書いた直筆の掛軸、秀頼から頂いた「おねぐい」の鞍などを鹿児島に持ち込んだ。
大坂落城のとき、大坂城の北、天満方面にはほとんど東軍の姿はなく、城兵は自由に逃げ出せる状態にあった。参戦したら、北方、西方に配置される予定だった西国方面の大名はほとんど戦に間に合わなかった。7日の夕方落城し、翌日にはすでに京都あたりへ大勢の落人が逃げのびていった。名のある武将で逃亡した者も少なくなかった。その中でも、長曾我部盛観、大野道犬治胤、秀頼の息女(7歳)らは逃亡中捕えられ、息女(7歳)は尼にされた。この息女(7歳)と息子国松(8歳)を除き、みな殺された。
豊臣秀吉から豊臣姓を称することを許されていた眞田信繁(幸村)が秀頼とともに薩摩へ落ちのびたという噂は早くからあったらしく、「花の様なる秀頼様を、鬼のやうなる真田がつれて、退きものいたよ 加護島へ」と京童に歌われた。実際には、秀頼は背丈が6尺5寸(197cm)で、水戸泉のような体格をしており、酒好きであった。逆に、眞田信繁(幸村)の方が小柄な優男であった。一方の眞田信之(幸)は身長185cmもあり、93歳まで生きた。眞田信之(信幸)は正妻(公家)の子で、眞田信繁(幸村)は側室(農民)の子だったが、本当は信繁(幸村)の方が兄だとする説もある。更に2人の上に兄がいて、長男が源一郎、次男が源次郎信繁(幸村)、三男が源三郎信之(信幸)とする説もある。
当時のイギリス東インド会社平戸商館長リチャード・コックスは、元和元年(1615)6月5日の日記に「秀頼様の遺骸は遂に発見せられず、従って、彼は密かに脱走せしなりと信じるもの少なからず」と書きしるし、同じ日付で「皇帝(家康)は、日本全国に命を発して、大坂焼亡の際、城を脱出せし輩を捜索せしめたり、因って平戸の家は、すべて内偵せられ、各戸に宿泊する他郷人調査の実際の報告は、法官に呈せられたり」と書いている。
また、コックスは、それから1カ月半後の日記になると「秀頼は薩摩か琉球に逃げのびた」という報告を書きとめ、京都から来た友人(イートン)の「秀頼様は今なお重臣の5、6名と共に生存し、恐らくは薩摩に居るべしとの風聞一般に行はるる」との話も後世に伝えた。
後に、オランダ商館長ティツィングの訳をクラプロートが増補した仏語版「日本王代一覧」によって、兵庫経由での薩摩落ち伝説は欧州にも紹介された。
鹿児島外史は「秀頼は京橋口より軽船に乗り河港から大軍艦に乗り~(中略)~(薩摩)谷山村の在す」と記している。
歴史研究・作家の加来耕三は、平成29年1月13日にテレビ東京の「古代ミステリーたけしの新世界七不思議大百科」で「汚穢船を使って堀へ出て堀から更に小さい川に出て、幅が大きくなったら大きい船に乗り換えて、最終的に兵庫沖で薩摩の船に乗り換えたという話が結構ありますから」と言っている。
おそらく島津の軍船は太平洋側を航行したために徳川の探索に引っかからなかったのだろう。実際、幕末の西郷隆盛も徳川幕府の関所に引っかからないようにするため、太平側を航行し、大波で揺られ、難儀したとある。
眞田信繁(幸村)の薩摩落ち(その4)
秀頼、幸村の薩摩入り
『採要録』によると「大坂落城後、鹿児島の南一里半ほどの谷山村(旧谷山市、現在の鹿児島市谷山地区)へ、どこからともなく浪人が来て住みついた。島津氏から居宅を造り与えられ、日常の費用も与えて何不自由のないようにしておいた。同じころ、薩摩の浄門ケ岳の麓(現在の鹿児島県南九州市頴娃町牧之内・雪丸)にも、風来の山伏が住みつき、また、加治木浦(現在の相良市加治木町)にも浪人が来住して、この3人は時に打ちつれていることがあった。谷山にいたのは秀頼、山伏は眞田信繁(幸村)、加治木の浪士は木村重成で、秀頼の子孫は木下姓を称し、重成の子孫は木村姓を称している」としている。
眞田信繁(幸村)は、鹿児島県南九州市頴娃町牧之内・雪丸(鹿児島弁では「ゆんまい」という)に住んでいた。眞田信繁(幸村)の墓はこの雪丸にある。ここの「くりがの」小学校にその記録である「頴娃村郷土誌」が保管されている。
雪丸(幸村がいたことから、雪村(せっそん)と呼ばれたが、のちに雪丸(ゆきまる)と呼ばれるようになった)に辿り着いてから、眞田信繁(幸村)は息子大助を「秀頼公をどうしてご出馬さ.せることができなかったのだ!」と大声で叱責した。大助も負けずに反論したため、口論となった。両方ともとてつもない大声で口論しつづけていたため、地元の人間はみな驚き、「不可思議に想った」と在地の伝承は伝えている。
肥前平戸藩主、松浦静山の随筆である『甲子夜話』、島津外史(鹿児島外史)、薩藩旧記などは、眞田信繁(幸村)について、次のように報告している。谷山時代に芦澤左衛門という名の八百屋がいたが、その家には、眞田信繁(幸村)の武具や刀などの品々があり、一介の八百屋にこのようなものがあることを当地の人たちは不思議に思った。頴娃に着てからも、こうした品々を持ってきたため、彼がかの有名な眞田信繁(幸村)であろうと当地の人々は噂していた。当人は決して眞田信繁(幸村)と名乗ったことは一度もなかった。
なお、『甲子夜話』は、薩摩には島津外史(鹿児島外史)というものがあり、これは漢文で書かれており、いささか読みづらいとしながらも、これを引用しつつ、眞田信繁(幸村)や豊臣秀頼についての記録を残している。
「谷山村郷土誌」(明治45年刊)によると「大坂夏の陣で戦死したはずの眞田信繁(幸村)が豊臣秀頼を護衛して堺の町に逃げ来たり、舟に乗って薩摩に亡命した」とある。鹿児島の上福元町には秀頼の墓と伝えられる宝塔が福元一雄氏の自宅敷地内にある。鹿児島文化財審議会の木原三郎氏が調査・鑑定したところ「秀頼の存命年代よりも古い時代の作であり、おそらく平姓谷山氏初代兵衛尉忠光の墓だろう」ということである。秀頼には伊茶(渡辺五兵衛の娘)という側室との間にできた8歳になる国松がいた。この国松にも生存説がある。
江戸時代の眞田幸村の子孫と眞田幸貫・松浦静山の甲子夜話
頴娃村郷土誌によると、眞田信繁(幸村)は、雪丸で島津家から与えられた居宅に住み、頴娃村摺木在の百姓某の娘に身の回りの世話をしてもらっていた。眞田信繁(幸村)は、この女性と恋仲になり、女性は身ごもったが、落ち武者の身であり、申し訳ないと思い、鹿児島県南九州市頴娃町別府・大川の浦人某に嫁がせた。
この結果生まれた子が、筆者の先祖(瓢左衛門─ひょうざえもん)である。
この瓢左衛門(ひょうざえもん)の後、周八、佐平次、菊蔵、武右衛門、佐平次(2世)、眞江田菊蔵(2世)、難波周八(2世)と続いた。叔父さん(故人)によると、新しく立て直す前の難波家の墓に代々の眞江田家の名前が刻まれていた。今の難波家の墓はその後立て直されたものである。眞江田家は、徳川の世も終わりに近い幕末になって藩主から苗字帯刀を許された。そのとき、先祖・眞田の名前をもらい、眞江田と名のるようになった。
当時の薩摩はまるで独立国家のようで、しかも辺境の地にあり、幕府も容易には手出しができなかった。まして、確証でもない限り、強制捜査などとうていできる訳がなかった。大勢に影響がない以上、事を荒だててまで、落武者狩りをすることは得策ではないというふうに、徳川幕府が考えたとしても別におかしくはない。
眞田信繁(幸村)直系の子孫である眞江田家では、江戸時代から眞田の姓を名のろうとしていたが、徳川への遠慮から控えていた。眞田信繁(幸村)の子孫は徳川幕府に遠慮しながら、江戸時代を通じて一貫して身分を隠して生き続けていた。
松代眞田家の第8代藩主・眞田幸貫は、この異説について調査を行い、その結果報告を見せてもらった肥前国平戸藩の前藩主・松浦静山の「甲子夜話」には「大坂落城の時、豊臣秀頼は潜かに薩摩に行かれたという一説あり。此の事、異域、(中国)へも聞こえたると見えて、『涌幢小品』に秀頼が兵敗走して和泉に入る。城焚きて死す。また薩摩に逃げ入るという者あり…」と記述するとともに、「これに拠れば、眞田信繁(幸村)は大坂に戦死せしには非らず」と、薩摩落ちを肯定する感想を述べている(『甲子夜話続編』)。
一方で、眞田幸貫は、幕末も近くになると、いろいろな書物に書かれたことから、幕府も松代眞田家の第8代藩主・眞田幸貫に尋問した時、「往時のことは戦火にて記録焼失して判り申さず」と逃げている。なお、眞田幸貫は、松平定信の2男で、眞田家の養子となり、のちに、老中として幕閣にも参加した人物である。
『甲子夜話』は「信幸は、眞田三代記に眞田信繁(幸村)の薩摩落ちが語られたことから、頴娃の眞田信繁(幸村)と目されるこの人物に使いをやったが、使いの問いに対して、幸村は、(落ち延びた身であり、使いが本物かどうかも分からないので、間者かもしれないと疑心暗鬼になり、)自分が眞田信繁(幸村)であることを認めなかった」としている。
天保14(1843)年に成立した眞田家の家譜「先公実録」中に幸村の伝記「左衛門佐君伝記稿」があるが、その中になど枚挙にいとまがない。「大坂の陣のあとに流行った童歌で『花のようなる秀頼さまを 鬼のようなる眞田がつれて 退きも退いたり 加護島へ』というものがあり、鹿児島へ逃げ延びたとする童歌が存在する」「頴娃郡の浄門ケ嶽の麓に風来の山伏がおり、地元の人も恐れていたが、これが眞田信繁(幸村)だった」と記されている。
おんなじだな、😅😅😅😅😅😮😮😮😮😮😮😢😢変わんねーな
500年近く経った現代でも山梨名物の武田信玄のほうとうはどれだけ美味しかったのだろう。ご馳走になってみたいものだ。
ほうとうは宝刀だったのか😮
信玄公はだだすべっとるけどw
放蕩なら作ったことがある、美味しかった( ´∀` )、
戦場では食べられることに感謝しなければいけない。とは言われますが、
戦国時代だと他の問題としてメニューが単調・食中毒とかいう問題もあったのでしょうね。
糠味噌は味はともかく、栄養の面では文句なかったと思いますので、そういう面では
食して良かったのではないかと思います。
「体に悪くてもいいから美味しいものが食べたい」というのが兵隊さんの本心だった
のではないかとも思えますが('ω')
あくまき、食べたことあります。独特の食感で美味しかったです!
海の無い国は鰹節手に入れるの大変だったやろな。
えっ、ずんだもん?(笑)
マズくても食べないと戦出来んからな。
大唐米
あの貧乏な李氏朝鮮の通信使ですら食えない不味い米つて…
陣中食
アゴ紐とかヒモとかに味噌を染み込ませて、ヒモ(蔓)が食べれるようになってたのよね
ひどい味より味がない方がマシ