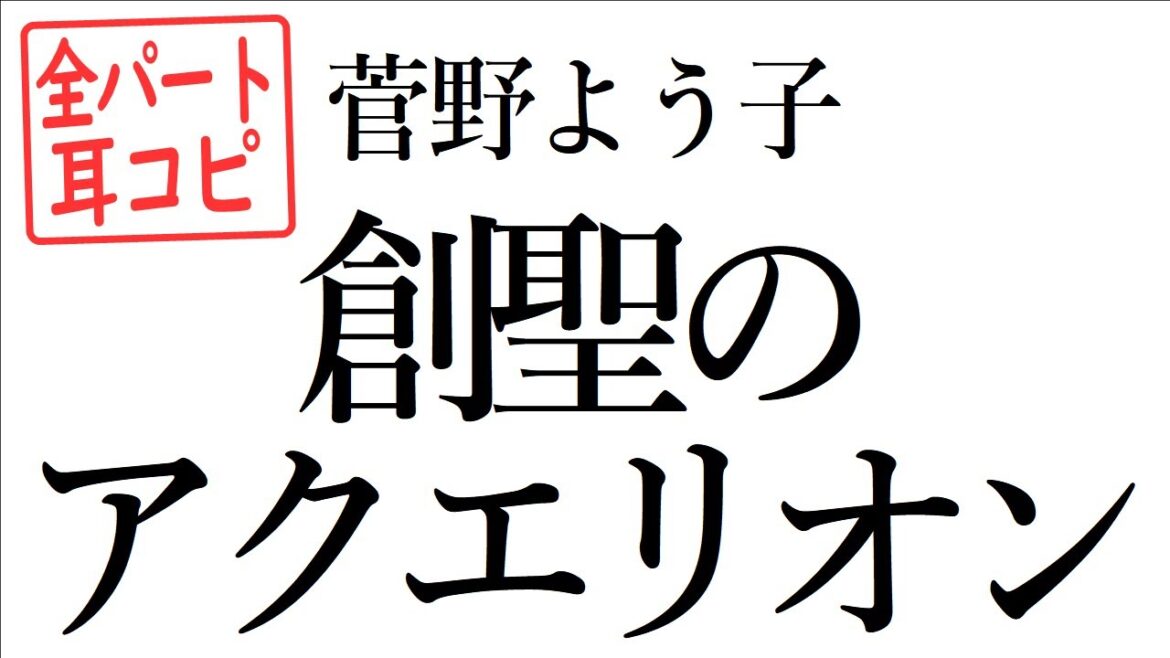菅野よう子『創聖のアクエリオン』の全パート耳コピ楽譜です。
トイドラによる楽曲分析(アナリーゼ)つき。
質問・意見はコメントにて。
〈総評〉
【楽式】
・典型的な「Aメロ-Bメロ-サビ」。
→サビでいきなり全音上に転調して盛り上がる。
【リズム】
・Bメロ以降、表打ちが目立つハッキリしたリズムに。
→特にサビが顕著。地に足ついた勇壮な感じ。行進曲のニュアンス?
・冒頭だけなぜかフラメンコ調。
→菅野よう子の引き出しの多さ。
【メロディ・和声】
・メロディがフレーズ終わりに高次のテンション(9th・11th)へ到達することが多い。
→瀟洒で浮いた感じ。菅野よう子の特徴。
→Aメロ冒頭、Bメロ全体など。
・VIM7の響きが効果的に使われ、軸となっている。
→特に「Im – Im7/VII – VIM7」というクリシェ。
→「VIM7 – III/V」というクリシェも印象的。
・コード進行が保続音を軸に考えられている。
→伸ばしっぱなしの弦の下でベースラインだけ動くなど。
→シンプルなコード進行でも、テンションや非和声音が多くなり響きがおもしろくなる。
・コード楽器とメロディ楽器にそれぞれ個別の動きをさせる。
→コード楽器はテンションを鳴らさずアルペジオでのみ鳴らす、コード楽器とメロディ楽器で和音が異なる、など。
→和音の響きは濁らせず、メロディラインのうまみも妥協しない。良いとこどり。
・ただの完全4度(空虚4度?)が使われている。
→ふつうは全く使われない和音!
→多義的な解釈が可能で浮いた響き。
・肝心なシーンで意外な和音を使う。
→前奏の果敢な2転、Bメロ前やサビ終わりの和音、サビ直前の転調誘導など。
【表現】
・メリハリのつけ方がとても巧妙。
→曲調がいきなり変わる。
→サビや間奏でいきなり転調する。
→弦が伸ばし続けていると思ったら突然細かく動く。
→クリシェを基本とした簡単なコード進行かと思ったら、キメで複雑なコードが一瞬出てくる。
☆常に予想を裏切ることで飽きさせない。ポップスの基本。
————————————————————————————-
作曲家のトイドラ → https://tomita-haruki.studio.site/
#菅野よう子
#創聖のアクエリオン
#音楽理論