今日の話題は
日本史から消された謎の部族サンカ 絶対に調べてはいけない理由がヤバすぎる…【 都市伝説 】をお届けします。
【おススメ動画】
今じゃ考えられない遊女の食事のヤバイ闇!
ヤバすぎる日本史の謎 闇に消された空白の150年
今じゃ考えられない平安時代の日常生活は!?現代と違いすぎる1日
実はせつを匿って生きていた?比企尼の生涯、せつのその後【鎌倉殿の13人】
【鎌倉殿の13人】善児はなぜ一幡を殺さずにかくまったのか?命令がなければ子供には手を出さない?【歴史雑学】
#日本史の謎 #歴史

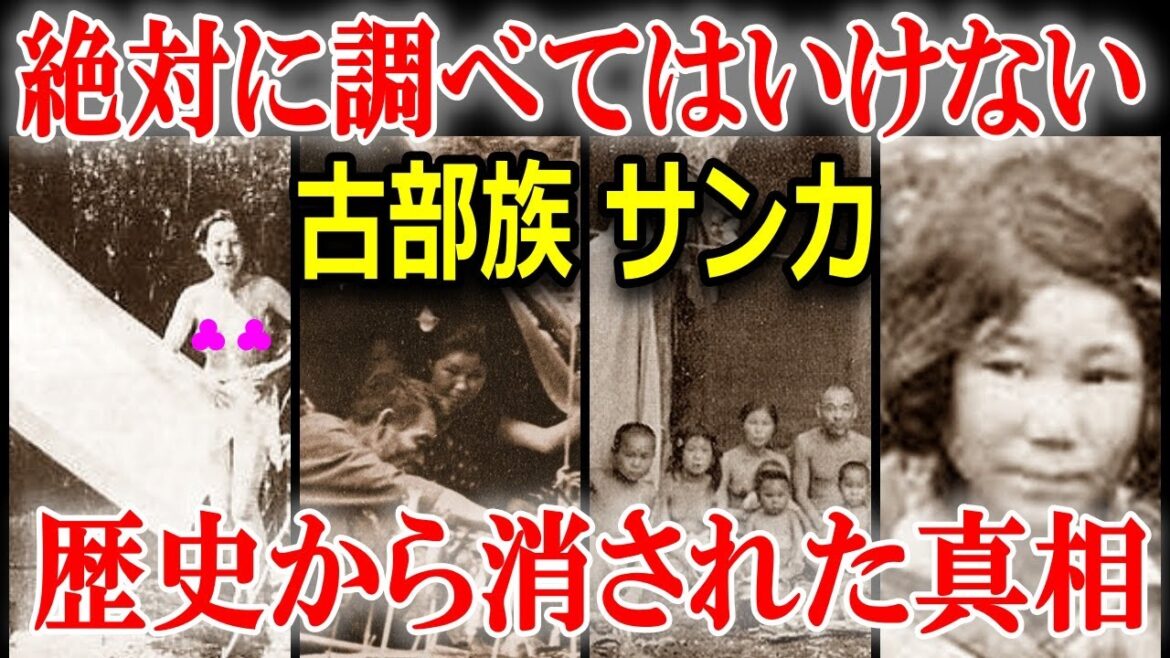
30 Comments
多分サンカが理想だろうね。
サンカ民族が消された理由は「イエスキリスト」を神としなかったからだ。
皮多のように、職業による差別ではないかと・・・
太平洋戦争行きたくなくて、山で隠れてたんじゃ?
山窩は部族でしょうか?
職業やアウトローを指す言葉に感じますが?
話盛りすぎてない?笑
自分も若い頃に同じ職業の人に聞いたことが有ります、山の中でも暮らす人がいることを聞きました、やっとわかりました。
戸籍がなかった人たちがどうやって就籍したのだろう?戦後就籍届などの件数に変化がないとすれば、戦死者などに成りすますしか日本人となることはできそうにも無い気がする。日本人化した可能性よりも、インフルエンザなど新しくもたら荒れた病気による死滅も考えられるのではないか。
ある程度の結論が出てることをロマンティックな話だから焼き直すんだろうなという印象
室町時代~近代にかけて貧困やその他の事情で山に住んだ人でいまの日本人と別民族ではないという結論だったと思います
大体どこの郷土史にもサンカの話しは出てきますよ。文化の発展は西と東だとかなり差があるので九州〜近畿であればヤマト朝廷の時代6〜8世紀くらいには租庸調に耐えらなかった下人(一般庶民)は租税を放棄して家族単位またはムラ単位で山中に生活の場を移した集団がいたのでしょうね。その子孫は静かに暮らした者もいれば、後の山賊みたいな生活をした者もいると思います。
またこんなファンタジーが
アイヌとかと同じ
行政の目に届かないところに
社会生活できないグループが住み着いただけ
実際にサンガは人里離れた山奥には住んでいない
日雇い労働で現金収入を得るから
里山近くそれも県境に住んでいた
警察が来たら隣の県に逃げるため
徴兵逃れが多かったからね
サンカ→山歌、テアトル新宿の映画館で鑑賞いたしました😮もともと文語に興味がありましてサンカ語の漢字が画数が多く鳥肌がたち深く追及したくなりました😅
つかみが悪すぎて見たくなくなるどうがですね。
縄文時代の遺跡がある市町村へ物を売り渡り歩く集団の様に思う 縄文から昭和まで続いていたのは驚異 みつくり池・みつくり井戸とか各地にあるが水源を開発・確保し そこをキャンプ地として移動か
1972年頃の中国地方ですが、サンカの話題は家庭内で普通に出ていました。山の中でサンカを見たとか。私はまだ幼少でしたが、今80歳以上の年配者からならもっと具体的な証言を得られるはずです。この方々が存命のうちに早急に聞き取り調査などの研究をすべきだと思います。
つまり各地方にいる無宿者という事?
「サンカ」って部族なの?
ただの無宿人の集まりを「サンカ」と名付けたんじゃないの?
そんなサンカなら、今でも大勢居ますよ。
椋鳩十 著の 鷲の唄 サンカの人達の事が 大胆に 牧歌的に 書き表してあります。令和の現代においては 考えられない 《 どこぞの?世界?》の話のようですが……‥。
今でも 案外 世界の秘境と呼ばれる 何処かの場所では サンカに近しい生活を送る 民が おおらかに ひっそりと 暮しているのでは と思います。
古くは縄文人、熊襲、蝦夷、隼人、アイヌ等の民族的に異なる集団、もっと時代が下っての、民族としての違いはなく、様々な理由で一般社会から離れて、定住せず山や川で暮らす人々等、様々な人等が古来、点在的にいたんではないでしょうか。
特殊な社会ルールで繋がるいわゆる狭義のサンカと呼ぶべき集団が存在した可能性も高いが、そうした人たちが全てこうしたサンカであったとは考えにくい。
それほど一般社会と一線を引きながらそれほど広域的であることも無理ではと思う。
一般社会の一部ではあっても、山奥で自給自足的に暮らす人々も古来いたし、街で普通の暮らしをする人にとって、違いは区別できにくかったはず。
サンカを見た、という情報のどこまでがいわゆるここにいう狭義のサンカかは怪しいものもあると思う。そもそも近代的な戸籍は明治以降の話。
多くは都市伝説ないしは、定住せず山で暮らす人々への被差別民意識の結果ではないのかと想像する。
政府、地方行政は、兵役や徴税のため、定住せず戸籍を持たず山で暮らす人々をいわゆる教義のサンカを含め定住させ、戸籍をもたせる取組みをしたはず。戸籍は5代前まで遡れるので、丹念に戸籍や行政の記録を調べれば「創籍」、経緯も確認できるのではないか。そうした調査はしてきたのだろうか?
民俗学的に何らかの痕跡(信仰等の)がないのも不思議です。
次はサンカ利権か
忍者の下人の一族じゃないだろうか(ノ´∀`*)
よくわからない人々の総称がサンカだったのでしょうね。
その人たち自身、『自分はサンカ(名称が何であれ)だ』という意識はなかったと思えますし。
欧州におけるジプシーに似ているような気もします。
ジプシーは『価値観の違う定住しない人々』なんですが、一般人から見ると『ドロボー』だった側面もあるようです。
サンカに生きる場所があった時代…少し憧れます。
私は昭和22年東京の世田谷生まれですが子供のころ夕方外にいるとサンカに拐われると叱られた記憶が有ります。多摩川辺りに居たようです。
神奈川中央部ですが昭和40~50年代にサンカっぽい人家族が農家の軒下借りて何日だか何週間だか住んではまた何処かへ行くという人達が毎年居たそうで、それっぽい家族連れを自分も若干1度だけ商店街で露店で物を売っているのを見た事があります。
全然知りませんでしたが、調べてはいけない理由は特に無いと思います。
調べたくもね~よ😂
樹海村のチャンネルで出てきた「言葉が通じない」で口論するおじさんが怪しい。
文献に照らせば、そもそもサンカは古部族ではありません。 サンカに関する著作は、古くは
柳田国男、三角寛らのものが有名ですが、最近では沖浦和光氏の一連の著作が学術的見地か
らもっとも信頼できるものだと思われます。都市伝説を語るのも結構ですが、その前に事実
として確認できるもの、仮説、噂や妄想、この三者は分別して語るべき。
もののけ姫は、サンカの話を元にして作られたものなんですね。
20年ぐらい前でしようか テレビ番組では最後のサンカ的な表現で数人のサンカのかたが登場されていました。 サンカ方の服装や仕事も普通でしたが これからは普通に溶け込んで生きてゆくで終了していました。
茨城のおじいちゃんが山の中で暮らしている民がいると昔教えてくれた。
子供の頃だったからサンカとは覚えてないけど、税金払わなくていいじゃんとか大人同士で話してた気がする